予期せぬ来客
本当になんて美しい女性なのだろう。
彼女の金髪は、蚕の繭から取り出したばかりの糸に似ている。一本一本が細く、柔らかそうな艶を放つ。瞳は近くで見ると、ごく淡い水色。アルカルドの瞳が深い湖を思わせるなら、彼女の瞳は春の空を連想させる。
なめらかな白い肌、高貴な面立ち、ふっくらとした薄桃色の唇。ただし彼女の流麗な眉は、怪訝そうにひそめられたままだ。
応接室で、フィリスは突然の来客と向かい合って座っている。アルカルドは村で行われている会合に出かけていると聞いた。壁際に控えるドルモアやバルローはいつもと変わらぬ様子に見えたが、室内には確かな緊張感が漂っている。お茶を運んでくれた従僕は非常に硬い表情をしていた。
状況を考えれば仕方がない。
デルフィーヌはアルカルドの婚約者だった女性だ。王命により、その婚約はなかったものとされ、フィリスが嫁いだのである。
デルフィーヌは無言でお茶を飲み、フィリスも挨拶のあとは黙っている。先程から視線が合わないため、どうしたものかと会話の糸口を探している。
するとデルフィーヌが大きなため息をひとつつき、花模様のカップを静かな動作でテーブルに戻した。そしてようやく、向かいに座るフィリスの顔を見た。
「家柄のせいではなかったはずです」
いきなり、そう言った。
「家柄?」
「わたくしも伯爵家の娘です。ましてや、今の王妃様は同じ家門のご出身。わたくしの伯母にあたります」
舞踏会に出席する貴族たちについては、名前と出身地だけは全員分頭に入っている。そもそもクレルモン家からは彼女の兄が参加する予定になっていたはずだ。デルフィーヌに関してはもと婚約者であることくらいしか聞いていない。ドルモアが気を利かせたのかもしれない。
「家柄のせいでないのなら、アルカルド様があなたを選んだ理由はなんだったのでしょう。わたくし、到底納得しておりません」
フィリスは頷いた。
「それで一足早く、当家にいらしたのですね」
「迷惑でしたか」
「いいえ」
彼女はどうやらとても正直な人のようだ。フィリスを見る瞳には苦悩が感じられる。正直で、そして、アルカルドのことを強く想っていた……今も。
「わたくしの場所を奪った方を、どうしてもこの目で確かめたかったのです。家柄で負けていないなら、何が原因かと。いかに王命だったとはいえ、アルカルド様はロシェル公のご嫡男。お断りすることもできたはずです。わたくしたちは幼い頃からの婚約者だったのですから」
フィリスには答えようがない。それは王や、アルカルド本人にしか分からない。
ただ、とても申し訳なく思う。幼い頃から彼に恋をしていたのはフィリスも同じだ。突然婚約を破棄されたからといって、想いを断ち切ることができるはずはない。
「こうして実際にお目にかかって、わたくしはさらに混乱しています。あなたのような方がエントワーズ侯爵夫人だなんて。未来の公爵夫人だなんて」
デルフィーヌは燃えるような目でフィリスを睨みつける。瞳の縁が屈辱のためか赤く染まって、唇が細かく震えていた。
ごほん。大きな咳払いをしたのは家令のバルローだ。
「お嬢様。長旅でお疲れでございましょう。よろしければお部屋にご案内いたします」
「わたくしが」
さっと近づいてきたのはドルモアで、テーブルの上のティーセットを手早く片付け、従僕が持つトレーにどんどん乗せてゆく。
「お部屋の支度は整っております。さ、どうぞ」
ドルモアにしては礼を欠いた対応だ。デルフィーヌは明らかに気分を害している。
「控えなさい。わたくしはまだ、こちらの方にお話がありますの」
「侯爵夫人でいらっしゃいます」
やんわりとドルモアが言った。
「こちらの方、とは。失礼ですが、フィリス様はすでに当家の奥方様でいらっしゃるので」
「……あなた。わたくしを馬鹿にしているの?」
「いいえ、まさか」
あくまでも穏やかに応じるドルモア。デルフィーヌがどん、とテーブルを拳で叩く。いけない。フィリスは慌てて腰を浮かせた。
「デルフィーヌ様。お部屋へのご案内はわたしがいたします。途中でお話をお伺いいたします」
デルフィーヌはドルモアをねめつけると、次にバルローを睨み、従僕や、壁際に控えるクロエまでをも順番に見た。
「……わかったわ。短い間にずいぶんといろんな人間を懐柔したこと」
それは品がある言い方とは思えなかったが、もちろん口にすることはできない。フィリスは先に立ち、廊下へと誘った。
デルフィーヌはごねることはせず、案外、あっさりと着いてきた。少し離れてドルモアとクロエ、それから、デルフィーヌのお付きの侍女らしいやや年配の女性も続く。
ホールに出たところで、デルフィーヌが唐突に言った。
「ひとつだけ教えてくださいな。本当のことを」
「なんでしょう」
「あなたは、アルカルド様と本当のご夫婦になられたの?」

フィリスは一瞬、意味が分からずきょとんとした。
「本当の夫婦……」
「一緒の寝室でお休みになられたのかと聞いています」
ああ、そういうことか。なるほど、フィリス自身も悩みのタネだった例の問題について訊かれたのだ。ただ初対面で、しかも妙齢の娘に、さらに立場的に恋敵ともなる相手に、単刀直入に訊かれるとは思わなかったため、すぐに意味をはかることができなかった。
反応が遅れたフィリスにデルフィーヌはさらに美しい顔を近づけ、畳み掛けるように続ける。
「どうなのです? わたくしのお友達は意に沿わぬ結婚をさせられて、半年は寝所を共にしなかったと言っていました。あなた方も実際はそうなのでは? だってあまりにも突然の結婚でしたもの」
「クレルモンのお嬢様! 失礼ではございませんか」
ドルモアが蒼白になって割って入ろうとする。
「部外者はお黙り!」
デルフィーヌは高い声で制した。赤く染まった目の縁からは、大粒の涙がぽろぽろとこぼれ落ちてくる。
「はしたない質問をしていることは分かっています。でもわたくしにはその権利があるわ。この王国で、わたくしだけは、アルカルド様のご結婚が本物かどうか、知る権利がある」
その通りだ。フィリスは心から、そう思ってしまった。
デルフィーヌが言うことはもっともだと。
「……結婚は本物です。わたし、旦那様を……アルカルド様をお慕いしております。でも」
「でも?」
噛みつくような勢いでデルフィーヌが問いかける。
「でも、なんなの? 早くおっしゃって」
「……でも。まだ、本当の夫婦ではありません。デルフィーヌ様の定義がそういうことであるならば」
刹那、デルフィーヌは勝ち誇った顔をした。
「やっぱり! そうだと思ったわ! アルカルド様はわたくしを裏切ったわけではなかった。あの方はあなたを本当の妻とは認めていらっしゃらない!」
フィリスは驚いた。
「どうしてそんなことを」
「どうしてですって? お分かりにならないの? アルカルド様があなたを抱かない理由は、まだ、わたくしを愛しているからよ。王命によってやむなく結婚式はあげたけれど、彼の心はまだわたくしにある」
高らかに宣言するように言われ、フィリスは言葉を失った。周囲にいる人間もみんな呆然としている。
どうしよう。メイドの噂話とは比較にならないほどの破壊的な言葉の数々。この場合、どう返事をするのが正解なのか。
すると、表が少し騒がしくなり、
「……クレルモン家の馬車だな。どういうことだ……」
怪訝そうな声と共に、アルカルドが玄関ホールに入ってきた。
「アルカルド様!」
デルフィーヌの方が反応が早かった。呆然と立ち尽くすフィリスの肩を押すようにして、彼女はアルカルドに駆け寄った。
「デルフィーヌ? いったい……」
帽子を脱ぐ間も与えず、デルフィーヌは倒れ込むようにアルカルドに体を寄せる。咄嗟のことで、アルカルドは彼女を支えた。
「デルフィ……」
「わたくし、わたくし……ああ、何もかも信じられなくて、いてもたってもいられなくて」
デルフィーヌは嗚咽と共にそう言った。実際、彼女は臆面もなく泣き始めている。あの常に冷静なアルカルドさえ困った様子で泣きじゃくる伯爵令嬢と、それから、フィリスを交互に見た。
「落ち着いて。なぜ君が来たんだ。俺は兄上に招待状を送ったはず」
「どうしてもお会いしたかったのです。だってひどい……わたくしはアルカルド様に嫁ぐ日だけを夢見て生きてまいりましたのに……こんな……こんな」
さらに号泣するデルフィーヌ。アルカルドは彼女を落ち着かせようとしてか、一歩下がって距離を取ると、身を屈め、彼女の顔をのぞきこむようにした。
「泣かないでくれ。あちらで座って話をしよう……」
しゃくりあげながら、デルフィーヌが頷く。アルカルドは彼女の肩にそっと手を置き、先程までいた応接室へと促した。
それから顔をフィリスに向け、軽く頷く。フィリスも頷いた。
ここは任せておけと、そういう意味だろう。
「奥様。よろしいのですか」
ドルモアがそばまで来て小声で尋ねる。アルカルドとデルフィーヌは応接室へ入り、ドアが閉められた。
「仕方がないわ。わたしが行ったら、ますます感情を逆なでしてしまう」
「しかし、あんな失礼なことを言われて、腹が立たないのですか」
腹を立てているのはドルモアだ。フィリスはどちらかといえば……ただただ、困っている。
「いいの。それより夫人。わたしを庇ってくれたでしょう」
ドルモアは苦虫を噛み潰したような顔をする。
「いいえ。とんでもない。ただ当家の使用人として至極当たり前なことを言わせていただいただけです」
バルローやクロエも無言のまま頷いた。フィリスは微笑んだ。
「お客様用のお部屋の確認に行きましょう。デルフィーヌ様には西の青の間がいいかもしれないわね」
客間の中でもっとも美しい部屋だ。後ろに続くドルモアはぶつくさ言った。
「まったく。お人が良すぎるってものですよ……」
違う。そうではない。フィリスは自分の正しい態度が分からず、そして……恐ろしいのだ。
アルカルドがデルフィーヌを抱きとめ、泣くなと言った時の表情や、彼女の肩を優しく押した姿が目に焼き付いている。
胸の奥がざわめいて、遅れて湧き上がってきた感情を、もてあましている。
どうか、と願うのだ。
たったの二年でも構わない。息子を取られても諦める。
ただ、どうかわたしを、わたしのままで、あなたのそばにいさせて―――お願いよ、アルカルド……。
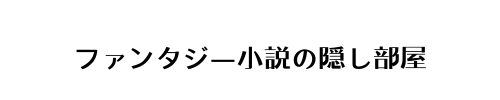


コメント