嫉妬
木漏れ日が手の甲に繊細な模様を編み出している。フィリスは籠を地面に置いて、両手を光にかざした。
エントワーズの屋敷からほど近い森に来ている。故郷の森に比べれば小さいが、屋敷の中にいるより、ずっとくつろぐことができる。
ベリー類や食用に適した茸もまあまあ採れるし、ウサギや狐の姿も見かけた。
屋敷に多くの客人があった時などは、盛大な狩りを行うことがあると聞いている。
狩りだったら、あの方に負けないのかしら。
ふとそんなことを考えてしまう自分を恥じ、フィリスは俯いた。
振り返れば、木々の間からエントワーズの大きな屋敷が見える。
今頃あそこでは、デルフィーヌがアルカルドとともに午後のお茶をいただいているかもしれない。
彼女がここに来てから三日。フィリスにとっては、気の休まらない日々だった。
デルフィーヌは、朝こそ貴族の令嬢らしく遅めの起床のようだが、そこから就寝時まで、なにかとアルカルドのそばにいようとする。昼食、午後のお茶、晩餐。日に三度は着替えているが、どのドレスも目を見張るほど見事で美しかった。
さすがに深夜の書斎への立ち入りはフィリスしか許されていないものの、日中、デルフィーヌはかなり自由に振る舞っている。
特に使用人への態度は、目に余る。部屋の掃除がなっていないとアニカが呼び出され、叱られたと聞いた。
フィリスは驚き、謝りに行った。しかし、
『あなたが謝る必要はありませんわ。だって本当の女主人じゃないんですもの』
そんな鋭い言葉で追い返されてしまった。
デルフィーヌは、エントワーズのあらゆる職種のメイドを呼び出した。肌着にまでアイロンを当てさせたり、庭の遠くの東屋へお茶を運ばせながら、そのお茶の味に文句をつけて淹れ直させたり……また、晩餐のメニューにも、細々と注文をつけ、コルテスを怒らせたという。
さらにフィリスを憂鬱にさせるのは、彼女がアルカルドへの想いを隠そうともしないことだ。何かと理由をつけては彼のところへ行き、世間話をしたり、一緒に庭を散歩してくれるようにねだったり。
いたたまれない。
彼女の美しさに圧倒されるばかりか、その奔放な振る舞いに困惑し……また、羨ましく感じてしまう。
あんな風に、自分の感情のままに振る舞えるのは、それが許されてきたからなのだろう。伯爵令嬢として、何不自由なく、ありのままでいることを許され、愛され、まっすぐに育ったのだ。
他人をここまで羨んだことなどなかったのに。
それでも侯爵夫人として、フィリスはゲストをもてなす立場にある。だから意を決し、彼女をお茶に招き、自分で焼いた菓子を振る舞おうとした。
しかしデルフィーヌは頭痛と吐き気がすると言って来なかった。フィリスがクロエに薬草を届けさせると、そのまま突き返された。
特にアルカルドと三人での晩餐は、苦痛の極みだ。デルフィーヌはフィリスが知らない幼少時代の話や、互いの家族の話をして、フィリスを会話から締め出した。アルカルドが気を使って妻に話しかけると、デルフィーヌはとたんに顔を曇らせ、ぽろぽろと泣き出してしまう。これにはアルカルドも対応に困り、弱りきった顔をする。
そして、そんな様子の夫を見ると、なぜかフィリスが、非常に申し訳ない気持ちになってしまう。
アルカルドにも、デルフィーヌにも、申し訳ない。
では、いったいどうすればいいのだろう。フィリスは煮詰まってしまい、こうして森に逃げてきたのだった。
「奥様」
ふと横合いから声がかかる。さすがに森の散策にひとりで来ることはドルモアが許可してくれず、侍女のクロエを連れてきていた。
散策ついでにと、熟れたブラックベリーやハーブを、一緒に収穫していた。
「そろそろ戻りませんと。晩餐の着替えの前に入浴されてはいかがでしょう」
確かに今日は久しぶりに汗をかいた。フィリスは笑顔で応じる。
「そうね。じゃあさっき摘んだばかりのラベンダーをお湯に入れようかしら」
「それは素敵ですね」
クロエは真顔で頷く。口数がとても少なく、表情もあまり変化しない侍女だが、彼女が持つ穏やかな気配がとても好きだ。
「ブラックベリーはどうなさいますか」
「マフィンを焼こうと思うの。ラベンダーはたくさんあるから、サシェにして屋敷の皆さんに配ろうかと」
屋敷の皆さん、とは使用人たちのことだ。
「皆喜ぶと思います」
「でもこれはクロエだけに。ほら」
フィリスは小さな果実をクロエに手渡した。
「まあ、桃ですか」
「向こうに自生している木があったのよ。たくさん実がなっていたけれど、これだけが食べ頃だったみたい」
「よろしいのですか。わたくしなどに」
「もちろん。とてもいい香りでしょう」
クロエはうつむき、両手のひらに乗せた小さな桃の香りをかぐ。
「……懐かしいです。生家の庭に、大きな桃の木がありました。毎年、誰が一番に実を食べるか揉めたものです。なにしろ弟妹がたくさんいたものですから」
クロエが実家の話をしてくれるのは珍しく、フィリスは優しい気持ちになった。
「そうなのね。きっとクロエのことだから、いつも自分は後回しだったのでしょう」
クロエは小さな目を瞬く。
「おわかりになるのですか」
「わたしの歳の離れた従姉妹たちもそんな感じなの。わたしは一番年下だから、従姉妹たちがけっこう甘やかしてくれたのよ」
「わたくし、一番に桃をいただくのは初めてです」
「ふふ。来週あたり、また一緒に来ましょうね」
クロエは頬をうっすらと染めた。
それからふたりは並んで歩き、屋敷へ向かった。歩きながら、クロエは自分のことをぽつりぽつりと教えてくれる。
弟妹が多く、食い扶持を減らすために、十三歳の時に、ハウスメイドとして奉公に出たこと。
懸命に働き、メイドとしての経験を積んだが、侍女に憧れ、勉強したこと。なんとか紹介状を書いてもらい、エントワーズには半年前に雇われたこと。
「故郷には、たまに帰るの?」
「いいえ。ここからずいぶん遠いのです。もう十年も帰っていません」
「そうなの……」
「時々夢に見ます。お土産をたくさんカバンに詰めて故郷に帰るのですが、走っていって、家のドアを開けても……誰もいないのです。なぜか当時飼っていた猫のオブリーだけが出迎えてくれて」
フィリスは籠を反対側の手に持ち替えて、クロエと腕を組んだ。背の高い彼女に、ぎゅっとくっつくようにすると、彼女は怪訝そうにフィリスを見下ろす。
「奥様?」
「すぐには難しいかもしれないけれど、もう少ししたら、長めのお休みを取ればいいわ。馬車を出してもらえるように、わたしから旦那様に頼んでみる」
「そんな。いけません。わたくしはまだこちらに上がって間もない身ですのに」
「わたしだってそうよ」
フィリスは明るく笑った。
「お土産もたくさん持って帰るといいわ。わたしにも選ばせてくれると嬉しい。それで、待っているわね。今度はクロエが、故郷のお土産話を、わたしに持って帰ってきてくれるのを」
「奥様……」
本当は、フィリスもすでに生家が恋しかった。二年後には戻ることになるのだが、今すぐに、川を越え、故郷の森の中を駆けて、駆けて、ひんやりとした石の城に駆け込みたかった。
そんな風に思うのは、不安だからだ。アルカルドのことだけを考えて嫁いできた。まさか自分が、こんな感情に翻弄されるとは思わなかった。
アルカルドとデルフィーヌが一緒にいるところを見ると、胸が苦しくなる。
分かっている。立場的に、アルカルドはデルフィーヌに負い目があると考えている。いくら王命だったとはいえ、彼女は長い間、彼の婚約者だった。
簒奪者はフィリスの方。
でも、苦しい。ほんの小さな笑顔ひとつ。優しい言葉ひとつ。彼女に与えてほしくはない。
フィリスは生まれて始めて自分の中に生じた、暗い嫉妬と、独占欲に恐れおののいている。
静寂と、緑の息吹に包まれたら、浄化されるような気がした。そうでもしないと、フィリス自身が、あの魔物に取り込まれてしまいそうだから。
ドール―ガ。まだ、つかまえていない。屋敷の中で、あの魔物に付け入る隙を与えてしまうのは、ほかでもない自分自身かもしれない。そんな可能性を考えてしまい、ひとり、怯えた日々を過ごしている。
それでも唯一の救いは、アルカルドの右腕が着実に回復していることだ。魔の穢れはほぼ浄化し終えた。もともとアルカルドの体は、鍛え上げられた強靭なものだった。腕の痛みや違和感が薄れるのと並行し、剣の稽古を再開したことも結果的にとても良かった。
おかげで、浄化魔法もだいぶ楽なものになってきている。昨日あたりから、飢餓にも似た食の欲求は薄れ始めている。それでもフィリスは意識して、たくさん食事をした。正直、デルフィーヌが同席している晩餐では、食べたものの味がよく分からなかったが、心の中で作ってくれたコルテスに謝りながら、黙々と食べ続けた。
デルフィーヌは心底軽蔑したようにフィリスを見ていた。
『まあ。フィリス様は伯爵令嬢とはいえ、ずいぶんと苦労されたのですね。まるで貧民街の者たちみたいなご様子ですこと』
フィリスはただ、微笑んでみせた。
飢餓感がなくなっても、しばらくは食べ続けなければならないのだ。力を蓄え、取り逃がした魔物の欠片をつかまえ、退治するために。
舞踏会が終わり、秋の気配を感じる頃には、アルカルドの右腕は完全に良くなるだろう。今のフィリスの最たる願いは、彼が再び、もとの力と元気を取り戻すこと。
それに尽きる。
そう。だから、デルフィーヌへのくだらない嫉妬や、ましてや対抗心など、抱く必要はない―――。

エントワーズ侯爵夫妻の寝室は、左右に夫婦それぞれの衣装室と支度部屋がある。フィリスが入浴と着替えのために寝室に入ってゆくと、アルカルドが、自身の支度部屋から従者とともに出てきたところだった。
「旦那様」
いつどんな時だって、彼に会えるのはとても嬉しい。フィリスは彼に近づいて、にこにこと笑った。
「森へ出かけたと聞いた」
「はい。クロエが付き添ってくれました。ブラックベリーが食べ頃で……」
「危険だな」
アルカルドは眉をひそめている。フィリスはぽかんとした。
「危険? でもあそこの森には猛獣はいないはずでは」
「狐に襲われたらどうする」
フィリスは思わず、吹き出した。
「狐に、わたしが?」
狐はいつだってこちらが狩る側だ。もちろん手負いの獣をいたずらに追い詰めたりしたら、何が起こるかは分からない。
それでも、普通の獣がフィリスを襲うことはない。たとえ腹を空かせた熊であっても。
「蛇もいるだろう。たちの悪い虫もいる」
「蛇がいそうなところには近づきませんし、虫は得意中の得意です」
「虫が得意とはどういう意味だ?」
しまった。フィリスは咳払いをする。
「あの……苦手じゃないという意味です。バランデュールにはそれこそたくさんの虫がいましたから。毒虫も見分けられます」
「確かに、君に森の危険性を説くのは、間違っているかもしれない」
アルカルドは俯き、嘆息した。どうやら本気で言ったわけではなさそうだ。しかし、やや不機嫌な様子にも見える。
いったいどういうことだろう、とフィリスが困惑していると。
「……俺が付き添いたかっただけだ」
横を向き、少しぶっきらぼうな物言い。
フィリスは驚き、大きく目を見張った。
「旦那様。でも……」
フィリスが森に出かける時、アルカルドは書斎にいた。一言断って外出しようとしたところ、少し開いたままのドアから、デルフィーヌの楽しそうな声が聞こえていたのだ。
だから、黙って森に出かけてしまった。
今、そのことをどう言えばいいのか、分からない。口にしたら、嫌味のように聞こえてしまいそうで。
「あの。来週も行きたいのです」
フィリスは代わりに、穏やかな声で言う。
「実は自生している桃の木を見つけて。来週あたりに食べ頃になりそうな実がたくさんなっていました。クロエとまた行く約束をしたのですけれど、アルカルド様も、よろしければ、ぜひ、ご一緒してください」
「来週というと、君の披露目のあとになるな」
「そうですね」
舞踏会は、もう五日後だ。
「明後日には両親はじめ、多くの客人がやってくるが……披露目が終われば、全員去って、再び静かになる」
全員、というところを強く言ったような。
フィリスが黙っていると、アルカルドは苦笑した。
「面白くない思いをしているだろう」
「わ、わたしは……」
そうなのです、なんて答えられるはずがない。
アルカルドが、デルフィーヌといるところを見る度に、面白くないどころか、決して褒められない、黒い気持ちが渦巻いてしまうなんて。
「ドルモアから聞いている。理不尽で無礼なことを言われたようで、すまない」
「……旦那様のせいではありません」
「いや。もちろん俺に責任がある。彼女にも謝罪し、説明を重ねている」
だから時々、ふたりで話し込んでいるのか。
結婚に至った経緯と状況を考えれば、アルカルドの立場はとても難しい。それが分かっていながら、自分の気持ちのことばかり考えていたフィリスは、己の心の狭さと幼さを痛感し、唇をそっと噛んだ。
アルカルドがそばまで来る。フィリスが俯き、顔を上げられないでいると、ふと、彼の手が髪に触れた。
「……葉っぱがついていた」
彼はフィリスの髪から、たしかに、小さな葉を取り去った。
「ありがとうございま……」
礼を言い終わる前に、フィリスはいきなり、アルカルドに抱き抱えられた。
「だ、旦那様?」
アルカルドはそのまま窓辺に歩いてゆき、窓枠に腰掛けると、フィリスを膝の上に座らせた。
「あ、あの……」
何が起こっているのが、状況判断ができず、頭が真っ白になる。
「君が俺を旦那様と呼ぶのは、距離を感じている時だ」
「あの、それは違って……」
「そうかな? 嫁いできた当初と比べて、君はどうやら元気がない。ここから、ひとりで外を見ていることがある」
はっとした。窓の向こうには、先程まで散策していた森が見える。
「故郷に帰りたくなったのではないかと、心配している」
「……違います」
いや、違わない。でも、もっともっと、複雑な気持ちが入り乱れている。
「確かに突然の結婚だった」
アルカルドはフィリスの手をそっと握った。
「だが、君と結婚できて、俺は幸運だったと思い始めている」
「旦那様……」
「アルカルドだ」
「……アルカルド」
「うん」
アルカルドは、柔らかく笑う。フィリスは胸の奥がずきんと痛んだ。
どうしよう。
もう、本当に好き。わたしは彼のことが、幼い頃より、ずっとずっと好き。
至近距離に、彼の顔がある。アルカルドも、フィリスをじっと見つめている。部屋はいつの間にかふたりきりだ。クロエもアルカルドの従者も、気をきかせたのか、出ていったようだ。
心臓がうるさい。腰に回された彼の手に力がこもる。ぐっと強く抱き寄せられ、口づけをされた。
フィリスは彼の胸に手をあてて、小さく震えながら、口づけを返した。
長い抱擁と、長い口づけのあと、アルカルドはフィリスの髪に顔を埋めて、くぐもった声で言った。
「故郷を思って、ひとり、ここから森を見るのはいい。だが……出かける時は、一緒に行こう」
睫毛が震える。熱を持ったままの唇も。すぐに返事をすることができず、フィリスはただ、こっくりと頷く。
「……ところで、もう一度、見せてくれないか?」
やがてアルカルドがつぶやくように言う。フィリスは夢見心地で問い返す。
「なにをです?」
「例の、君の、丈夫な歯を」
ぱっと顔を上げる。アルカルドがにやりと笑い、青い目がいたずらっぽく輝いている。
フィリスも笑った。
「もちろん、さあどうぞ」
気恥ずかしいのを我慢して、いーっと口を横に大きく広げ、彼にもう一度、自慢の歯を見せてやった。
それからふたりは同時に吹き出し、しばらくの間、声を立てて笑い続けたのだった。
ドアの外に立つ人物が、一部始終に聞き耳を立てていたことなど、露知らず。
森の中でも浄化できなかった不安や黒い気持ちは、嘘のように晴れた。フィリスは、この時、ただただ、つかの間の幸福に酔いしれていた。
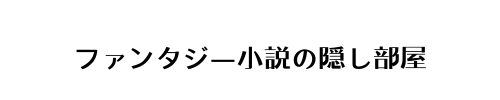


コメント