鏡の中のフィリス
とうとう舞踏会まで二日となった。明日には王都をはじめ国中から、招待客がやって来る。
フィリスは夜半、寝室で、アルカルドの寝顔を見つめている。
『君との結婚を、幸運だったと思い始めている……』
そう言ってくれた夫は、相変わらずフィリスを抱こうとはしない。
そっと右腕に触れてみる。
心の底から、安堵し、ため息が漏れた。
アルカルドが負った魔物による穢れは、完全に浄化された。想定していたより、ずっと早い。
フィリスは、大きな役目をひとつ、果たしたのだ。
『わたしの可愛い小さな姫さん』
と、フィリスのことを呼ぶ男がいた。フィリスが物心ついた頃から、年に一度か二度、バランデュールにやってくる男だ。
茶色い口ひげが特徴的で、温厚そうな男のことを、フィリスの方は、『とんがり髭の小父様』と呼んでいた。
彼は、メライアを渡る特別なクルミの舟に乗ることができる。そして、やってくる度に、フィリスや従姉妹たちにたくさんのお土産をくれた。
美しい箱に入った美しい人形、リボンやブローチ、櫛に鏡。宝石みたいに色とりどりの飴細工に焼き菓子。
彼は特に、フィリスをかわいがってくれていたと思う。従姉妹たちがお土産に夢中になっている間、フィリスは彼と、渓谷にせり出した露台でチェスをした。
いつも、フィリスが勝った。負けてばかりの彼は、悔しそうにしながら、どこか嬉しそうだった。
今年、彼が言った。
『小さな姫さん。いや、もう小さくはないな。ひとつ、わたしと賭けをしないか?』
『いいわ。何を賭けるの?』
『銀色の狼がいる。若くてとても美しいのだが、たいそう傷ついていてね。このままだと死んでしまうだろう。彼の命そのものを賭けたい』
『その狼はそんなにひどい怪我をしているの?』
『ああそうだよ。彼が弱っていくさまをただ見ているのは辛い。だからね、小さな姫さん。この勝負に、今年こそわたしが勝ったら。その狼のお嫁さんになってくれないか? そしてどうか、君の力で、助けてやって欲しい』
『わたしが勝ったら?』
『この指輪をあげよう。前から欲しがっていたね。どうだ?』
小父さんは、左の小指に指輪をしている。台座は黒ずんだ銀色で、どうやらとても古いもののようだが、石が素晴らしい。
濃い色合いの緑柱石。覗き込むと金の虹彩が確認できる。
どんなに美しいお土産よりも、フィリスはその指輪が、ずっと、欲しくてたまらなかった。
指輪が持つ力も承知していた。
今、フィリスはアルカルドの彫刻のように整った顔を闇の中で見つめる。
チェスの勝負に、負けたことは一度もなかった。
しかし、今年はわざと負けた。
小父さんはそのことをじゅうぶんに理解していた。フィリスが銀狼の戦神に恋い焦がれていることを知っていたから。
フィリスはアルカルドが熟睡していることを確認し、そっと体を寄せる。寒いからではない。ただただ、彼にくっつきたい。アルカルドは、すると、ごく自然な動きで、フィリスを抱き寄せ、長い腕でくるむようにしてくれる。
もちろん彼は眠っている。フィリスが淹れたお茶と、お菓子と、魔法のせいで。
舞踏会が終わったら。
もう、魔法をかけるのはやめよう。アルカルドは予定よりずっと早く完治した。
本当の夫婦になって、彼の子供を生む。その先のことは、希望を捨てなくていいかもしれない。
フィリスは彼を愛しているし、彼の方も、確かな愛情を示してくれている。
そうであるならば、すべてがうまくいくに違いないのだから。
それでも、懸念事項は依然として残っている。なんといっても、ドールーガの欠片をまだ捕まえられていないこと。招待客が滞在するようになったら、探すのがますます困難になるし、万が一にも客の誰かに寄生されてしまうと、厄介だ。
探し回りたいのに、なかなか集中できる時間が取れない。
フィリスは女主人としての作法や、客を迎える準備について、ドルモアから多くを学ばねばならない。一足先に来ているデルフィーヌの存在も気になる。同時に舞踏会で着るドレスの仮縫いや、コルテスとの料理の相談、夜は夜でアルカルドのために軽食を作り、浄化魔法など、やらねばならないことが山積していた。
しかしこの日、ぽっかりと時間が空いた。正午過ぎ、ドルモアと執事のバルロー、それから使用人が総出で、ホールの最終的な清掃と飾り付けを行うことになった。花屋が出入りしたり、シャンデリアが磨かれたりと慌ただしい気配が満ちている。
アルカルドは領地の見回りと会合のために、昼前から出かけている。デルフィーヌは、馬車を出しアルカルドを追いかけていったという。
おそらく、今日が最後の機会だ。
フィリスは自室で午睡を取るということにして、こっそりとまた三階へと上がった。
両腕に、小さな陶器の壺を抱きかかえて。
大勢の来客に備え、三階は、普段と違って明るく、人が行き来している気配があった。すべての厚いカーテンは引かれ、多くの客室は空気を入れ替えて清掃するため、ドアが開け放してある。
フィリスは用心しながら、各部屋を見て回った。寝台の下、バスタブの陰、衣装室の奥までくまなく見たが、やはり、ドールーガの気配はない。
今日中に三階と屋根裏まで見て、いなかった場合は、なんとかもう一度、使用人の居住区も確認したい。
それにしても屋敷は広すぎる。
フィリスは持ってきた壺をいったん床に置くと、蓋をずらし、中を覗いた。
白い蟲が蠢いている。
全部で五匹―――。
「……いい子」
壺の中には、先日クロエと一緒に森に行った際に収穫した、新鮮な桑の葉を入れていた。
森に出かけたのは、桑の葉を手に入れるためでもあった。
フィリスはバランデュールから、この壺を嫁入り道具に忍ばせて持ってきた。
壺の中には、魔法で仮死状態になった特別な蚕たちが眠っている。新鮮な桑の葉を与えると眠りから覚め、フィリスの役に立ってくれる。
彼らは、希少な繭を提供してくれるだけではない。バランデュールの蚕は、使い魔として使役できるのだ。
『ボーラン ボーラン 我が下僕よ……』
壺から取り出し、両手のひらに乗せて呼びかけると、蟲たちは嬉しそうに頭部を揺らす。フィリスは微笑み、指の腹で優しく白い腹を撫でてやる。
そして。
「お行き。屋敷中をくまなく探して、邪悪なものを見つけたら、すぐに報せて」
蟲たちは手のひらで白い蛾に変じる。そして順番にふわりと飛び立ち、しばらく部屋の中をあちらこちらへと飛び回っていたが、一匹ずつ、ゆっくりと廊下に出ていった。
フィリスは引き続き、三階の各部屋を念入りに調べた。
出会ったら、今度こそ必ず浄化してみせる。その時に備えて、栄養を日々蓄えてきたのだ。少し肥ったようで、ドレスの仮縫いの時、仕立て屋が困っていた。申し訳ないが、優先事項というものがある。
部屋を一つひとつ、しらみ潰しに調べてゆき、とうとう、東側の廊下の奥までたどり着いた。一番端の部屋は鍵がかかっている。
実は前にも、この部屋の前までは来ていた。
鍵がかかっていたので、入ることができず、気になっていたのだ。
屋敷中の鍵を管理するドルモアに頼めば、開けてもらえるかもしれない。だが、うまい理由が思いつかない。
どんな鍵でもたちどころに開けられる従姉妹がいた。彼女は鍛冶仕事を専門にしているから、錠前のことは構造から理解しており、そのため魔法も利用できる。しかし、フィリスはその方面に詳しくはない。
それでも駄目元で、今日もドアノブに手をかけてみた。すると予想に反し、ドアはすんなりと内側に開いた。
そこは、明るい光が満ちていた。
てっきり骨董品をしまう物置のような場所かと思ったのに、どうやらここも客室のようだ。大勢の来客に備え、開放し、使えるように準備しているのかもしれない。
それにしても。
「なんて豪華なお部屋……」
フィリスとアルカルドが使っている部屋よりも一回りは大きく、寝台を初めとした家具調度品は、さらに立派なものだ。カーテンや絨毯、壁紙、長椅子に並ぶクッションなどは青と白で色味が揃えられている。
中でも目を引くのが寝台だ。リネン類は純白で統一され、天蓋から吊るされた帳はやはり白の繊細なレース、そこに細かな金色の花が刺繍されている。
フィリスは少しの間ぼうっとして、豪華な部屋を眺めていたが、首を振り、すぐに調査を再開した。他の部屋と同様に、チェストのすべての引き出しや、長椅子の裏まで確認して回る。
そして、巨大な寝台の下を見るために、床に這いつくばっている時である。
「そこで何をなさっているの?」
フィリスは驚き、無様な格好のまま背後を振り向いた。
デルフィーヌだ。
ドアのところに、腕組みをして立っている。
「あの……探しもの、です」
慌てて立ち上がり、小さな声で言うと、デルフィーヌは小首をかしげるようにした。
「何を無くされたの?」
「……大したものではありません」
「大したものではないのに、侯爵夫人ともあろう方が、床に這いつくばっていらしたの?」
「……それは」
別に彼女に丁寧に説明しなければならない理由もない。そのことに気づき、フィリスは平常心を取り戻した。
にっこりと笑う。
「人にはあまり言えないものなのです」
「だから、なんですの、それは」
「どうかお許しください」
微笑んで、しかしきっぱりと首をふると、デルフィーヌは不愉快そうに顔をしかめた。
「アルカルドに言うわ」
仕方がない。
「……どうぞ。ところでデルフィーヌ様は、お出かけになられたのではなかったのですか」
デルフィーヌは唇を歪める。
「それはやめたの」
「どうしてまた?」
純粋に疑問に思った。今までのデルフィーヌだったら、何が何でもアルカルドについていったはずだ。アルカルドが強く断れない状況であることを分かっている。
しばらくの間、お互いに無言のまま相手を見ていた。フィリスはどうやってこの部屋を出ようかそればかりを考えていた。
ドアのところにデルフィーヌが仁王立ちしている。どいてくれなければ、出られない。
時間が惜しい。今日はなんとしても、ドールーガを見つけたい。
「デルフィーヌ様。申し訳ありませんが、そこを……」
「あなた、アルカルド様に呪いをかけたの?」
衝撃的な言葉に、フィリスは息を呑んだ。
「……なんとおっしゃいました?」
「呪いをかけたかと聞いたわ」
「なぜ、そんな」
「メイドたちの噂話を聞いたのよ。あなたは、忌まわしい魔女なんでしょう?」
鼓動が激しくなる。じわりと冷たい汗が吹き出す。フィリスは動揺を見せないよう、黙ったままデルフィーヌを見つめ返す。
「確かに前も聞いたことがあったわ。バランデュールの女たちはみんな魔女だって。そんなの馬鹿馬鹿しいって昔は思っていたけれど、火のないところに煙は立たない」
フィリスは呼吸を整える。静かに息を吸って、吐く。
そして、再びにっこりと笑ってみせる。
「では、今は信じるのですか? わたしが魔女だと?」
デルフィーヌはじろじろとフィリスの全身を眺める。
「どうかしら。魔女って年老いた女か、逆に、もっと妖艶な感じかとも思うし……でも、アルカルド様があなたに優しいのは、魔術か呪いをかけられたせいだとすれば、腑に落ちる気もするの」
「魔法なんかかけられなくたって、アルカルド様は誰に対してもお優しいと思います」
デルフィーヌは瞳を細める。
「それはそうよ。じゃあ、認めるわね? あなたが決して特別ではないと。王命に従って結婚させられたから、表面上は優しくしているだけだって」
「表面だけではありません」
フィリスははっきりと否定した。
「アルカルド様は、真にお優しいのです。わたしを……妻だと認めてくださっています」
デルフィーヌの眦がつり上がった。
「そこを通していただけますか。そろそろ下に戻らなければ」
本当はまだまだ時間を割いて調べる予定だったが、仕方がない。いったん撤退しないと、これ以上デルフィーヌにあれこれ聞かれるのは困る。
デルフィーヌは意外にも、素直に道をあけてくれた。フィリスは廊下に出られたが、
「ねえ、あなた」
すぐに呼び止められた。
「……まだ、なにか?」
「あなた、臭いわよ」
「え?」
毎日入浴しているのに? フィリスは思わず腕を持ち上げて服の匂いを嗅ぐ。デルフィーヌはくすっと笑うと。
「田舎臭いだけじゃないわ。なんというのかしら。罪人と同じ臭いがする」
「罪人……」
「わたくし、一度だけ見たことがあるの。窃盗と殺人を繰り返して、広場で処刑されることになった女を。その者と同じ臭いがする」
さすがになんと答えていいか分からず黙り込む。するとデルフィーヌは、なおも言った。
「じゅうぶんに用心するのね? 人の婚約者を盗んだばかりでなく、もし、本当に、忌まわしい魔術を行う魔女なのだとしたら。わたくし、どんな手段を用いても、あなたに刑を受けてもらいます。それが侯爵家のためであり、国のため……アルカルド様のためでもありますから」
フィリスは頷くことさえできなかった。するとデルフィーヌは勝ち誇った笑みを浮かべ、先に廊下を歩いていく。
「ああ、そうそう。その寝室が誰のものか、ご存知ないようね?」
金色の髪の美女はくるりと振り向き、余裕たっぷりの笑みを浮かべる。
「どなたのです?」
「歴代の侯爵夫妻のお部屋よ。だから、あなたが今寝起きされているお部屋よりうんと広いし、立派でしょう」
フィリスは頷いた。
「確かに、とても広くて素敵です」
「わたくしが嫁いだら、使うはずのお部屋でしたの」
「……そうなのですか?」
「ええ、そうよ。現ロシェル公爵夫妻も、かつて使われていたの。でも、王都へ越されるとき、公爵夫人はわたくしに言ったのよ。ここはデルフィーヌ、あなたが使ってちょうだいねと」
フィリスは胸がぎゅう、と痛くなって黙り込んだ。デルフィーヌはなおも衝撃的な言葉を続けた。
「ですからわたくし、こちらに遊びに来る度に、自分好みに部屋を整えておりましたの。アルカルド様は、ここ数年は、ずっと、戦地にいらして、領地に戻る暇はありませんでした。わたくしは彼の未来の妻ですから、来る日に備えて、ふたりの部屋を準備したのですわ」
デルフィーヌはふと寂しそうな横顔を見せて、ドアを見つめた。
「……予定が変更になって、ここは閉ざされてしまったけれど。でも、片付けられてもいないでしょう? わたくしはそれが、アルカルド様のお考えを示しているのだと信じております」
デルフィーヌが去ったあと、フィリスはもう一度、先程の部屋に戻った。
なるほど、話を聞いたあとに見てみれば、この寝室には彼女の気配があちらこちらに感じられる。猫脚の家具や大きな鏡を載せたチェスト、彼女の瞳と同じ色合いで統一されたカーテンや絨毯。
フィリスが今、アルカルドとともに使っている居室とて、とても贅沢で広いものだ。だから、なんの不満もない。
それなのに、心に穴が空いてしまった気がした。
アルカルドはこの部屋を片付けなかった。
二年後には、また必要になるかもしれないから?
でもフィリスは、その未来を考えたくはない。アルカルドが言った、ふたりの結婚が幸運なものだと思い始めている、というあの言葉に、希望を見出している。
ああ、彼との結婚生活が、永遠に続けばいいのに。
フィリスは廊下に飛び出した。今すぐに、アルカルドに会いたい。会って、この不安を払拭したい。先日、窓辺で彼の膝に乗り、キスをしてもらった、あの時のように、もっと、もっと―――。
フィリスはその時、ぎくりとした。誰かに強く見られている。
横を見る。
鏡だ。
廊下にかけられた、金で縁取られた大きな鏡の中に、フィリスが映っている。
小さな悲鳴が漏れた。
「……わたし?」
そこに映る女の顔は、とてもではないが、自分のものとは思えない。
歪められた貧相な顔。苦悩、怒り、嫉妬、独占欲……あらゆる負の感情が刻まれた顔は、まるで魔物そのものではないか。
フィリスはへなへなとその場に崩れ落ちた。
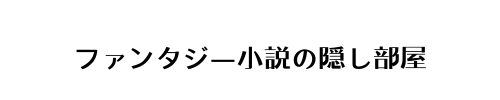


コメント