自信作を投稿し、ドキドキしながら選考結果を待ち、結果落選と知った。かなり落ち込みますよね。まるで自分自身や夢そのものを否定されたように感じるものです。そして心折れ、日常と折り合いをつけるという名目で、小説を書くことを断念する。しかしすっぱり諦めることもできず、時々思い出しては苦しくなる。
朝起きたときに、物語を書くことしか考えられなかったら
映画『天使にラブソングを2』(1993年公開 主演ウーピー・ゴールドバーグ)の中に、印象的なシーンとセリフがあります。
主人公のデロリスはラスベガスのショー・ガール。ひょんなことからシスターに扮し、問題児ばかりの音楽クラスの指導を任される。歌が天才的に上手な少女リタは、複雑な家庭で育ち、母親から歌手になる夢を否定され、「現実を見ろ」と言われ続けていた。それでも音楽への情熱を胸に燻らせ苦しむリタに、デロリスはリルケの『若き詩人からの手紙』を渡す。
「作家を目指していた男が、ある日リルケに手紙を出したの。自分の作品を読んで欲しいって。リルケはこう答えた。『そんなことをわたしに聞くな。もし、朝、目が覚めて、物語を書くことしか考えられないなら、君はすでに作家なのだ』って。あなたにも同じ言葉を贈るわ。朝、目が覚めて、歌うことしか考えられないなら、あなたは歌手になるべきよ」
集英社では昔、ロマン大賞という新人賞がありました。原稿用紙250枚から350枚が応募規定でしたから、長編になります。大賞賞金は100万円で、受賞作は原則文庫化して出版される。
(この賞は2014年に廃止になり、現在のノベル大賞に統合されています)
ある年、わたしは様々な理由から会社を辞め、投稿中心の生活をすることにしました。仕事が忙しすぎて体調を崩しやすく、文章を書く時間がなかなか取れなかったのです。作家になる夢を諦めたくありませんでした。すでに結婚していたのですが、パートナーが理解を示してくれ、背中を押してくれました。
前回書きましたが、初めて書き上げた長編は、ジャンル違いのレーベルに出して落選。その後、自分が読者でもあったコバルトの新人賞への挑戦を決め、腰を据えて長編を書きました。そして送ったのが、このロマン大賞です。
編集部から電話があり、最終選考に残ったことを知らされました。候補者は4人。
電話を切ってから快哉を叫び、パートナーに報告し、「もう受賞したも同然」の気持ちでした。
落選しました。

選評で、厳しくも有り難いお言葉をいただきました。
泣きましたね。ひとりで。
しばらく何も手につかず、ぼんやりと過ごしていました。その頃、近所に新しくカフェがオープンし、スタッフを募集していたので、そこで働くのはどうだろうか、と考えました。才能もないのに無職のままでいるのは、申し訳無いと思ったんです。まだ子供もいませんでしたし。
「履歴書を送って面接の日も決まったよ」
と彼に報告したら、真顔で指摘されました。
「そうなんだ。でも、そこで働くために仕事辞めたんだっけ?」
もう少しがんばるべきではないか、と言うのです。以前から、わたしが書くものを好きだと言ってくれていました。期限を設定するのはいいとしても、今はまだ、もっと書いて、書いて、投稿を続けるべきではないか、と。
それから数日は、まだグダグダしていました。もう書けないし、書きたくもない。わたしが書かなくても、誰も困らない。資格試験と違い、「これだけ勉強したら受かりますよ」とはならない。費やした時間は成果を保証せず、望む扉を見つけることができても、目の前でバタンと閉ざされてしまうことがある。
でもある日、とてもよく晴れた日、窓辺に仰向けに寝っ転がって空を見ていたんですが、急に、物語がうわっと溢れ出てきたんです。
書きたい、と強く思いました。当時使用していたiMacまで駆け寄って、一気に、一日で、だーっと小説を書きました。プロットもなにもありません。原稿用紙で100枚くらい。
それを、当時のノベル大賞(この頃は短編対象)に応募したんです。
再び最終選考に残った連絡を、同じ編集者さんからいただきました。
もう浮かれませんでした。ただただ、「自分らしい小説」を書いたという実感があり、これでダメなら、潔く再就職しようと決めていました。
でもきっと、ダメでもやめなかったと思うんです。再就職はしたかもしれないけれど。
創作欲は生涯つきまとい、決して離れていってくれない病
もうやめよう、諦めよう。小説家を志す人なら、誰しも一度は思うのではないでしょうか。もちろん、初めての小説ですんなりとデビューできる稀有な方もいらっしゃる。でも多くは、容赦のない落選や、第一次選考、二次選考止まりを経験されているのでは。または、一度も書き上げることができず、お蔵入りになっている物語を胸の奥底にしまい込み、生活している。
リルケは「朝目が覚めたときに〜」と言いましたが、わたしはよく、眠りに落ちるときに物語を考えています。朝はご飯なんにしよ、とか、今日ゴミの日だな、とか、猫のトイレシート交換しなくちゃ、とか。ものすごく生活感に溢れている。
妄想世界に身を置いて眠るのが好きなんです。誰にも邪魔されない静寂の時間。幼い頃からそうでした。物語を作るというより、物語世界に入り込む。
小説を「もう書くのはやめよう」と思いながらも、考えてしまうし、ストーリーを組み立ててしまうのではないですか。なんならラストシーンだけでも、思い浮かべることができたりしませんか。
それはもう治りません。
諦められない、じゃなくて、すでに体質的にやめることができない、のです。たとえ、なかなか受賞せず、認められなくても。
そうであるならば、書き続けるしかありません。その欲求は、短期的なものではなく、ずいぶんと昔から身体の内側を侵食し、息をするたびに自然に湧き上がってくるものだから。
かくいうわたしも、本当はこんな偉そうな記事を書ける身分ではないのです。売れてませんし、説得力に欠けると思われる方がいても仕方ありません。ただ細々と、長く継続はできている。それは、やめることができないからです。まだ書きたい世界があり、諦めることができないからです。
時には休み、人の創作物にもたくさん触れる
とはいえ、休みたくなるときもありますね。もう、自分自身にうんざりして、心の中を隅々まで探しても、開けられる引き出しはひとつも残っていないと感じたときなど。
アニメ『魔女の宅急便』でキキは画家のウルスラにスランプについて訊ねます。すると彼女はこう答えます。
「そういう時は、ジタバタするしかないよ。描いて、描いて、描きまくる」
「描くのをやめる。散歩をしたり、景色を見たり、昼寝をしたり、何もしない。そのうちに急に描きたくなるんだよ」
休むのがベストなのですが、人間厄介なもので、そうすると、焦りも生じてしまう。「今、こんなことしていていいのだろうか」「二度と書けないのではないだろうか」「こんなことしているあいだにも、才能豊かな人達がどんどんデビューしてしまうのではないか」
休んで大丈夫です。というより、正確に言えば、完全に休んでいる状態ではありません。前述したように、ふとしたときに物語を作ってしまう病なんですから。
枯渇したと思っても気のせいです。枯渇していません。
休んだとき、わたしなら、以前と同様ぼんやり過ごし惰眠を貪ったり、大掛かりな断捨離をしたり、犬と遠くまで散歩に出かけます。そして、少し余裕が出てきたところで、新しい小説や漫画を読みまくります。
ものすごく面白い作品を読むと、複雑な気持ちにもなりますね。人様の才能に嫉妬もしますし、再び焦りも出てくる。でもそんな醜い感情を吹き飛ばすほどの、「ああなんて面白いんだろう。この話好き!」という高揚感。嬉しくて、楽しくて、人生得した気分になる。そういう人は、どうしたって、物語が好きなんです。
そして、気づけば、ぼんやりと霞がかっていた新しい物語が、空の引き出しにみっちりと育ち、ある日バン! と飛び出してくる。そうじゃなくても、最初の1ページを書き始めるかもしれない。500枚もの長編も、1枚目から。書き出さないと始まらないのです。
以上がわたしが考えるところの継続であり、夢を諦めないということです。
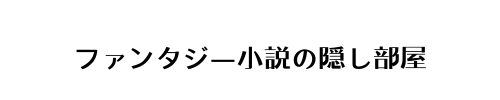


コメント