さよなら、バイバイーーー泣かないでね。ちょっとはいいけど、たくさんは泣かないでね。大丈夫。きっとすぐにまた会えるから。
第四話 小川佳代の事情
朝起きると、しま子の姿は消えていた。
古民家は無駄に部屋数があって、頼子が寝起きしているのは、南側の奥の一番小さな部屋だ。雨戸を開けながら囲炉裏の部屋まで行ってみると、ストーブは消され、毛布もきちんと畳んで置いてあった。
彼らがここにやってくるのは、満月の三日前の夜半。それから三日の間に、もと飼い主の調査をする。当然、清掃のアルバイトがない日に行う必要がある。
毎月、その付近の数日間はアルバイトを入れないようにしている。調査に赴くには、なにかと事前準備が必要である。
頼子は前夜のうちに、食パンに使用したのと同じ酒粕酵母で、あんパンの生地を仕込んでいた。朝見ると、元気に発酵してくれていた。いつものように、朝食を食べる前に生地を分割、ベンチタイム、成形をすませる。二次発酵を待つあいだ、家の空気を入れ替え、風呂場や土間を軽く掃除した。
今日の朝食は、ご飯に豆腐とワカメの味噌汁、自家製塩麹に漬け込んであった鮭、カブときゅうりの浅漬だ。本当は酒粕酵母の食パンに、トマト麹でスープでも作ろうとしていたのだが、パンはしま子がすべて食べてしまった。たまには和朝食も悪くはない。
洋食にしろ、和食にしろ、頼子はできるだけ発酵食品を摂るようにしている。パン作りの基本となる天然酵母以外にも、冷蔵庫には四季折々の発酵食品が詰まっている。
豆乳を発酵させたヨーグルトに、各種野菜の一夜漬け、キャベツのザワークラウト、発酵ジャム、料理の旨味を引き出すたまねぎ酵母。塩らっきょう、自家製糀みそ、梅漬け。大小のビンやタッパーが冷蔵庫に入っていると安心できる。どんなに疲れた日でも、具合が少々悪い日でも、数日買い物に行けない日が続いても、冷蔵庫に発酵食品があればなんとなるのだ。
酵母や菌が生命に多大な影響を及ぼすことを知ってから、頼子は、以前にもまして発酵食品を摂るようになった。
おかげでこの仕事を請け負ってからというもの、身体の調子がすこぶるいい。肌はもちもちとして、髪の艶も増している。
もっとも、それで美人になれるわけではないが。
そんなことをつらつらと考えながら食事を終え、片付けをしていると、メッセージアプリの着信音が続けて鳴った。
時刻は八時二分。相変わらず朝早くから仕事を開始しているらしい。
差出人は佐倉市役所、市民部市民課、猫班の鳴宮律(なるみやりつ)―――たったひとりの仕事仲間である。
彼はたいてい、リアルな猫のスタンプを送ってくる。おはようございます、と。そして続けて、重要な情報を報せてくる。
今回は、小川しま子のもと飼い主、小川佳代の個人情報だった。
住所は、大佐倉。広大な農地が広がるあたりだ。
良かった、と頼子は今回も安心する。過去に一度だけ、飼い主が海外に越してしまい、着替えが成立しなかったことがある。この特殊な生まれ変わり制度には明確なルールがあり、飼い主は佐倉市在住に限られているのだ。それがなぜなのかは知らされていない。もしかしたら、全国には猫班を置く市町村がほかにもあるかもしれない。
焼き上がったあんパンを箱に詰める。いつも通り、さっと身支度をすませ、戸締まりをして外出の準備を終えた。
小川佳代は七十四歳。頼子の祖母が亡くなったのも、その年齢だ。
大佐倉方面へ軽トラックを走らせながら、頼子は祖母のことを考えていた。
再婚した母から頼子を引き取ってくれた祖母は、足が不自由で、すでに年金を受給していた。生活は決して豊かではなかった。頼子は祖母の介護のために、高校を中退した。その後、祖母を看取り、気づけば二十歳になっていた。
祖母と住んでいたのは小さな戸建てだったが、県の住宅支援事業を利用した借家で、祖母の死後は出なければならなかった。もちろん、住居費のほか、生活するためには、働かなければならない。頼子はできるだけ人と話さずにすむ仕事を探した。市民病院の夜間清掃の仕事は、ぴったりだった。
祖母は亡くなる前の一年間は完全に寝たきりの生活だったが、頭は最後までしっかりとしていた。最後まで、頼子のことを案じていた。彼女は何度も謝った。高校を中退させてしまったこと。自分が死ねば迷惑をかけずにすむのにと。それなのに、死ぬ直前にはこう言ったのだ。
「おまえをひとりぼっちにしてしまうね」
祖母が死んだ時。頼子は確かに、ほっとした。これで自由になれると。でも、それ以上に苦しかった。愛する者の死は、想像以上の力で人を打ちのめす。それは決して慣れることのできない痛みだ。
小川佳代は、愛猫の死を、どうとらえているのだろうか。はたして生まれ変わりを望むだろうか。奇しくも祖母と同じ年齢の女性について、頼子はいつも以上にあれこれ考えてしまう。
小川家は、地図アプリに頼らなくてもすぐに分かった。というより、しま子が捨てられたあとしばらく根城にしていたという、壊れたショベルカーが目印になった。彼女は草むら、と言っていたが、そのあたりは広大な田んぼが広がっている。ショベルカーが打ち捨てられている場所だけが、雑草が生い茂っているのだ。錆びた車体にツタが絡まり、屹立している様子は、なんだか世紀末のような物悲しい雰囲気を醸し出している。
市道を挟んで反対側に、大きな家がぽつんと建っていた。市道から左折し、敷地内に躊躇なく軽トラックを乗り入れる。二階建ての家は、築年数がかなりいってそうだ。もしかしたら、市道の向こうの田畑もこの家が所有しているのかもしれない。敷地内には倉庫のような建物も見えたが、錆びたシャッターは下ろされたままだ。
引き戸式の、磨りガラスが入った玄関ドアの横についているインターホンを押す。鳴っている様子はない。さてどうしたものかと考えていると、右手から人が現れた。
「どちらさん?」
ああ、彼女が小川佳代だ。痩せぎすで、紺色の矢絣のモンペに長靴を履いている。両手で抱えた籠には、泥をつけたカブがたくさん入っていた。農作業の途中だったのだろう。髪は白く、日焼けした肌には深い皺が刻まれている。厳しい目をして、頼子を胡散臭そうに見ている。
「権藤頼子と申します。小川佳代さんですね」
「そうだけど。なに、なんかのセールスだったら……」
「小川しま子さんの依頼で、事前調査に参りました」
少しの間。皺に埋もれた目が、大きく見開かれる。
「……え?」
「お時間は取らせません。お話、うかがっていいですか」
佳代に案内されたのは、庭先だった。靴を履いたまま縁側に腰掛けて、手入れされた庭を眺めていると、佳代がお茶を載せた盆を手に戻ってきた。
お茶が置かれたタイミングで、頼子も手土産を渡す。朝焼いたあんぱんだ。中の餡子は前に大量に作って、冷凍保存しておいたものである。よもぎの粉を使った生地は渋みのある緑色で、アクセントに黒ゴマを散らしている。
佳代は無言のまま、隣に腰を下ろすと、あんぱんを食べ始めた。頼子はお茶をいただきながら、庭に目をやる。
ふと、庭木の根本に目が止まった。小さな御影石が置いてあり、菊の花が供えられている。
「しまちゃんは、あそこで眠っているよ」
ぽつりと佳代は言った。それから、しま子について語り始めた。

小川佳代の話―――
もう十五、六年も昔の話だね。秋の終わりで、大きな台風が近づいてきている晩のことだった。その少し前に、上の娘に続いて下の娘も結婚して、嫁いでね。あたしは、独り暮らしだった。
早めに雨戸を全部閉めて、雨戸がない二階の窓には養生テーブを貼って、台風に備えたんだ。夜になって、いよいよ風や雨がひどくなって、こんな日は早く寝ちまおうと思っていた。
その時に、聞こえたんだ。猫の声がね。いや、正直、最初は猫だと分からなかった。人間の赤ん坊みたいに、でっかい声がしてねえ。それで、意を決して、市道の方へ回ってみたんだ。
驚いたね。暗闇の中から、猫が現れた時は。最初は狸かと思ったよ。ずぶ濡れで、お世辞にも可愛らしいとは言えない、鼻ぺちゃの子でさ。足は短いし、目つきは悪いし。何より汚らしいし。正直、迷ったよね。見なかったことにしようかって。
でもあの子は、必死にあたしの脚にまとわりついてさ。狂ったみたいに鳴くんだ。
見捨てないでって、叫んでいるようだった。
その姿が、胸に堪えてねえ。
あんまり健気で、可哀想で。だから、とりあえずこの嵐の夜の間だけでもって思って、連れ帰ったんだ。
タオルで拭いてやって、味噌汁の出汁に使ったあとの煮干しとか、茹でた鶏のササミなんかをやったんだったかね。恐ろしいほどがっついて食べて、そのあとはコテンと眠っちまった。
よく見ると、左脚の付け根のあたりに血がこびりついていてね。歩き方もなんだかおかしいし。だから、次の日に動物病院に連れていったんだ。
股関節を傷めていて、生涯、左脚は引きずるでしょうってさ。
あたしは、猫は嫌いだったんだよ。だからその病院で、里親募集の張り紙をしてくれることになって、まあ飼い主が見つかるまでってことで、しばらく面倒見ることにしたんだ。
なぜ猫が嫌いかっていうと、どうにも薄情な印象があってさ。自分勝手で、犬と違って言うことはきかないし、気まぐれで、物覚えも悪い。
でも、そんなのはぜんぶ間違っていたけどね。
猫ほど、愛情深くて、賢い生き物はいないよね。
それが、しま子を飼うようになって、初めて分かったんだ。
そう、飼うことになっちまったんだよ、結局。病院の方でも、貰い手は見つからなかったし、なにより情が移っちまって。
しま子は、たしかに一見ブサイクなんだけど、見慣れると味わいがあるっていうか、逆に愛嬌があって可愛いというか……ほら、人間の女でもいるだろ、美人じゃないのに妙にモテる女が。
とにかく、一緒にいるようになって、一ヶ月後には、あたしはあの子を溺愛するようになっていたんだ。
だって可愛いんだよ。しま子は、どんな時も、あたしの視界に入る場所にいるんだ。庭仕事をしている時は木陰で昼寝したり、虫をつかまえて遊んだりさ。家に入ればついてきて、甘えたい時は膝に乗ってくる。風呂に入れば風呂の蓋の上に寝そべって、じっとしている。夜は一緒に眠ったね。あたしの右側の腹のあたりが、あの子の定位置だった。あったかくてねえ。鼻が潰れているもんだから、寝息もうるさいんだ。でもその寝息が、不思議と心地よい音でねえ。
あたしは、しま子に言ったんだ。おまえはあたしの三番目の娘だよ。おまえはあたしに恩返しをしなくちゃなんない。それは、ずっと一緒にいることだよ。人間の娘たちは、ふたりともあたしを置いて出ていった。それはそれで幸せなことだけど、三番目の娘は、ずっと一緒にいてもらいたいってね。
佳代は話を切り、また黙り込んだ。皺に埋もれた目は、じっと、庭先に注がれている。
「あんぱん、もうひとついかがです」
「……そうだね。いただこうか。不思議だねえ。これを食べたら、しま子のことをまざまざと思い出したよ。あの子の手触りとか、匂いとか」
「そうですか」
「死んで、もう一年以上経つのにね。ここに来たのが推定で二歳くらいだったから、十八歳くらいで死んじまってねえ。恩返しをするって約束したのに、まったく」
頼子は自分もあんぱんをひとつ手に取り、一口齧る。酒粕酵母の風味とよもぎの香りがマッチして、もっちりとした食感だ。あんこの甘さもちょうどいい。
「戻ってきてほしいですか?」
大事な質問を、さらりとした。
「ええ? しま子のことかい?」
「はい。小川のしま子さんに、戻ってきてほしいですか?」
「そりゃ……」
佳代はそこで、言葉を飲んだ様子を見せた。うつむき、皺だらけの手を膝の上でぎゅっと握る。
それから、つぶやくように答えた。
「―――いいや」
いろんな飼い主がいる。心の底から、飼い猫に戻ってきてほしいと願う人。
戻ってこなくてもいい、という人。
家や経済状況の変化で猫が飼えなくなってしまった人もいる。
自分自身が老いて、今からだともう新たに飼えないという人も。
「都内の、長女のところに行くことになったんだ」
佳代は言った。
「旦那が死んだ時から市道向こうの田んぼは人に貸してたんだけど、そっちも綺麗さっぱり売ってね。あたしはもう七十四だ。しま子が戻ってきてくれても、最後まで飼ってやることはできないだろう。娘家族も狭いマンション暮らしだし。今度は、あたしの方が、しま子を残して逝くことになっちまう」
「しま子さんは、それでもいいって言っていましたよ」
「ええ?」
「恩返しの約束を守れず、あなたより先に死んでしまったことを、ずいぶんと気に病んでいます。子供が親より先に死ぬのは逆縁だって。だから、今度こそは、最後まであなたと一緒にいたいと」
ははっ、と、佳代は笑ったようだった。しかし、その顔がみるみる崩れる。涙が溢れ、音を立てて、手の甲に落ちた。
「馬鹿だねえ。馬鹿みたいに律儀な子だねえ。そんな、猫が本当の人間の娘のように、長生きできるはずがない」
「でもしま子さんは、本気であなたの三女である自覚があるようでした」
だから彼女は、人間で言えば老婆の年齢で死んだのに、幼い女の子の姿で現れた。自由奔放にふるまいながら、やけにきちんとした佇まいで、義理堅いことを言った。
恩は返さねばならないと。
「今度こそあなたを看取って、またひとりぼっちになったとしても、構わないと言っていました」
「それは駄目だ」
佳代は強く首をふる。
「あたしが死んで、ひとりになったら、あの子はまた、賢明に鳴くだろう。あの嵐の夜みたいに。だけど今度は、あの子を拾い、濡れた体を拭いて、抱っこして、食べ物をあげる人間はいない。今度こそひとりぼっちだ。あの子があたしを母親だと思うなら、余計にわかってもらいたい。母親ってのはね。我が子が寒い思いをしていたり、お腹を空かせた状態でいるのが、耐えられないんだ。ましてや、ひとりで、寂しがっているなんて、なおさら駄目だ」
佳代はそう言って、顔を覆って泣いた。嗚咽が指の間から漏れ、涙が伝い落ちる。
頼子は瞠目する。
『おまえをひとりぼっちにさせてしまうね』
再び、病床の祖母の顔を思い出した。
心配そうだった。
申し訳無さそうだった。
それから―――愛おしそうだった。
頼子の時間を奪った祖母は、頼子にそれ以上に大切なものを与えてくれた。
実の母親がとうとうくれなかったものを。
頼子は佳代の嗚咽を聞きながら、黙って自分のあんぱんを食べ、お茶を飲み干し、立った。
「わかりました。では、そのように伝えます」
「ま、待って」
縁側から離れようとした頼子を、佳代が呼び止めた。
「あの子は、今、ひとりぼっちなの?」
頼子は答えを迷った。
ひとりぼっち? それは、亡くなってしまったのだから、そうなのだろう。でも……。
「毛皮を着替えない猫は、生前と同じ姿で、虹の橋のたもとで待つと言われています。飼い主さんがやってくるのを」
「虹の橋……」
虹の橋の話は、ペットロスに苦しむ人に向けた詩がもとになっていると言われている。原作者はイギリス人の女性で、自身が飼っていた愛犬の死をきっかけに創作したものだとも。死んだ犬や猫たちは、そこで、仲間たちと遊びながら、飼い主が来るのを待つという。
「とても綺麗で、楽しい場所だとか。まあ、わたしも実際に見たことはないですけど。そこでの時間の流れは、現世とは違うといいますね。小川佳代さんが天寿をまっとうされた暁には、きっと、再会できるはず」
これを聞いて、佳代はようやく泣き止んだ。うっすらと、穏やかな微笑を浮かべる。綺麗で、少し寂しそうな微笑を最後に見て、頼子は小川家を後にした。
佳代はすぐに、今のやり取りを忘れるはずだ。残ったあんぱんを見ても、何も思い出さない。
彼女は頼子の訪問を忘れ、また日常を送る。
でも彼女が、可愛い三女のことを忘れることはない。
満月が空に輝いている。
夜半。しま子は再び裏庭からやって来た。土間の椅子に飛び乗り、テーブルに身を乗り出すと、期待に満ちた目で頼子を見た。
胸が痛かったが、結果は結果だ。
頼子はあえて事務的に、小川佳代の考えを告げた。
「そうなんだ。ご恩返しが、したかったのにな」
予想に反し、しま子は落ち込んだ様子は見せなかった。ただ、つまらなさそうに唇を尖らせる。
「まあ仕方ないか。おかーさん、あたしがひとりぼっちになるのが、嫌なんだね」
「そうですね」
「分かった。あーあ。カタログがないっていうから、今度はどんな毛皮にしようか、一生懸命考えてたのになあ」
「毛皮の模様は自分では選べませんよ。でも、どんな毛皮が良かったんですか」
「うーん。あたし、しま子って名前、気に入ってたのね? だから今度もしましま模様がいいかなって。茶トラとか、サバトラとかね」
「同じ名前はつけなかったと思います」
なにしろ飼い主は、同じ猫が毛皮を着替えてやってきたとは思わない。頼子とのやり取りが記憶に残っていないので、なおさらだ。その仕草や気配で、「生まれ変わりなのかも?」と思うことはあっても、確信は持てない。
「まあそっか。じゃあやっぱり、着替えなくてよかったのかな」
しま子はそう言って、むしゃむしゃとパンを食べた。新しく焼いたあんぱんである。それを先日の食パンと同じように、
「うまうま、あーおいしい、うまうま」
と呟きながら、あっという間に食べ終えると。
「それじゃあたし、もう行くね」
さっぱりとした口調で言い、ぴょん、と椅子から飛び降りて、裏口に向かった。
左脚を少し引きずりながら。
着替えをしない猫は、東の戸から出ることはできない。来た時と同じ、西の戸から、帰ってゆくのだ。
彼女は生まれ変わらない。毛皮は着替えない。
「あのさ」
戸に手をかけた状態で、こちらに背を向けたまま、しま子が言った。
「あたし、おかーさんが好きだったの。本当の本当に、大好きだったの。いつの日かひとりになったとしても、また会いたかった。あと一回でいいから、おかーさんの布団で一緒に眠りたかったんだ」
「はい」
頼子は小さな背中に、そっと言った。
「佳代さんも、そうだと思います。あのですね、あなたの手触りとか、匂いが恋しいって、そう言ってました」
「そっかあ」
しま子は振り向いた。鼻ぺちゃで、大きな目。その目から、とても綺麗で透明な涙がこぼれている。
「憶えていてくれるなら、それでいいや」
それから笑って、手をひらひらとふると、戸を開き、その向こうに消えた。
虹の橋が本当にあるのかはわからない。ただ、あったらいいと強く思う。互いに想い合っているふたりが、また必ず会えますように。
頼子は閉ざされたドアを見つめ、そう願った。
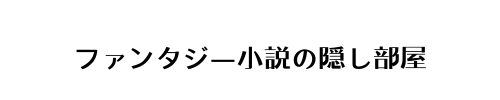


コメント