フィリスの失態
アルカルドは、身体が軽くなっているのを実感していた。
朝、目が覚めた時、頭がすっきりとして、深く眠れたことが分かった。起き上がると、例の忌々しい腕の痛みは、だいぶ良くなっている。驚いて痣を確認すると、薄くなったように見えた。気のせいではない。あの醜い牙の穴にもかさぶたが生じ、閉じられたようだ。
フィリスは相変わらず寝相が悪いのか、アルカルドの方へ転がってきていた。またしても赤子のように身体を丸めて眠っていた。アルカルドは彼女を起こさないよう、掛布を優しくかけて、部屋を出た。
これほど身体が自由に感じるのは、久しぶりだ。彼女の淹れてくれた茶のせいだろうか。スフレも上等な味わいで、胃腸の負担にならず、仕事に集中もできた。
久々の感覚が有り難く、アルカルドはその朝、庭で剣の鍛錬をした。前回の出兵前まで当たり前に習慣だったことだ。帰還後は、身体が重く、気分が晴れず、剣を持つことはなかった。
久しぶりに剣を握ってみれば、ずっしりとした懐かしい重さに身体が疼いた。アルカルドは従者たちを相手に、小一時間ほど剣の鍛錬をし、汗をかいた。
その後、着替えてから朝食室へ行くと、今日はフィリスが先に来ていた。
「アルカルド様。おはようございます」
朝の光の中で微笑む彼女を見た時。アルカルドの胸に、なんともいえない温かな気持ちが広がった。彼女の微笑みは、不思議なことに、アルカルドの気持ちを和らげるばかりではなく、より強い感情を抱かせる。
「ああ。おはよう……」
声が掠れて、アルカルドはそんな自分に驚いた。今朝もフィリスは顔色が悪い。医者を呼んで一度診てもらった方がいいのではないか。彼女は笑って大丈夫だと言うだろう。しかし、アルカルドは考える。
彼女はひょっとして、あらゆることに関し、我慢する癖があるのではないか?
自分のことは後回しにする癖がついているような。もしもそうならば、ここではそんな必要はないのだと、分かってもらいたかった。
「足はどんな様子だ?」
「もうすっかり治りました。大丈夫です」
想像した通りの答えが帰ってくる。体調は? と聞きたかったが、やめておいた。まるで自分が心配性の父親のような感じがしたからだ。
「……ではフィリス。今日もダンスのお相手を努めよう」
代わりにそう言うと、フィリスは花のような微笑を浮かべたのだった。

フィリスが侯爵家に嫁いできてから、半月が経過した。風変わりな侯爵夫人に屋敷の人びとは次第に慣れたのか、廊下で会っても、笑われることが減ったようだ。アニカいわく、特に厨房ではフィリスの評判はとても良いのだという。
「奥様がお作りになる焼き菓子がたいそう評判で、皆楽しみにしているようです」
フィリスはアルカルドのために、日々、簡単な焼き菓子やスープを作っているが、多めに用意して使用人たちにも振る舞っていた。
「それは良かった」
服装もだいぶ違っている。侯爵家お抱えの仕立て屋は、驚き呆れるほどの新しい服を持ってきた。日中の普段用のモスリンのドレス、晩餐用のタフタのドレス、乗馬服、夜着の類から、ガウンや新しい靴、スリッパまで種類も用途もさまざまなものを。
髪は毎日、クロエによって手入れされ艶を増し、軽く化粧もするようになった。
またアルカルドはフィリスに宝飾品も贈ってくれた。希少な真珠の耳飾りと揃いの首飾り、色とりどりの石をはめ込んだ髪飾り、腕輪やブローチ。立ち居振る舞いの細かな所作は、ドルモア夫人の指導を受け、話し方や、困ったときの交わし方なども学んだ。おかげでフィリスは、一見、それなりに落ち着いた教養のある娘に見えるようになり、それに伴って陰口も減っていったらしい。
侯爵夫人としての勉強の合間に、アルカルドと乗馬を楽しむこともあった。
ダンスの練習も付き合ってくれているし、夜半、眠る前にお茶を淹れた時は、会話を交わすこともある。
またフィリスは彼の許可を得て、彼が仕事をしている間、書斎の片隅で図書室の本を読むこともあった。もちろんアルカルドより先に寝室に行き、眠ったふりをしながら魔法の準備をすることだけは怠らずに。
アルカルドはフィリスの毎晩淹れる茶と軽食、就寝後の浄化魔法のおかげで、確実に回復している。同時に始めた剣の鍛錬も思い通りにいくらしく、朝食時にはさっぱりとした表情をしていた。自信が回復し、表情や言葉に力強さを感じる。フィリスはそんなアルカルドを見て、とても安心していた。
一方で、浄化魔法の連続の使用は、フィリスの肉体を確実に蝕んだ。朝食に栄養を摂ったくらいでは相殺できないほどに。それでも化粧を覚えたことで、顔色の悪さは隠せていると思う。なにより元気になったアルカルドと過ごす時間が日に日に増えて、フィリスはとても幸せだった。
そんなある夜、フィリスはいつも通りに茶と、厨房で焼いたばかりの胡椒を効かせた小さなキッシュを書斎に持っていった。
アルカルドは領地の書類仕事のほか、王都からも軍の編成のための事務仕事を頼まれているらしく、この日も書斎机で仕事をしていた。フィリスは彼と目があった時、無言のまま、ただにっこりと会釈し、自分は暖炉の側の椅子まで行って読みかけの本を開いた。
書斎は静かで、アルカルドがペンを走らせる音と、フィリスが本のページをめくる音、そして時々、薪が爆ぜる音しかしなかった。
ふと首の後ろに視線を感じ、振り向くと、アルカルドが手を休め、こちらを見ている。
「君はここで不自由なく暮らせているか?」
フィリスはにっこりと笑う。
「はい。旦那様もお優しいですし、ドルモア夫人をはじめお屋敷の方々もみな親切です」
アルカルドは苦笑を浮かべる。
「名前で呼ぶのは難しいらしい」
「あ。すみません。アルカルド様」
「様はいらない」
フィリスは困惑する。彼を呼び捨てにするなんて、抵抗があった。初めて出会った幼い頃ならいざ知らず……。
「まあゆっくりとでもいい。君が健やかに過ごせているのなら安心だ」
「は、はい。それはもう」
「だが、時々無理をしているのではないか? 特に朝、顔色が悪いことがあるようで、心配している」
ばれてしまっていたのか。明日から化粧をもう少し濃くしなければ。フィリスは内心でそう決めたが、とぼけた表情を浮かべた。
「そうですか? でも、わたしは元気です。実は生家にいたときの倍くらいは食べていますし、眠ってもいます」
「それならいいが。君は、辛いことがあっても笑っていそうでそれが心配だな」
フィリスは目を見張った。アルカルドがそこまでフィリスのことを考えてくれているとは。
「そ、そう思われますか」
「君が泣いたり、喚いたりしているところは正直想像できない」
「……確かにわたし、泣きません」
「我慢すると?」
「いえ……泣くほど辛い目にあまりあっていないせいかもしれません」
最後に泣いたのはいつだったか。そうだ。母が出ていったあの日だ。
「君はつくづく、わたしが知るご令嬢とは違うようだ」
フィリスは内心で慌てる。どうしよう。可愛げがないと思われたのかしら?
「だが人間、時には泣いたり怒ったりするものだ。俺の妻になったからには、そういった感情も我慢させたくはない」
ああ。アルカルドは本当に優しいのだ。フィリスは胸の奥がじんと熱くなった。
「アルカルド様。わたしが負の感情を出すことはないと思います」
はっきりと言うと、アルカルドは驚いた顔をする。
「そうなのか。なぜ?」
なぜなら……バランデュールの女に、負の感情は禁忌だからだ。負の感情は、フィリスのような娘の手に負えず暴走し、周囲を大きく巻き込むことになる……と、祖母や伯母たちから、口を酸っぱくして言われていた。
『いいかい、フィリス。もしも自分を制御できないほどの感情に支配されそうになったら。どんな状況でも、どんな場所にいようとも、必ずここに帰ってくるのだ。それがおまえのためであり、おまえが愛した男のためでもあるのだからね』
ええ、お祖母様、伯母様。わたしは約束を守る。
「……なぜなら、わたしは、ここに来ることができてとても幸せだからです。負の感情など抱くはずもありません」
それもまた真実だった。アルカルドはまだ腑に落ちない顔をしていたが、それきり何もたずねず、フィリスが淹れた茶を口にふくんだ。
その後の、深夜を過ぎた時刻。フィリスはいつも通り、アルカルドが寝室にやってくるのを待った。夜半過ぎ、彼がドアを開けて入ってきたので、眠ったふりをする。いつもなら、アルカルドは寝台にあがって、すぐに寝息を立てて眠りに落ちる。それから浄化魔法をかけるのだ。しかし、この日は違った。
「……フィリス」
名前を呼ばれ、間近に気配を感じた。目を開くと、アルカルドがすぐそこにいて、じっとフィリスを見下ろしていた。
「アルカルド様」
「……起こしたか?」
「いいえ、いえ、はい」
驚きのあまり、変な返事をしてしまう。アルカルドは手を伸ばし、フィリスの髪に触れた。心臓がうるさいほど音を立てる。
「あの……」
何か言おうとした時、顔が近づいてきて、口づけされた。
フィリスは戦慄した。自分に何が起きたのか、いや、これから起ころうとしているのか。頭では理解し嫁いできたが、初夜どころかそれ以降も、夫婦の契りは皆無だったため、心の準備が遅れてしまった。
固まったフィリスに気づいたアルカルドが身を起こす。彼は両手をフィリスの顔の左右につき、彼女を見つめた。
青い瞳は細められ、顔にはやや不安そうな表情が浮かんでいる。
「嫌か?」
そう聞いてくれるのが彼の優しさだ。フィリスが嫌だと言えば、これ以上は何もされないだろう。
しかし、フィリスは、「嫌」ではなかった。
だからしっかりと首を振り、「いいえ」と答える。
再び唇を寄せられた。フィリスは、咄嗟にアルカルドの胸に両手をつき、彼との距離を保った。アルカルドが再び顔をあげ、問うようにフィリスを見る。
「旦那様。いえ、アルカルド様。あの、わたし、アルカルド様にお伝えしておきたいことがあるのです」
アルカルドはこれを聞き、いったん離れた。すぐ側に横たわり、肘をついて、フィリスを見る。
フィリスは起き上がり、寝台の上に正座をすると、真剣な面持ちで言った。
「これが実質の初夜にあたるわけですから。前もって言っておかなければなりません」
鬼気迫るフィリスの様子に感じるものがあったのか、アルカルドも真剣な顔をしている。
「何を聞いたとしても受け止めよう。この婚姻は君にとっても急な取り決めだっただろうから」
フィリスはじっとアルカルドを見つめ、
「大好きです」
と言った。アルカルドは拍子抜けしたような顔になる。
「え?」
「わたし、アルカルド様をお慕いしています。とても、とても大好きです。旦那様」
奇妙な沈黙が天蓋の内側に満ちる。燭台の明かりはまだついている。薄闇の中でも、フィリスの顔が真っ赤であることは分かってしまうだろう。
「……それが伝えたいことなのか?」
「はい。そうです。これは、旦那様にとっては国王陛下からの命令による結婚で、旦那様、いえ、アルカルド様はわたしのことは好きではないと思います。でも、わたしはあなたが好きです。なので、とても幸せです」
「……そのことを、今言おうと思ったわけは?」
「初夜だからです。なんというか、本当の夫婦になる前に、気持ちを伝えておくべきかと思いまして……実は、初日から、言おう言おうと、ひそかに狙い済ませていたのです」
「虎視眈々と?」
「ええ。虎視眈々と」
アルカルドは、ははっと笑った。とても愉快そうに。
「アルカルド様?」
「真剣な顔で、何を言い出すかと思えば……」
「あの。お言葉ですが、わたしは真剣です」
「ああ、すまない。ただ、俺は……てっきり、他に好きな男がいたことでも打ち明けられるのかと」
「他に好きな男?」
フィリスは思考をめぐらせる。そんなことはあり得ないが、どうしてそう思われたのだろう……と、考えて、はっとした。ああそうか。閨でこれから事に及ぼうとしているときに、フィリスが遮り、真剣な顔で話があると切り出したため、そういった可能性も考えたのかもしれない。
「あの……アルカルド様。とても申し上げにくいのですが、わたしは、そうしたことを、いたしたことはございません」
「それは、なんとなく分かってはいた」
「ではなぜお疑いを」
「君が申し訳無さそうに切り出すから」
アルカルドはそんなことを言う。
「俺に負い目を感じてほしくはなかったのだ。あらゆる可能性があってしかるべきだろう。俺たちの結婚は、互いに唐突なものだった」
「はい……それは、そうです」
「なのであえて聞いておこう。君はなぜ、俺にそれほど好意と信頼を寄せてくれているのか」
「それは……幼い頃、アルカルド様をお見かけしたことがあって」
「前にも言っていたな」
もちろん見ただけではない。アルカルドは、母を追いかけて溺れそうになった幼いフィリスを助けようと自らあの川に飛び込んでくれたのだ。あの日、フィリスは彼と二昼夜を森で過ごした。
しかし、彼は憶えていない。
「あの。つまり、一目惚れです」
フィリスは生真面目な声で、きっぱりと言った。これは嘘ではない。ただ前後の詳細を省いただけだ。
これを聞き、アルカルドは一瞬目を見開いたものの、じっとフィリスを見つめた。
「……アルカルド様?」
なにか間違ってしまったのだろうか。どうにもフィリスは、アルカルドのことになると、自信が持てなかった。
彼にふさわしい妻になりたいのに、侯爵夫人として、どういったふるまいが正解なのかまだ分からない。
アルカルドは嘆息し、言った。
「君の気持ちは分かった。俺は……どうやら初めから間違えたらしい」
「旦那様」
「もう寝よう」
アルカルドは先に横になる。フィリスはどうしたらいいのか分からず、ただ小さく頷き、アルカルドから離れた場所に身を横たえた。
今日はまだ浄化魔法をしていない。それにもかかわらず、唇が細かく震える。自分の中に何か大きな、説明のつかない感情のうねりが生じたような気がした。
不安なのか、失望なのか……苦しくて、でも、深く深呼吸することすら憚られる。すると、
「寒いのか?」
アルカルドがこちらを向いて聞いた。フィリスが黙っていると、
「おいで」
自分からフィリスを抱き寄せた。
「確かに夜は冷える。ああ、君は毎晩寒いのだな」
「……毎晩、とは?」
「朝……俺にくっついてきている……」
それは、浄化魔法のせいです……とは、当然言えるはずもなく。フィリスはアルカルドの腕にすっぽりくるまれた。やがてようやくお茶が効いたのか、アルカルドが規則的な寝息を立て始める。
彼の鼓動の音、彼の胸の温かさ、香り。ずっとこのままでいたかった。
でもそれでは駄目なのだ。フィリスは心を鬼にして起き上がると、暗闇の中でしばらくの間、彼の寝顔を見つめた。
『サンザシの枝を打ち鳴らせ……』
いつものように、祈りと浄化の子守唄を口にする。しかし心が乱れていたせいか、いつも以上に苦しい。彼の腕の痣から流れ込んでくるこの悪意。真っ黒な蛇が不吉に輝きながら、フィリスの全身を締め上げる。
「だ……め」
フィリスは頭を振った。長い黒髪の毛束が踊り、鞭のようにしなって、身体に巻き付いた蛇を打ち据える。
すると蛇はあっけなく離れてくれた。
とたんに呼吸が楽になったが、フィリスははっと息を飲んだ。
わたしは今どうしたの?
もちろん、あの魔物を我が身から離してはいけなかった。あれは蛇であり、呪いであり、穢れなのだ。アルカルドの身からフィリスの肉体に移したもの。今まではどんなに苦しくてもその苦痛に耐えながら時が経つのを待ち、体内で確実に浄化した。
しかしフィリスは今、あまりの苦しさに耐えきれず、蛇を放ってしまった。
アルカルドは静かに眠っている。彼に戻ったわけではない。部屋の中に目を走らせる。どこにもいない。
そしてフィリスは気づいた。部屋の、大きなマホガニーのドアが、ほんの少し開いていることに。
慌てて寝台を飛び降り、裸足のまま廊下に出てみる。そうして途方に暮れてしまった。広い廊下は当然のことながら暗闇に包まれ、その闇は、どこまでも深淵のように広がるばかりだ。
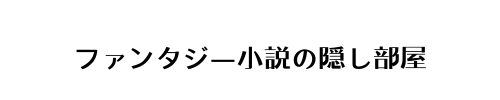


コメント