触れられないもの
川を越えて吹き付けてきた風が顔にあたる。草原を駆け抜ける二頭の馬の足取りはどちらも力強い。
フィリスは手綱を自在に操りながら草原を駆けた。アルカルドを乗せた黒馬も並走している。時々、目が合う度にフィリスはにこりと笑いかけた。アルカルドは何か言いたそうな顔をしたが、無言のまま、しばらく草原を疾走した。
色鮮やかなサルビアやフウロソウが咲き誇る花畑を見た。陽光を存分に受けて輝く花や草木、どこまでも開けた視界は、生まれ育った森とはまったく違う。故郷の森は、日中でも暗く、真夏でもひんやりとした空気が満ちていた。
フィリスは、深い森の木漏れ日や、外界から隔絶された静寂、森の息吹と香り、静寂を破る野鳥や鹿の声を愛していた。それでも乗馬に関して言えば、エントワーズの開放感は素晴らしいと思わずにはいられない。自然に笑みになって、思い切り駆けた。
やがて草原が切れ、馬車の轍が残る道に入った。アルカルドと馬首を並べて、今度はゆっくりと進む。左右には立派な糸杉が等間隔に植えられている。その高さに感心して見上げていると。
「いい手綱さばきだな」
アルカルドが褒めてくれた。フィリスは嬉しくて声を弾ませる。
「馬が素晴らしいのだと思います」
「気に入ったか」
「はい。生家で可愛がっていた子に似ています。マーラと言って、この子と同じ栗毛の馬です」
「馬が好きなのだな」
「ええ。でも、マーラは中でも特別です。わたしが初めて取り上げた子ですから」
アルカルドは目を見張った。
「君が取り上げた? 馬の出産に立ち会ったのか?」
「馬だけではありません。生家では他に牛と、山羊も飼っておりまして、出産の時は必ず立会います。中には難産で命を落とす場合もありますから」
家畜の出産が近づくと、注意深く様子を見て、場合によっては小屋に泊まり込む。特に馬や牛は沢沿いの畑を効率よく耕すのに重要な働き手なのだ。何しろ城には女ばかりなのだから。

「……ドルモアが驚いたと言っていた。君は自分で馬車を走らせ、嫁いできたと」
「はい。ものすごく驚いていました」
つい二日前のことだ。フィリスは小舟でマルレ川を渡り、貴重な銅貨三枚で農家の馬車を借り受けた。御者を頼む余裕はなかったから自分で御者台に座った。屋敷に着いた時は、フィリスが本当にバランデュール伯爵令嬢だと分かってもらうために、出生証明書まで見せなければならなかった。あの時点でドルモアは卒倒しそうな顔をしていたものだ。
「家族は誰も付き添いを申し出なかったのか? 父君は亡くなっていると聞いていたが」
「はい。わたしが生まれる前に。母は弟と王都にいるらしいのですが、かれこれ十一年ほど会っておりません」
フィリスは正直に言った。
「曾祖母と祖母、伯母が三人と、従姉妹が七人いますが、皆、外側……いえ、森から出ることを嫌がります。なので、ひとりでこちらに参りました」
アルカルドはこれを聞き、なるほど、と頷いた。
「滅多に領地から出ない一族とは聞いていた。だが、見知らぬ土地にひとりで来るのはさぞかし心細かっただろう」
「家族と別れるのは寂しかったですけれど、心細くはありませんでした」
「そうなのか?」
不思議そうにフィリスを見る青い瞳を、フィリスはじっと見つめ返す。
「はい。わたし、旦那様にお会いしたかったのです。あの……ずっと昔、まだ子供の頃に、旦那様と会ったことがあって」
アルカルドは驚いた顔をした。
「俺と面識が?」
やはり、まったく憶えていらっしゃらない……。
当たり前よ、フィリス。お祖母様がおっしゃっていたじゃないの。
『メライアは忘却の川。許可なくこちら側に入り、運良くあちら側に戻れた男はみな、一族の女を忘れてしまう』
「もうずいぶん昔の話です。わたしが一方的に……お見かけしただけですので」
「しかし、バランデュールの者は領地からほぼ出ないと」
「旦那様。わたし、昔からお転婆だったのです。言いつけなんて守りません」
アルカルドは目を見張り、それから、声を立てて笑った。
「どうやらそのようだな」
ああ、とフィリスはうっとりとする。彼の笑い声。笑うと目尻に薄く皺が寄って、表情が柔らかくなる。フィリスもそれが嬉しくてにこにこと笑う。ふたりはほんの束の間、笑みを浮かべたまま、互いを見つめ合った。
「君はお転婆なだけでなく、とても変わっている」
アルカルドはなぜか少し体裁が悪そうだ。
「はい。どうやらそのようです。侯爵家の皆さんには、申し訳ない気持ちになります」
「いや……慣れるには時間がかかるだろう。ゆっくりで構わないし、譲れないことは譲らなくてもいい」
「本当ですか。旦那様は、ご不快じゃないですか」
「そうだな……」
アルカルドは、少し考える様子をみせ、それから言った。
「強いて言うならひとつだけ」
「なんでも仰ってください。わたし、変わり者かもしれませんが、変化には柔軟に対応したいと思っております」
決意も新たにそう言うと、アルカルドはまたほんの少し笑った。
「では、アルカルドと」
「え?」
「君は俺の使用人ではなく、妻なのだから。名前で呼んでくれ」
「……アルカルド」
その名を口にすると、フィリスは胸がじんと熱くなった。嬉しくて、頬を染め、更にもう一度。
「アルカルド」
アルカルドは、青い瞳を細めた。少し嗄れた声で、ああ、とつぶやくと、馬の腹を蹴る。
「……この先に農村や果樹園がある。今日は村人たちに軽く挨拶だけしよう」
「はい」
鼓動が早く、頬が熱い。アルカルドが、自分を憶えていなくたって、ちっとも構わない。
わたしが憶えている。
フィリスは初恋の人と結婚し、こうして一緒に馬を駆り、名前を呼ぶことも許された。
この人の役に立ちたいと強く思う。自分以外の誰かを幸せにしたいと、生まれて始めてそう思うのだ。
夢見心地のまま、農村に到着した。漆喰の壁に焦げ茶色の屋根で統一された家々が立ち並ぶ集落だ。その向こう側には広大な田園風景が広がっている。
領主の到着に気づいた幾人かが、帽子を取って挨拶をした。
先に馬から下りたアルカルドが、フィリスに両腕を伸ばし、補助してくれようとした。いつもなら難なく自分で馬に乗り降りするフィリスだが、有り難く彼の両肩に手を置き、腰を支えてもらった。
身体がふわりと宙に浮き、そのまま着地しようとした時。
アルカルドが、ほんの少し、顔をしかめた。フィリスははっとして、彼の右腕のあたりを見た。
「……お怪我をなさっているのですか?」
アルカルドの青い瞳が凍る。ぞっとするほど冷たい瞳で自身の右腕を見て、それから、静かに彼女から離れた。
「アルカルド」
「……大事ない。さあ、行こう」
向けられた背中は、フィリスを拒絶している。呼ぶことを許されたばかりの名は、虚しく響いただけだ。
フィリスは先に歩いてゆく夫の大きな背中を、しばらくの間、呆然と見つめるばかりだった。
その後、アルカルドは村人たちにフィリスを紹介し、簡単なあいさつ回りを終えて屋敷に戻った。
行きと違い、他人行儀な空気がふたりの間に漂っていた。アルカルドは終始礼儀正しかったが、行きに見せたような心からの笑顔は見られず、温かな言葉を聞くこともできなかった。
帰宅後も状況はそのままだ。彼は執務室に入ったきり出てこなかったし、フィリスはひとりで食事をした。晩餐も素晴らしい料理が出てきたが、それらを完食しつつも、朝のように楽しくはなかった。
そして、ドルモアに侯爵夫人としての心得を教わりながら、屋敷内を案内されている時のことだ。
家宝の絵や置物が展示されているロングギャラリーに入ろうとした時、数人のメイドたちが話している声が聞こえてきた。
「……川向うの住人だっていうから。もっとこう、妖艶な方かと思っていたわ」
「男を惑わす魔女って噂だったわよね。確かにあたしも期待しちゃった」
「普通に地味な方よね。パッとしないどころか、かなり見劣りするんじゃない。旦那様の横に立つと特に、ねえ?」
「あれで伯爵令嬢なんて信じられない。身なりもみすぼらしいし、なんなら侍女の方がいいドレスを着ているもの」
「お可哀想ねえ、旦那様。お怪我さえなさらなければ、今だって銀狼の騎士としてご活躍され、デルフィーヌ様とご結婚されていたでしょうに」
フィリスはその場に立ち尽くした。隣にいたドルモアが、抑えた声で聞く。
「どうされます、奥様。あの者たちを罰しますか?」
「罰する? なぜ?」
「上の階の方々……つまり侯爵家の方々の噂話はご法度です。聞いた場合は、罰するのが当然でしょう」
「具体的には?」
「まずは減俸ですね。反省が見られないなら、里に返すことになります」
「その必要はないわ」
ドルモアは嘆息した。
「奥様がお聞きになってしまったので、ご判断は奥様にお任せいたしますが。わたくしだけでしたら、相応の罰を与えたところですよ」
「そうなのね」
「ここには明確な規律がございます。規律は守らせないと、下々の者に軽んじられ、さらに厄介な問題に発展いたしますので」
「でも、夫人。まずはわたし自身がその規律とやらを、息を吸うように自然に守れるようになっていないと、彼女たちを罰することはできないでしょう。説得力に欠けますから」
ドルモアは目を見張った。
「まあ……そうですね」
「なので時間をください。わたしがんばりますから。胸を張って、旦那様に恥をかかせないように」
「フィリス様」
「誰もが認める侯爵夫人になってみせますから。その上で、先程のような陰口を申す者が現れたら、その時は罰を受けてもらいます」
フィリスはにっこりと笑った。
「では、中に入りましょう。きっととても慌てるに違いないから、可哀想ですけれどね」
茶目っ気たっぷりにそう言って、足取りも軽く中に入った。
「こんにちは。お仕事ご苦労さま」
フィリスの予想通り、そこにいた三人のメイドたちはぎょっとした顔をして、しどろもどろに挨拶をし、逃げるように部屋を出ていったのだった。
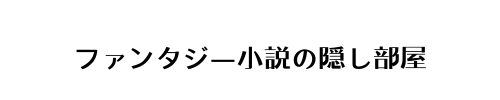


コメント