初めてのダンス
アルカルドが言ったように、その日、仕立て屋がやってきて、新しいドレスのために細かく採寸された。午前中は採寸と、ドルモアによる侯爵夫人の心構えについての勉強に追われた。
「奥様はひょっとしてお裁縫もおできになりますか」
ふと、ドルモアに問われ、フィリスは頷いた。
「はい。伯母や従姉妹たちほど上手ではありませんけれど」
「もしやそのドレスも縫われたのですか」
「そうです。何かおかしいですか?」
ドルモアは首を振る。
「いいえ。先程、仕立て屋が申しておりました。奥様のドレスは形は簡素ではありますが、とても丁寧な作りだと。生地の裁断も縫い目も完璧だと」
「それはとても嬉しいです」
フィリスはにこにこと笑って、サモワールから紅茶を注いだ。アルカルドに茶を出す前に、ドルモアが作法を見たいと言ったためだ。
「生地も実は大変上質な絹を使われていると。どちらでお買い求めになった布なのですか」
「ドレスに使う布地は、自分たちで作っています」
ドルモアは、えっと素っ頓狂な声をあげた。
「絹を、ご自分たちで?」
「はい。領地では蚕を大量に飼育していて、繭から糸を紡ぎ、生地を織り上げます。時間はかかりますが、バランデュールの女たちは代々そうやって自分で着る服は自分で作ってまいりました。糸車や機織りは従姉妹たちの役割で、わたしはもっぱら蚕の飼育と、桑畑の管理が仕事でした」
「そ、それは……なんというかご立派です」
ちなみに生地の濃紫色は、熟した桑の実で染め出したもの。桑の葉は養蚕に欠かせず、実は熟し具合によって薬にも食用にもなる。
「このドレスの生地はまだ余っていたはずです。よろしければ夫人に一着縫って差し上げましょうか? 生家に連絡すれば、布地を送ってくれるはず」
「いえ、とんでもない!」
ドルモアは目を白黒させて、フィリスが淹れたばかりの茶を口に含んだ。その目が、再び驚きに見開かれる。
「この茶葉は?」
「夫人が用意してくださったものですよ。昨日も飲みました。おかしな味でしたか?」
「いいえ! 大変美味しゅうございます。ええ、とても同じ茶葉とは思えません」
フィリスはにっこり笑って自分も茶を飲んだ。
ドルモアはしげしげとフィリスを見つめた。
「……お作法も実は完璧なのですね」
「え?」
「食事やお茶をいただくお作法です。従僕たちも申しておりました。奥様は、貴族のご令嬢にしてはたくさんお召し上がりになりますが、作法は美しく完璧だと」
「まあ。皆さんとってもお優しい」
心からうれしく思い、そう言うと、ドルモアはさらに窺うような目で見て聞いた。
「……奥様は厨房をお使いになりたいと仰ってましたね」
「はい。旦那様に許可もいただきました」
「もしや、お料理がおできになるのですか」
「簡単なものならば。もちろんここの料理長には遠く及びません」
「旦那様に何を作ってさしあげようと?」
「胃腸の負担にならないスープや……焼き菓子も。わたし、愛用の型をいくつか持ってきましたので、それで」
「あの少ない荷物の中に焼き菓子の型が」
「はい。なにしろ愛着があって手放すのが惜しくて」
「ま、まさか。ご自分で鋳型を造られたのでは」
「いえ、鍛冶仕事は従姉妹の担当でした」
自分も含め、若い娘は八人。一番上は二十八歳で、フィリスは一番年若だ。それぞれの得意分野を生かした仕事を分担して行っていた。フィリスは養蚕と畑の管理、狩り。薬作りや薬草園の管理をする者もいるし、糸紡ぎや機織り担当の者、それから……祈りに専念する者。
掃除や料理だけは皆平等に、交代で。
「なにしろ生家では自給自足が当たり前ですから。馬の蹄鉄や厨房用品、矢じりまで、鍛冶屋がいないので、幼い頃から自分達で……」
「も、もうけっこうでございます」
ドルモアは手を振って制した。フィリスは考える。どうやら想像していた以上に、貴族の奥方は自分でやることは少ないらしい。もし、畑に使う肥料も牛や馬の糞を配合し自分で研究していたと知ったら、卒倒してしまうかもしれない。
「……わたくしは、大いに勘違いしていたかもしれません」
茶をすべて飲み終えた夫人は、つぶやくように言った。
「フィリス様は侯爵夫人として学まねばならないことが多いと申しましたが、おできになることは多いのですね」
「でも、侯爵家のしきたりや上流社会の作法などは知らないことが多いようです。本で読んだだけですから。教えていただけるのはとても助かります」
謙遜でもなくそう言うと、ドルモアは気を取り直したような顔をした。
「もちろんお任せください。なんとしても、一ヶ月後のお披露目に間に合うよう、細かなことを詰めてまいりましょう。さっそくですが、フィリス様。ダンスの心得はございますか?」
フィリスは軽く目を見張った。
フィリスはその日の午後、厨房へと足を踏み入れた。ハウスメイドのアニカに案内されて、使用人だけが使うという階段を下り、半地下まで行った。
使用人専用の小さなホールを抜けて厨房に入ると、それまで忙しく立ち働いていた使用人たちは、いっせいに動きを止めて、しんと静まり返る。
「コルテスさん。あの、奥様がおいでになりました」
アニカが厨房奥にいる男に遠慮がちに声をかける。料理長にふさわしく白く高い帽子をかぶった男はこちらに背を向けたまま、ひとりで鍋をかき回しているようだ。
「あなたが料理長のハンス・コルテスですか。わたしはフィリスと言います」
フィリスが名乗ると、顔を心持ちこちらに向けて、軽く頭を下げた。小さく「どうも」と言っただけで、また鍋の方を向いてしまう。
「美味しい食事を作ってくださって、ありがとうございます。お陰でこちらの生活に食べる楽しみが増えましたし、毎日力が漲るのを実感しているところです」
コルテスは、すると、ようやく手を止めてこちらに向き直った。三十代後半くらいだろうか。背も身幅もとても大きい。ただ、フィリスを見る目は冷たく、うるさがっているのが一目瞭然だ。
「侯爵夫人ともあろう方が、わざわざ階下においでなさって礼を述べる必要なんてありません。俺たちは自分の仕事をこなしているだけなんで」
「聞いていると思いますが、厨房が空いている時間に少し使わせていただきたいので、その挨拶も兼ねてまいりました」
「聞いてますよ。まあ、正直あまりありがたくはないお考えですが、貴族の方々の気まぐれに付き合うのも仕事のうちなら仕方ありませんや。ドルモアさんに伝えましたけどねえ、昼食や夕食のご用意のあとでしたら、まあいいですよと」
「はい、聞きました」
「じゃあなんでわざわざ? ここに来る階段は狭く急でしょう。上でのんびりとお勉強でもなさっていたほうがいいんじゃないですかね。ご実家とここじゃ、何から何まで違うでしょうから」
くすくすと笑い声が起こる。アニカが背後からそっと言った。
「……戻りましょう、奥様」
フィリスはアニカを手で制して、じっとコルテスを見つめ言った。
「お礼も挨拶も直接言わなければ意味がありません」
「はあ、そうですかね」
「確かにわたしは上流貴族としての嗜みに疎く、勉強も必要です。でもわたしは、人の働きによって助けられたり、感銘を受けた時は、身分にかかわらず礼節を重んじるものだと教わってきました」
フィリスはコルテスだけではなく、再びしんと静まってこちらを見ている使用人たちひとりひとりを見て言った。
「だから、どうもありがとう。毎日とても美味しい食事を作ってくださって。おかげでわたしは本当に元気でいられます。食は幸福の、とても大切な要素です」
それから、と続けた。
「あなた方の仕事場をかき乱すつもりはありません。厨房の隅をほんの一時貸していただけたら、片付けまで自分でいたします。どうぞよろしく」
「……お好きになさってくだせえ。あなたは侯爵夫人だ」
コルテスは苦虫を噛み潰したような顔をして、再び鍋の方を向いた。
「……ということがあったようでございます」
その日の夕方、ドルモアが書斎に現れて、厨房の出来事をアルカルドに伝えた。アルカルドは目を通していた書類をいったん脇に置き、呟いた。
「料理長を黙らせたとは、なかなかやるな」
ハンス・コルテスは腕のいい料理人だ。貴族社会で腕の立つ料理人は奪い合いであり、コルテスは家令のバルローが、某伯爵家から引き抜いた男だった。
腕がいい代わりに自尊心も高く、愛想がない。
しかし仕事に厳しい彼のおかげで侯爵家の厨房は統制が取れて回っているともいえる。そこにあの風変わりな娘が顔を出すことになり、厨房を使用することを許可はしたものの、アルカルドは気になっていた。
「実はその後も、奥様を口さがなく言う者たちがいたそうなのですが、コルテスが一喝したそうです。自分が許可したのだから、とやかく言うなと」
アルカルドは思案する。
「ドルモア。彼女の何が、あのコルテスを黙らせたのだろうか?」
「あくまでわたくしの考えですけれど。おそらく、嬉しかったのではないでしょうか」
「嬉しい?」
「奥様はまず、お礼を述べられました。日々の食事の素晴らしさについて。それが口先だけではないことは、この屋敷の者は分かっています。たくさんお召し上がりになりますし」
「確かに」
アルカルドはふっと微笑む。フィリスの食欲は朝から旺盛だ。今朝、顔色が少し悪いような気がしたものの、それも食べている間にみるみる良くなった。
「旦那様。奥様は、ご実家で、どのような生活をなさってきたのでしょう」
ドルモアが、途方にくれた様子でそんなことを言う。それもこの完璧な家政婦にしては珍しいことだ。
「奥様は狩りや獣肉の解体のほか、生糸の生産やドレスの縫製もなさるようです。失礼ながら、最初は大変に粗野なお育ちの方がお嫁にいらしたと絶望に近い気持ちで……」
乗馬、しかも貴族の令嬢の乗り方とは違ってまさに雄々しく草原を駆け抜ける手綱さばきは、アルカルドも確認した。しかし、狩りや獣肉の解体? 生糸の生産? 大いに驚き、黙り込んでいると、ドルモアは続ける。
「なにしろ持ち物も本当に少なくて……それでも数少ないドレスはとても上質なものなのです。こちらを御覧ください」
ドルモアはハンカチを取り出し、机に広げた。アイボリー色の布地に同色の糸で繊細な刺繍が施してある。花模様とも違う、何かの凝った意匠を繰り返し重ねてあるものだ。アルカルドは武人であり、女子の持ち物に詳しくはない。しかしそのアルカルドにも分かる。これは、とても見事だ。
「こちらは奥様のご親族が刺繍されたものだそうです。布も、ご親族の女性が織られたと。王族の方々でも、これほど見事な小物はお持ちではないでしょう」
バランデュールはどこの領地とも行き来がない。
建国から二百年余、あの森の奥で暮らす人々は、自給自足のために様々な技術を身に着けただけではなく、その手技は高度な芸術をも生み出したというのだろうか。
「話に聞いた限りでは、奥様は閉鎖的な環境でお育ちになったと。しかし、驚くのはこればかりではございません。お食事の作法は量はともかくとても洗練されて美しいですし、姿勢も正しく、足運びも静かで綺麗です。ああ、それから……」
「まだあるのか?」
アルカルドは半ば呆れた。フィリスが嫁いできてまだ一週間だ。ドルモアがこれほど一度に話すところも、生まれて始めて見た気がする。
「はい。旦那様。奥様は、読み書きも完璧ならば、王国の歴史にも精通なさり、古代ゴルダ語もお読みになれるのです」
古代ゴルダ。グランタール王国の建国以前、はるか昔大陸に存在したという国。神が最初に大陸に作った国で、神の子が初代王として君臨し、精霊が国や民を守っていた。しかし人の悪意に弱く、西方から頭角を現した民族に侵略され、没したという。ゴルダ国はそれこそ謎が多く、残されている記録や文献も少ない。
ただ神が愛でた国であったことから、聖職者たちの間では絶対的に神聖視されており、古い聖典や儀式などには古代ゴルダ語が使用される。
王国の由緒正しい貴族の家には、枢機卿が祈祷し浄化した聖典が置かれている。この家にも図書室に置いてあったはずだ。もちろん、実用的なものではない。アルカルドも読めないし、代々の侯爵で読めた者もいないはず。
あれをフィリスが読んだというのか?
「……確かにバランデュール家は古代ゴルダ王国の流れを汲むと聞いてはいたが」
「なんでもご実家では、朝夕のお祈りにゴルダ語が使われていたとおっしゃるのです。わたくしは本当に驚きました」
他にもドルモアは、フィリスについて驚くことを並べ立てた。茶の淹れ方が家政婦である自分や他の上級使用人の誰よりも優れている。古代ゴルダ語のみならず、大陸の少なくとも他二カ国の言語にも精通しているようだ。彼女が持参してきた軟膏は非常に良く効くと、ハウスメイドのみならず、水仕事をするキッチンメイドやスカラリーメイドの間で早くも評判になっている。
「できないことはないと?」
「髪をまとめるのは苦手なご様子ですね。なので、侍女をつけるまではただひとつに結ばれていたのです」
「ほう」
「肌のお手入れや髪のお手入れには無頓着ですね。ああ、ただ……親族の女性に持たされたという美顔水をご愛用です。そのためかお肌はとても綺麗でいらっしゃいます」
確かに。フィリスの肌はアルカルドが知る女たちの中でも白い。化粧は普段しないようだが、何しろ肌が美しいので好ましい。
「見た目を繕うことには興味がなかったのだろう」
まだよく知らない間柄だが、それもなぜか彼女らしいと思えた。
しかし、アルカルドは引っかかりを覚える。親族の女性が、会話の端々に登場する。曾祖母に祖母、伯母が三人、従姉妹が確か、七人ほど。その女性たちも謎だ。伯母たちは誰も嫁がず、婿も取らず、子を産み、森の奥で今なお暮らしているということか。
「あと、もうひとつございました。フィリス様がおできにならないことが」
ドルモアがなぜか嬉しそうな顔をしている。アルカルドは大いに興味を引かれた。

わたしは夢を見ているのかもしれない―――。
フィリスは実際、夢見心地で、教わったばかりのステップを踏む。ドルモアの采配によって、フィリスはダンスを習うことになった。貴族のたしなみとしてのダンスは、確かに習ったことはなかった。誰かと踊る機会がなかったためであり、そもそも相手となる人間もいなかったのだ。
それが今、相手を務めてくれているのは夫であるアルカルドだ。ピアノの調べに乗って、ホール内をゆっくりと移動しながら踊る。手やステップの細かい部分は、侍女のクロエに教わり、アルカルドと共に実際に踊るという流れ。
最初は何回かステップを間違えたり、曲に遅れたりしたフィリスだったが、すぐに形にすることができた。
「覚えが早いな」
踊っているさなか、アルカルドにそう褒められ嬉しくなる。
というよりも、アルカルドに手とり足取り教わっている状況そのものが嬉しく、楽しく、自然と表情が華やぐのだった。
アルカルドに手を取られ、腰を支えられ、ステップを踏む間、彼の青い瞳がじっと自分に注がれる。顔が近く互いの息を感じられるほどだ。
アルカルドのリードは自信に満ち溢れ、慣れないフィリスを次の動きに上手に誘う。右腕の不自由さもいっさい感じさせない動き。曲が終わって、互いに少し距離を取り、お辞儀をする。フィリスはいつまでも踊っていたいと思ったが、アルカルドの方が、
「ここまでにしよう」
と切り上げてしまった。彼はフィリスを壁際の椅子まで連れてゆき、そこに座らせる。ドルモアやクロエも側まで来た。
「どうなさいました」
「踵を痛めたようだ。至急手当を」
確かにフィリスは右脚の踵を痛めてしまった。慣れない踵のある靴で踊ったせいだろう。
「わたし大丈夫です」
フィリスは足を引っ込めようとする。
「まだ、できます」
アルカルドは、しかし問答無用でフィリスの足を引っ張ると、やや強引に靴を脱がせた。
そして踵を観察する。なんだかとても恥ずかしくて、フィリスは赤くなってしまった。
「あの……旦那様」
「名前で呼ぶように言っただろう。フィリス。靴はこれだけか?」
「はい。他には乗馬用のブーツだけです」
この靴は結婚式にも使った。実は普段は、靴は履かずに育ったと言ったら、驚かれそうだ。フィリスは裸足で森を駆けるような少女時代を過ごした。
さすがに乗馬や農作業の時は靴を履いたが、基本的にはブーツで、踵のあるような靴を履いたのは結婚式が初めてだったのだ。そのせいもあって、式では何度かよろめいて転びそうになったのである。
ドルモアが言った。
「昨日、ドレスと同時に靴も何足か注文いたしましたから、舞踏会には間に合いますでしょう」
「では練習はほどほどに。当日も一、二曲踊ればいいのだから、それほど心配はいらない」
フィリスはがっかりした。アルカルドと踊るのは本当に幸福だった。できれば毎日こうした時間を持ちたい。ふたりは夫婦になったが、一緒に何かをする時間は、想像していたよりとても少ないから。
「もう……教えていただけないのですか」
気持ちが言葉と表情に出てしまったのだろう。アルカルドはフィリスを見て、言った。
「俺は君の足を心配したのだが……もし大丈夫だと言うなら、また時間を取ろう」
「もちろん、大丈夫です!」
顔を輝かせて即答すると、アルカルドはくしゃりと笑った。
「では、今日のところはよく手当をするように。君は、とてもよく効く薬を持参してきていると聞いた」
「はい。明日には、きっと良くなります」
アルカルドは頷き、微笑んだまま、ホールを出ていった。
「驚きましたわ」
呟いたのは、クロエだ。
「旦那様があんな風に笑われるところは、初めて見ました」
「アルカルド様は、もともととても感情表現が豊かなお子様だったのですよ。軍務で責任あるお立場になられてからは、今のような冷静さを落ち着いたお振る舞いを身につけられましたけどね」
アルカルドを幼少期から見てきたドルモアはそう言った。
「でも確かに、久しぶりです。きっと奥様のお陰でございましょう」
「わたしですか?」
「奥様が素直に感情表現をなさるからですよ。旦那様は先の戦からご帰還後、ずっと難しい顔ばかりされていましたから」
それはおそらく、例の怪我のせいだ。フィリスは胸が痛んだ。
やはり一日でも早く治療を開始しなければならない。そう決意したのだった。
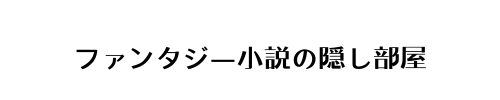


コメント