せっかく嫁いできたけれど
信じられない。
わたしは、なんて幸運な娘なのだろう。
フィリスは祭壇の前に立ち、夢見心地で、隣に立つ自分の夫となる青年を見た。
彼、アルカルド・ヴァン・エントワーズは若き侯爵にして、つい最近までグランタール王国軍の将官を務めていた。銀狼の戦神との異名にふさわしく、輝く銀髪と青い瞳を持つ美貌の青年だ。上背はこれまでフィリスが見たどんな人間より高く、肉体は細く引き締まっていて、婚儀のために着用した濃紺の軍服が非常に似合っている。
一方で、花嫁である自分はどうだろうか。
髪は黒色、うねりが強く、今はなんとかまとめられてヴェールの下におさまってはいるが、毎朝梳るだけでも一苦労。瞳は暗い緑色。顔立ちは平凡で、背は低め。深い森の奥で生まれ育ったため、肌は白い……が、鼻の頭にうっすらとそばかすができてしまっている。今は化粧でなんとかごまかしているけれど、花嫁の支度を手伝ってくれた女たちの眼差しは、なかなか辛いものがあった。
フィリスは、十九歳の今まで自分を客観的に見たこともなければ、他人の容姿に興味感心を抱いたこともなかった。それが今、まさに、痛感している。
夫なる彼、アルカルドは、非常に美しい。武人らしく鍛え上げられた肉体をしているのに、顔の造作は繊細で整っている。
自分は、美しくはない。そしてふたりは結婚式の今日、今この瞬間が、ほぼ初対面なのだ。ほぼ、というのは、フィリスは過去に彼に一度だけ会ったことがあるから。しかしもう十年以上も昔のことである。
神父に促され、フィリスのヴェールが手袋をはめた彼の手によって持ち上げられる。初めて、正面から、互いの顔をじっと見つめ合った。
ああ、やっぱり、なんて素敵。フィリスは嬉しくなり、美貌の青年に、笑いかけた。しとやかに、声も立てず微笑んだだけだったのに、彼、アルカルドは怪訝そうな顔をした。そしてその青い瞳に失望の色が浮かぶのに、あまり時間はかからなかった。

「君も承知していると思うが、我々の婚姻は多分に契約的な意味合いが強い」
その夜、寝室で初めて口をきいた夫は、低く抑揚のない声でそう言った。
巨大な寝台を前に、互いに夜着の姿で、向かい合って立っている。フィリスは、生真面目な顔で頷いた。
「契約内容は承知しています」
フィリスの生家は、エントワーズ侯爵領に隣接する森林を領地とするバランデュール伯爵家。もっとも貴族とは名ばかりで、実態は平民とそう変わらない。領地の九割は森に覆われている。起伏が激しく、深い渓谷や急流に阻まれ、近隣領地との交流はほとんどない。産出できるほどの農作物はなく、唯一豊富にある材木は、昔からの決まりで伐採できないことになっている。そのためごく限られた土地で育てる農作物で、自給自足の生活を行うことが余儀なくされていた。
古い石造りの城が住居だったが、フィリスの他には、年老いた曾祖母、祖母、伯母が三人、従姉妹が七人という、女ばかりの少々変わった家族構成で、使用人もいない。
父は、フィリスが生まれる前に死んだと聞かされている。そして母は、フィリスが八歳のある朝、領地を出て、二度と帰らなかった。
それから十一年。十九歳になったフィリスは、エントワーズ侯爵家に嫁ぐことが決められた。婚姻を命じたのはこの国の君主―――グランタール国王シャルゴード三世である。
実はフィリスには、十年以上も会っていない弟がいる。彼は赤子だった時に、母が領地から連れ出たまま、音信不通だ。この弟が、王から男爵位を授けられ、相応の領地を得られる運びとなった。
フィリスの生家バランデュール伯爵家は、代々、女しか相続できない。現在の女伯爵はフィリスの祖母だ。従って、本来、弟には領地も爵位も相続の権利はない。ところがこれを不服としたフィリスの母が、国王に便宜を願い出て、弟に新たな身分が与えられた。
フィリスの結婚は、その交換条件なのだ。
アルカルドの父親は国王の弟であるロシェル公であり、アルカルドも王位継承権を持つ。王室は、かねてより、バランデュール伯爵家との婚姻を希望していたらしい。そう……かれこれ二百年も昔から。
「君とは、後継ぎが無事に生まれたら離縁する」
アルカルドに言われ、フィリスは頷く。
「男子が生まれたら、ということですね」
「そうだ」
「女子の場合は、わたしと共に去ってもよろしいのですか」
「俺個人としては後継ぎの性別は気にしないが、父は男子を望んでいる。また、君の家も女子なら受け入れると聞いている」
子供が男子ならエントワーズの後継者としてここに残す。女子なら、バランデュールで育てる。第二子、三子と作る猶予はない。なにしろこの結婚には期限が決められている。
たったの、二年―――。
「……子作りはこの結婚の最重要課題だ」
「はい」
そう。王とロシェル公爵が欲するのは、バランデュールの血を引く子供。もっとも望ましいのは男子を産むことであり、フィリスは息子を手放しエントワーズ侯爵夫人の座から退く代わりに、国王と公爵からかなりの額の報奨金が約束されている。子供が女子であった場合、もしくは二年以内に身ごもらない場合は、報奨金は支払われないが、弟の男爵位はそのまま保持できる。
「だが、俺の目から見ると、君はどうにも子供を生むには幼いようだが……」
アルカルドは、じっとフィリスを見てそんなことを言った。
「大丈夫です、旦那様。確かにわたしは小さいし痩せていますけど、心身ともに健康ですし、風邪ひとつひいたこともないです」
「……そうか」
まだ何か納得できていない様子のアルカルドに、フィリスは焦る。どうにかして、この婚姻が履行可能なものであることを理解してもらわねば。たとえ二年という期間限定であったとしても。
「あの。それからわたし、こう見えて力持ちです」
「力持ちは関係ないのでは」
「関係あります。赤子を育てるのは重労働だと、わたしの祖母と伯母たちが常々言っておりました。力持ちだと、たとえ双子が生まれても、両方いっぺんに抱っこしてあやすことができますし」
「……なるほど」
「あ、あと、歯も丈夫なのです。御覧ください」
フィリスはアルカルドに一歩近づき、いーっと歯を剥いてみせた。アルカルドは面食らった顔をした。
「すみません。見苦しかったですか」
アルカルドは口に手を当てて俯き、いや、とくぐもった声で返事をする。
「君が健康体であることは分かった」
フィリスはほっとした。
「分かっていただけましたか!」
「だが、今日は疲れているだろう。先に休むといい。わたしはまだ片付けねばならない仕事がある」
「は、はい」
アルカルドは夜着の上にガウンを羽織ると、あっという間に部屋から出ていってしまった。
一人、残されたフィリスは、力なく寝台に腰掛けた。寝具は非常に肌触りがよく、良い香りもする。改めて室内を見渡すと、家具といい、カーテンや絨毯といい、どれもこれもうっとりするほど豪華なものであることが分かった。
嘆息し、横になると、軽く温かな掛け布団を顎まで引き上げる。厚意に甘えて先に寝るのも申し訳ないような気もしたが、確かにフィリスは、とても疲れていた。
それにしても。今日は結婚式で、初夜だというのに、ひとりでこの寝台で眠ることになるとは。
でも大丈夫。きっとなんとかなる。わたし、あの方と結婚できたのだから……。
アルカルドはフィリスとの出会いを憶えてはいない。そのこと自体は予測できたことなので驚いていない。
それでも彼はフィリスの初恋なのだ。初恋の人と再会できたばかりか、結婚することができるなんて。フィリスは、自分は本当に幸運な娘だと思いながら、ひとりきりで、眠りについた。
アルカルドは執務室の椅子に背中を預け、深く嘆息した。
何もかもが想定外の出来事の連続である。まず、つい先月まで陸軍の将官として西方の騎馬民族と戦っていた自分が、領地に戻り、一線を退いたこと。その原因は、この忌々しい右腕だ。
戦で、アルカルドは右腕を負傷し、剣を握れなくなった。単なる一騎打ちで敗れたというには、あまりにも不可解で、おぞましい出来事があったためだ。物心ついたときにはすでに剣と共にあったアルカルドには、耐え難い日々の始まりでもあった。
それから、降って湧いたようなこの結婚。アルカルドには、幼少期に定められた婚約者が別にいた。その婚約を破棄し、バランデュールの娘と結婚するよう命じたのは、現国王だった。
「バランデュールか……」
確かに領地は隣り合ってはいるが、彼の伯爵家は、長年謎に包まれた一族だ。エントワーズ領の北東、マルレ川を挟んで向こう側に広がる広大な渓谷と森。それすらも、川幅が広すぎて遠くに霞のように見えるだけだ。
伯爵家の人間を、もう長いあいだ、誰も見たことがない。過去幾人もが、あちらに渡ろうとして溺れ、命を落とした。アルカルド自身も少年の日、冒険心から川に入ったことがある。しかし結局は流れに逆らえず、押し戻された。前後の記憶がはっきりしないが、なぜかそれきり興味を失い、二度と向こう側に渡ろうとはしなかった。

そのマルレ川は、国の歴史書には常世につながるメライア川という呼称で記されている。メライアを無事に行き来できるのはグランタールの国王と聖職者のみとされ、実際、シャルゴード国王も年に一度、大神官を伴って現地を訪れている。不思議とその日は舟がひっそりと着岸し、王を森の懐へと誘うのだという。
そこで三日間の潔斎の後、国の平和と五穀豊穣を願う儀式を執り行うとも聞いたが、本当かどうかは定かではない。
ただ、一ヶ月前ほど前。王は確かに、バランデュールに渡った。いつもならそのまま静かに王都へ帰るのに、今年は何を思ったか、エントワーズに立ち寄った。
そしてこう言った。
『よいか、アルカルド。バランデュール家の娘との婚姻は、我が王室にとって悲願である』
シャルゴート三世には、成人した王太子がいる。アルカルドの従兄弟にもあたる。しかし彼は昨年、隣国の王女と結婚したばかりだ。それで白羽の矢がアルカルドに当たったというわけである。
王だけではなく、父ロシェル公も、どういうわけか、この婚姻を強く望んだ。
一説によると、バランデュール家はこの国が建国されるより前に存在したゴルダ王国の流れをくむ家柄らしい。その古い王国では、魔法が当たり前に存在したとされている。そのため、森の奥深くで暮らす伯爵家の人間は、魔法使いであるとか、魔女であるとか、魔物そのものであるとも言われている。
「魔物……」
アルカルドは、ぞくりと肌が粟立つのを感じた。咄嗟にガウンと夜着の肩を外し、自分の右上腕部を見下ろす。赤紫色の大きな痣があり、それは、人間の手の形をしている。痣はよく見ると蛇の鱗状の模様があり、その中央には鋭い牙を突き立てられた痕が、黒々とした二つの穴になって残っていた。
この痣が生じたあの日から、アルカルドは剣を振るう力を失った。
日常生活に支障はないものの、それまでのように重い鋼鉄の剣を自在に振るうことはかなわない。鱗の模様は日に日に濃くなり、それに伴って痺れも増している。牙の痕に似たふたつの穴からは時折出血もあり、じくじくと痛んだ。王都のどんな名医さえ、この症状には匙を投げた。
魔物など、信じていなかった。しかし、アルカルドは実際に魔物に刻印を刻まれた。前線から王都に呼び戻され、今度は、魔女と噂のある一族の娘との結婚を命じられた。
自暴自棄に近い気持ちにもなっていたかもしれない。もともとの婚約者は幼馴染でもあったが、互いに家のためと割り切っていたし、執着があったわけでもない。誰と結婚しようと同じだ。王や父に歯向かう気力も残っていなかった。ましてや、アルカルドは、分かっていた。
おそらく自分は長くは生きられない―――。
そうであるならば、後継ぎは早くもうけておくべきだ。なにしろ自分は父公爵のたった一人の息子なのだから。
そういった経緯で、結婚に期限をもうけたのはアルカルド自身だ。若い娘を寡婦としてここに縛り付けておくことはできない。
結婚相手に多くは期待していなかった。
それが―――。
『わたし、こう見えて力持ちです』
自分が健康体であると、必死に訴えてきた娘。今まで接してきた多くの女は、自分がいかに美しいか、身分が高いか、あるいは女らしいかを示そうとしていたものだ。それが、アルカルドが妻にした娘は違う。
顔を見たのは、今日が初めてで、しかも祭壇の前だった。ヴェールをめくった時、現れた顔が、あまりにも幼いと思い、不安を覚えた。確か十九歳と聞いていた。アルカルドは二十五歳だ。それでなくても六歳の差があるのに、彼女は、まるで十四、五歳くらいに見えた。小柄で、あどけなさの残る丸い顔をしていて、緑色の瞳は好奇心に輝き、終始にこにこと笑っていた。
聞いたところによると、彼女は単身でエントワーズにやってきて、門を叩いたという。婚儀というのに、親族はひとりも参列していなかった。もっとも侯爵家側も、突然の婚姻の命令で周知が間に合わず、参列したのは比較的近隣に住む親族のほか、家令を始めとした一部使用人と、村の有力者くらいだ。王都のタウンハウスに住むアルカルドの両親さえ、出席を見送ったほどだ。
それもまた王命のせいだった。
婚儀は必ずや、夏至の日に行うように―――。

互いに目的が明確な契約結婚ならば、婚礼の参列者は少なければ少ないほど都合が良かった。式は屋敷内の礼拝堂で、年老いた神父が執り行い、婚礼後の晩餐会も簡素なものだった。そのまま粛々と初夜を終えるつもりでいたのだが。
『歯も丈夫です』
初対面で……いや、気心が知れた女性からでさえ、歯を見せられたことなどない。それもあんなに思いっきり。
思わずアルカルドは笑いそうになって、俯き、こらえた。それでもどうしても笑いを我慢できず、慌てて部屋を出たのだ。
「……ふ」
思い出すとまた笑ってしまう。そこで、はたと気づいた。
俺が笑うだと?
この忌々しい痣を得て、領地に戻ってから、一度として笑ったことはないというのに。
誰もいないのに体裁が悪く、咳払いをして書類に意識を集中しようと試みる。しかしどうしても、あの娘の、歯を剥いた顔が浮かんできてしまう。
「……あれが妻とは」
苦笑し、首を振った。十代の頃から軍事訓練と実戦に明け暮れたアルカルドだったが、多少の遊びはした。彼女……フィリス・バランデュールは、アルカルドの好みから大きく外れている。
変わった娘だ。
男子が生まれれば、侯爵家の後継ぎとして養育され、未来のロシェル公として、グランタールの王位継承権も得る。
ただ、あの娘が閨でどういう様子をみせるのか、想像するのは非常に難しい。
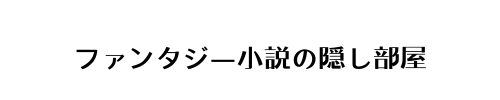


コメント