こう見えて大食いなのです
フィリスは早朝に目覚めた。起き上がってすぐに隣を見たが、夫となった若き侯爵がそこで眠った気配はなかった。
がっかりしつつも、寝台から下り、自分で分厚いカーテンを開ける。ついでに窓も開けて外の空気を入れた。
外はまだしらじらとしている。朝靄に霞んだ森が遠くに見えた。バランデュールではない。ふとせつない気持ちになったが首を降り、手早く夜着を脱いだ。
フィリスが持参した衣類は多くはない。結婚生活のために伯母や従姉妹たちが夜なべして縫ってくれた新しいドレスが一着と、古い濃紫のドレスが一着。あとは下着くらいだ。少し迷ってから、着慣れた濃紫のドレスにした。
髪は、普段通り、丁寧に櫛ってからひとつに結ぶ。化粧品の類は持っていない。装飾品は、やはり伯母たちがそれぞれ一つずつくれた琥珀のブローチと、黒瑪瑙の耳飾りと、緑柱石の腕輪である。普段身につける習慣がないため、宝石箱にしまったままにする。
寝室に隣接する衣装部屋には、昨日着た花嫁衣装がかけられている。胸と裾一面に芥子粒ほどの無数の真珠が縫いつけられたそのドレスは、先代の侯爵夫人、つまりアルカルドの母が着用したものだという。ただしフィリスには大きすぎたため、あちらこちら縫い詰めて着用した。
その他、持参した荷物が少ないこともあって、衣装部屋はがらんとして見える。かつての自分の部屋と同じくらいの大きさだから、いっそここで寝起きする方が落ち着きそうだな。そんなことを考えながら廊下に出た。
廊下はまだ薄暗い。耳を澄ますと誰かが起きて立ち働いている音は聞こえる。フィリスは音がする方へ足を向け、廊下の突き当たりにある大きな部屋に入ってみた。
「あっ……」
驚いた声をあげたのは、まだ若い娘だ。といっても自分より少し下くらいか。焦げ茶の髪をお下げに結び、メイドのお仕着せを着ていて、薪の束を両手で抱えるようにして持っている。
「おはよう」
少女は慌てた様子で薪を下に置き、頭を下げた。
「お……はようございます。お、奥様」
奥様と、初めて呼ばれ、フィリスはくすぐったい気持ちになる。
「フィリスでいいわ。あなた、名前は?」
「……アニカと申します」
「アニカ。可愛い名前ね。お仕事中、申し訳ないけれど、お屋敷の中を案内してもらえるかしら?」
アニカはびっくりした顔をした。
「ど、どちらへ?」
「いろいろ見て回りたいけれど、それはおいおいとして、そうね……まずは厨房へ」
フィリスはとてもお腹が空いている。生家に使用人はおらず、従姉妹と交代で家族全員の食事を用意した。侯爵家がどうなっているのかまだ分からないが、早朝、使用人たちの手をわずらわせるのは申し訳ないので、厨房に自分で出向き、簡単なスープでも作ろうと思っていた。
しかし、目の前のメイド、アニカは、見る見る青ざめる。
「……ど、どうか、お許しください」
目を見張ったフィリスに、彼女はしどろもどろに言った。
「奥様がこれほど早起きされるとは、あのう、思ってもいなかったのです」
「わたし、いつもこのくらいの時間に起きるのよ。それより、許せってどういうこと?」
「……あたしはハウスメイドです。下級使用人ですから、本来、侯爵家の方々の目に止まってはならないのです」
「そういう決まりが?」
「左様です。ご家族の方が起床されるより前に、お部屋に火を入れるのが仕事のひとつです。ですからどうか、お許しくださいませ」
フィリスはなんと答えていいのか分からず、ただ、曖昧に頷いた。
「そうなの……でも、わたし、あなたに会えて嬉しかったけれど」
まさに渡りに船という感じで。なにしろこの屋敷は広すぎる。微笑んで見つめていると、彼女はさらに居心地悪そうな顔になった。
「す、すぐに侍女を起こして参らせます。お食事のご用意も、あたしが伝えますので」
呼び止める間もなく、アニカは出ていってしまった。
あの様子では、どうやらフィリスが勝手に歩き回ると、この屋敷の人びとの迷惑になるようだ。
ただ、アニカは結局、暖炉に火を入れることなく行ってしまった。バランデュール同様、ここエントワーズの夏も、早朝と夜間は冷える。フィリスはドアから顔だけ出して廊下に人の気配がないことを確認すると、薪を暖炉にくべた。そして左の手のひらを上に向け、そこに生じた熱を、さっと暖炉の奥に送り込むように動かした。
重ねた薪の奥に火がともるのは一瞬だった。

『フィリスや。可愛い姫や。よいか、メライアの向こうでは、力を使っては駄目だよ』
祖母の言葉が耳の奥にこだまする。
力は、生まれた時から当たり前に存在した。どうして川のこちら側で使っては駄目なのか、フィリスは理解している。過去、同じように力を持つ一族の女たちは、森の奥深くで暮らしている分には良かったが、外で力を使い、不幸を招いた。
忌まわしい魔女として糾弾され、中には、火炙りになった者もいたと聞く。
だからフィリスも、控えるつもりできたのに、つい使ってしまった。
「あの子の手。痛そうだった……」
フィリスは自分の手を見る。荒れてはいないが、そう綺麗なわけでもない。炊事洗濯、糸紡ぎ、なんでもやってきた。弓矢で狩りもしたから、一部の皮膚は硬くなってタコもある。
日常生活の中では、時々、力が今のように役に立った。
アニカの手は、あかぎれだらけで関節からは血が滲んでいた。よく効く軟膏を持っているから、彼女にあげたいけれど……。フィリスは暖炉の火を火かき棒で調整し、よいしょ、と腰を上げた。
侍女を行かせるとアニカは言ったが、部屋にやってきたのは家政婦のトリシュ・ドルモアだった。
ドルモアは五十歳くらいで、髪には白いものが目立つものの、一本の乱れもなく大きめの髷にまとめ、糊の効いたドレスを隙なく着た痩せぎすの夫人だ。歩く度に衣擦れの音に混ざり、腰のベルトにさげた鍵の束がじゃらじゃらと鳴る。フィリスは後から知ったのだが、一般的な貴族の館において、家政婦とは、家令や執事と並び立つくらい権限を持つ人物らしい。
「フィリス様。早起きはいい習慣ですが、使用人より先にお起きになるのはおやめください」
ドルモアは朝の挨拶をすませるとすぐにそう言った。
「ごめんなさい。お腹がとても空いてしまって。あ、厨房さえ教えてくださったら、今後は自分で……」
「とんでもございません!」
ぴしゃりと遮られた。
「エントワーズ侯爵夫人ともあろうお方が、ご自身で厨房に立たれるなど。前代未聞です。よろしいですか。侯爵夫人は、厨房に献立の指示を出すことはあれど、調理をすることはございません」
フィリスは大いに驚いた。
「そう……なの?」
「当家には料理長を筆頭に三名の料理人と十人のキッチンメイドがおります。フィリス様がお召し上がりになるものは、すべて彼らが準備し、従僕が給仕いたしますので」
「では……食材を調達する必要もない?」
ぴくりと、夫人の頬が動いた。
「調達、とは?」
「あの。領地にいた頃は、わたし、沢沿いの畑でじゃがいもや葉物野菜を収穫したし、森で樹の実や果物を……」
「侯爵家と契約した指定農家から定期的に納められますし、足りないものはメイドが村まで買いにまいります」
「あの、では、肉とか」
「……お肉でございますか?」
「わたし狩りが得意なの。ウサギは罠が効率よくて、鹿はやはり弓ね。滅多に狙いもはずさないし、血抜きして解体して、毛皮も綺麗に川で水洗いして干して。新鮮な肉をその日の食卓で食べて、余ったら干し肉に……どうかなさった?」
ドルモアがよろめいて椅子の背につかまったため、フィリスは心配した。
「まあ顔色が。大丈夫?」
「……少々頭痛がしてまいりました」
「それはいけないわ。夫人、よろしければわたしが持参した頭痛や貧血によく効くお茶を……」
「けっこうです。フィリス様。ほんの少し、わたくしにお時間を」
「ええ、いいわ」
フィリスは口を閉じ、じっと待った。その間に、お腹がぐうと鳴ってしまい、夫人がかっと瞳を見開いた。
「……ええとその。ごめんなさい」
気恥ずかしくなって照れ笑いを浮かべると、ドルモアはなぜか憐れむようにフィリスを見た。
「どうやらフィリス様には、一からいろいろと覚えていただくことがたくさんあるようです」
フィリスは頷いた。
「そのようね。ドルモア夫人。いろいろ教えてくださると、わたしもとても助かります」
「……よろしいでしょう。今日からさっそく取り掛かります。ちょうど一ヶ月後に、フィリス様をお披露目する舞踏会が行われます。それまでになんとか、マシになっていただかなければ!」
フィリスは目を丸くした。
「わたしの、お披露目?」
結局その日、フィリスが朝食にありつけたのは、起床から三時間後のことだった。
フィリスはドルモアに食堂に案内された。そこは今朝方アニカに会った場所で、朝食のための部屋だったらしい。ちなみに昼食のための部屋と、午後のお茶をいただくサロン、夕食のための部屋、客人を招いたときに利用する大きな晩餐室など、食事に関する部屋だけで五つもあるとのことだった。
朝食室には、すでにアルカルドがいた。
「旦那様!」
フィリスは嬉しくなって、にこにこ笑いながらアルカルドの側に行った。アルカルドは席を立ち、礼儀正しく挨拶をする。
「早起きをしたそうだね」
「そうなのです。でも、あの、明日からもう少しは寝ているつもりです」
アルカルドは軽く頷く。フィリスはいそいそと彼の差し向かいの席に腰掛けようとしたが、
「フィリス様。こちらへ」
ドルモアに促され、見ると、テーブルの反対側の椅子を促されていた。なんだかとても遠いような。それでも言われた通り、そこまで行くと、従僕のひとりが椅子を引いてくれた。
「ありがとう」
テーブルには様々な食事が用意されている。籠に盛られた数種類のパンに、ケーキやプディングのようなもの。置かれている大小の皿は眩しいほど輝き、揃いのオレンジの花が絵付けされている。ほう、と思わずため息を漏らしたフィリスの前に、お茶が運ばれてきた。
「奥様。お茶の前にミルクになさいますか。林檎ジュースもございますが」
と従僕に聞かれた。フィリスは夢見心地で、
「ええとあの、両方いただきます」
と答えていた。

すぐに運ばれてきた林檎ジュースは濃厚で、酸味と甘味の塩梅がちょうどよく、非常に美味だ。ミルクは新鮮で、遠慮なく手に取ったペストリー類は乾燥させた果物、ナッツをふんだんに使用し、口に含むと芳醇なバターの香りがした。
次に運ばれてきたのはふわふわのオムレツで、マッシュルームのソースとよく合い、スープはトウモロコシが信じられないほどなめらかに裏ごししてあり、まろやかで、カリカリに炒めた玉ねぎがいいアクセントを添えていた。
フィリスは順番にそれらを胃袋に収めていった。
実は、食べ方の作法については、伯母たちは厳しかった。特に姿勢や、カトラリーの使い方は、幼い頃から徹底的にしつけられてきたものだ。森の奥でも、王宮の晩餐会に招かれなくても、食べるものが乏しくたとえクルミひとつ、卵ひとつのお皿であっても、淑女としての品位を失ってはならないと。そのためフィリスは、がっつかないよう注意しながら、丁寧に、ひとつひとつを味わい、観察し、舌で確かめ、香りを堪能した。すると、
「口に召したか?」
テーブルの向こう側のアルカルドに訊かれた。いけない。すっかり、夫の存在を忘れてしまっていたのだ。気づくとアルカルドのみならず、従僕やドルモアが、あっけに取られた様子でフィリスを見ている。
「は、はい。わたし、これほど美味しい朝食は初めてです!」
席が遠いのであえて大きな声でそう答えた。ドルモアがこめかみに手を当てる。また頭痛だろうか。従僕たちは見てはならぬものを見たかのような顔をし、フィリスは自分の食べ方の作法が心配になった。
ああ、本当は、このオムレツの残ったソースを、このパンのかけらで拭って食べたい。それは作法に反してはいないはずだ。しかしフィリスの皿は従僕によってさっと下げられてしまった。
少ししょんぼりしたが、正面に座るアルカルドを見て、安心した。
彼は穏やかに笑んでいる。フィリスもつられて、にこにこと笑った。
「……今日は午後まで時間が空いている」
アルカルドは言った。
「フィリス。君さえ良ければ、わたしが領地を案内しよう」
フィリスは顔を輝かせた。
本当に? 結婚早々、そんなに素敵なことが?
「はい! とても、とても嬉しいです、旦那様」
また大きな声でそう言うと、お茶のお代わりを注ごうとしていた若い従僕が、ぷぷっと声を漏らして笑ったのだった。
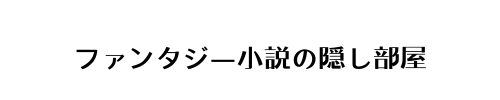


コメント