公爵の秘密
ほとんど他人と接したことはなかったから、人に悪口を言われることも、フィリスにとって新鮮なことではあった。もちろんあまりよい気分ではない。それよりも、彼女たちの話で気になったのは。
『お怪我さえなさらなければ……』
アルカルドは夜半、フィリスが眠ってから寝室に入ってくる。フィリスは寝たふりをするようにした。そうでなければ、アルカルドが出ていってしまうような気がしたのだ。
寝台の端で布団を被り、彼に背中を向けるようにして動かずにいると、アルカルドは静かに横たわり、フィリスと同じようにこちら側に背を向けて休む。
そうやって夜を過ごすようになってから三日目。フィリスはアルカルドのかすかな寝息を確認し、むくりと起き上がると、寝台の上をそろそろと移動した。
暗闇の中、じっと、夫である人の顔を見下ろす。そして、彼の右腕に触れてみた。
思わず声を漏らしそうになって口を押さえる。
アルカルドの右腕に残る魔の気配。彼の負傷は、魔物によるものだ。
その部分に手を触れたまま、目を閉じる。薄闇の中に、視える……彼にその日、何があったのか。
勇猛果敢に剣を振るい、騎馬民族と戦うアルカルド。戦の熱気と異様な空気が伝わってくる。
アルカルドは、全身に青い入れ墨をした戦士と戦っている。熾烈な闘いの末、相手は落馬し、奇怪な形の岩が特徴的な山へ逃げ込んだ。アルカルドも馬を捨て、男を追った。血痕が洞窟の奥へと続く。アルカルドは剣を手に、中へ入ってゆく。

暗がりの奥に座り込む戦士がいた。
真っ赤に染まった両眼と、耳まで裂けた口。顔だけではなく、体中に彫り込まれた青い文様が蠢き、男の口から呪詛の言葉が吐かれた。アルカルドは地面に縫い留められたかのように動けない。
そんな彼に、突如生じた黒い蛇が襲いかかってきた。
なんて、大きい―――!
そのまま右腕に噛みつかれ、アルカルドは苦悶の声を漏らす。牙が腕に食い込み、ぬめりを帯びた黒い鱗が暗がりで不吉に光った。
しかし、さすがは銀狼の戦神。彼は強靭な精神力で呪縛を解き、自分の腕ごと岩壁に蛇を叩きつけた。蛇は地面に落ちたものの、再び鎌首をもたげて踊りかかってきた。アルカルドは、今度は攻撃を許さず、剣で薙ぎ払った。
絶叫が響き、血しぶきと共に地面に転がったのは、蛇ではなく相手戦士の腕だ。
アルカルドは獣のように叫び、剣を逆手に持ち変えると、男の心臓付近に深々と突き立てた。絶命の間際、男は笑い、また呪詛の言葉を吐いた。
『おまえの肉体は腐りやがて朽ち果てる』
フィリスは、はっと声を漏らし、瞳を開いた。うめき声が聞こえる。発しているのは、眠るアルカルドだ。苦悶の表情を浮かべ、汗をかいている。
フィリスはアルカルドの腕に触れたまま、空いている左手で、そっと彼の額に触れた。それから、小さな声で歌を歌う。
幼い頃、悪夢を見た時は、祖母がこうして歌ってくれた。
『サンザシの枝を打ち鳴らせ
ほら白いカラスが来るよ
サンザシの枝を打ち鳴らせ
ほら白い蟲が羽ばたくよ
回せ 回せ 運命の糸車を
とんとん たたたん とんとんとん
流れる水を越えてはならぬ クルミの小舟が迎えに来るまで
サンザシの枝を打ち鳴らせ
回せ 回せ 運命の糸車を
とんとん たたたん とんとんとん……』
バランデュールの女たちが歌う子守唄には、言葉のひとつひとつに力が備わっている。やがてアルカルドの顔から苦痛は消え失せ、健やかな寝息が聞こえ始めた。
フィリスはほう、と息を吐いた。頭の芯がくらくらして、吐き気にも襲われた。全身が細かく震えている。とても寒い。このままでは、凍えて死んでしまうだろう。
座したまま、ころんと転がってしまい、起き上がることができなかった。寒くて仕方がないので、温かな何かにぴったりとくっつくようにして、深い眠りに落ちた。
早朝、爽やかな香りが鼻腔をくすぐり、アルカルドは目を覚ました。その瞬間に、妙に気分がよいことが分かった。
これほどぐっすりと眠ったのは、いつ以来のことだろうか……。
頭がすっきりしている。しかし、背中に慣れない人の体温を感じ、驚いて起き上がった。身体をひねるようにして背後を確認すると、彼の名ばかりの妻フィリスが、小さな子どものように丸くなって眠っていた。
室内には早朝の青く淡い光が漂っている。芳しい香りの正体は彼女か。ハーブのような、野生の野薔薇のような、不思議な香りがする。
黒髪がもつれて顔にかかっているのを、無意識のうちに手を伸ばして払っていた。アルカルドはじっと彼女の寝顔を凝視する。
「……寝相が悪いのか?」
寝台は大きく広い。端と端で眠っていたはずが、こちらまで転がってきたのか。
寝顔は、起きている時よりもさらにあどけなく幼く見えた。だが、こうして改めて見ると、彼女が実はとても整った相貌をしていることが分かる。目鼻立ちは確かな気品があり、小さな鼻はすっと筋が通り、唇の大きさや形も申し分ない。そして薄暗がりでも、とても色が白いことは確かだった。
アルカルドはそこではっとした。
彼女を抱きしめたいと思ってしまったのだ。
昼間もそうだった。馬を自在に乗りこなす彼女は生き生きとしていた。屈託なく笑い声を立てて、アルカルドに向けられた瞳には尊敬が見られた。悪い気分になるはずがなく、アルカルドも、彼女との時間を楽しんだ。
だが、馬から下ろそうとした時、右腕が悲鳴をあげた。忌まわしい記憶と共に、骨を蝕むほどの痛みと苦痛に襲われ、その後は彼女を労ってやれなかった。
しかしフィリスは文句一つ言わず、またつまらなさそうな顔もすることなく、終始穏やかな態度だった。その落ち着いた振る舞いに、アルカルドは感心し、感謝した。
今、丸まって眠る小さな子どものような彼女を見て、アルカルドは思う。
この娘は、理不尽な王命によって、ここに単身で嫁いでくるはめになったのだ。それも、長い間会っていない弟と母親のために……。
どれほど心細かったか知れず、それなのに気丈に振る舞い、笑顔を絶やさない。
いずれ離縁するとしても、ここでの二年を、寂しいものにしたくはなかった。自分がしてやれることは存分にしてやりたい。そんな気持ちが芽生えてくる。
愛することは無理でも、互いに尊敬し、尊重することはできるはずだ。アルカルドはかがみ込み、いまだ名ばかりの妻の額にそっと口づけをした。
起きた時、フィリスはひとりだった。アルカルドはすでにいない。それもそのはず、フィリスにしては寝坊をしてしまったらしい。
あの尋常ではない寒気は消えている。しかし身体が奇妙に気だるい。
理由は分かっている。アルカルドは、少しは眠れただろうか。
起きて、着替えをしようとしていると、ノックと同時にドルモア夫人と若い娘がふたり、入ってきた。
「奥様。おはようございます。洗面とお着替えをお手伝いいたします」
「ええと、その、わたしは……」
「今日から侍女をおつけいたします。こちらはクロエ。奥様のお着替えなど身の回りのお世話をさせていただきます」
淡い栗色の髪の、背が高い娘が、丁寧に頭を下げる。年齢はフィリスより少し上くらいか。唇を引き結びにこりともしないが、お辞儀の所作は美しい。フィリスは彼女に会釈し、もうひとりの小柄な娘を見た。
「あら。あなたは……」
「当家のハウスメイドです。どうしても、直接奥様にお礼を申し上げたいと」
たしかにアニカだ。頬を染め、はにかんだ様子でそこに立っている。
「奥様。あの、先日は、軟膏をありがとうございました。おかげで水仕事が本当に、本当に楽になりました」
「そうなのね」
フィリスはぱっと寝台から下りて、アニカの手を取ってみた。確かにだいぶマシになっている。
アニカに初めて会った日、ドルモアを通じて彼女に軟膏を渡してもらったのだ。こんなに早く効くとは、フィリスも嬉しくて思わずアニカの手を優しくさすった。アニカはさらに真っ赤になり、肩をすぼめる。ドルモアが、ごほんと咳払いをした。
「実はこちらのクロエはまだ経験が浅く侍女見習いだったのですが、今回、格上げいたしました。なにぶん口がかたく、浮ついたところもなく、無責任な噂話には興じないという美点がございます。心構えや教養が足りない点はありますが、奥様には、もしかしたらその方が気安く、共に学んでいくという意味でもお心強いかと思いまして」
そっけない口調だが、言葉の端々に確かな温かみを感じる。ドルモアは先日、メイドたちの陰口をフィリスが聞いてしまったことを、気にかけてくれたのかもしれない。
クロエは先程よりさらに深々と頭を下げると、しっかりとした声で言った。
「若輩者ですが、一生懸命お仕えいたします。奥様。至らない点がありましたら、どうぞ叱ってくださいませ」
「そんな。わたしこそ……」
言葉を続けることができず、フィリスは咄嗟にうつむいた。長い髪で顔を隠すようにする。
「奥様? 具合でも悪いのですか」
ドルモアに問われ、首を振った。
「いいえ。嬉しくて」
なんだか泣きそうになってしまったのだ。自分でも知らないうちに、気を張り続けていたのかもしれない。初めて目の当たりにした他人の悪意と悪口も、思った以上に堪えていたのかもしれない。
ああそれから、なんといっても、アルカルドが負ったあの傷……災い。
どのような涙も、人に見せてはならない。決して。強い感情に揺さぶられてはならないのだ。絶対に。
幼い頃から、そのように育てられた。
フィリスはひとつ息を吐き、顔をあげた。眉をひそめているドルモア夫人とクロエ、心配そうに見ているアニカに笑顔を見せる。
「こちらこそよろしくね、クロエ。ドルモア夫人も、今日も一日よろしくお願いします」
それからアニカが用意してきてくれた水で洗面をすませ、クロエにドレスを着るのを手伝ってもらった。髪もクロエが丁寧に梳かしてくれ、自分では到底できないような凝った編み込みにしてくれたのだった。
朝食室に行くと、アルカルドがいて、すでに食後のお茶を飲んでいるところだった。フィリスは寝坊を詫び、先日と同じ正面の席についた。すると、
「よく眠れなかったか?」
アルカルドがすぐにそう聞いた。
「顔色が悪い」
フィリスは慌てて首を振る。
「大丈夫です。寝坊してしまうくらいたくさん寝ました。きっと寝すぎでしょう」
「疲れが出たのでは?」
「そうだとしても、わたし、食べると元気が戻るのです。だから大丈夫です」
実際、それは本当のことだ。フィリスは今朝も、出された食事をもりもりと食べた。次第に力が戻ってくるのが実感できる。
「確かに顔色が戻ったな」
フィリスはにっこりと笑った。
「はい」
「ただし、無理はしなくてよい。ドルモアから披露目のことを聞いたかと思うが、当日は俺も側にいるし、あまり気負わなくてよい」
「ありがとうございます」
「君は努力家だとドルモアが褒めていた。言っておくが、彼女が人を褒めるのは珍しい」
フィリスは笑った。
「そうなのですね。それは、光栄です」
アルカルドは、じっとフィリスを見つめると、穏やかな口調で、
「今日、仕立て屋が来る」
と言った。
「君のものを、いろいろ揃える必要があるようだ」
フィリスはごくん、と口に入れたばかりのパンの欠片を丸呑みした。メイドたちの悪口が思い出される。
「……わたしの嫁入り道具が少ないからですね。あの、このドレスも、侯爵夫人としての体面が保てておらず申し訳ありません」
「俺はあなたの装いは好みだ」
アルカルドはそう言い切った。
「清潔で無駄がない。だが代々の侯爵家の者たちは用途に応じて相応の物を持つようにしてきた。仕立て屋は新しい侯爵夫人に最高の品を作ることを楽しみにしている。これも義務のひとつと思い、受け入れてもらえると助かる」
「分かりました。有り難くお受けいたします」
フィリスに気を使わせないように言葉を選んでくれている。アルカルドは本当に優しい。
彼は、ちっとも変わっていない―――。
「ほかにあるか?」
「え?」
「その……君は、自分からはあまり要望を言わないだろう。できる限り快適に過ごしてもらいたいのだ。ほかに欲しいものや、俺に頼みたいことは?」
フィリスは少し考え、言った。
「それなら、お願いがひとつございます」
「なんなりと叶えよう」
「旦那様……いえ、アルカルド様は、お仕事がお忙しいようですが、合間にお茶は飲まれますか」
アルカルドは一瞬ぽかんとした顔をした。
「そうだな。午後と……仕事が深夜に及んだ時は」
背後に控えていた初老の家令、オズワルド・バルローが、微笑んで頷く。
「夜半はお酒を召し上がることもありますが、お茶をお持ちすることが多いです」
「では……、そのお茶の支度を、わたしにさせていただけませんか?」
意外な申し出だったのだろう。アルカルドは軽く目を見張った。
「君が?」
「はい。バランデュールでは、お茶とお茶菓子や軽食を用意するのが日課でした。なので、もし可能なら、厨房も使わせていただけたらと……」
これにはバルローの方が驚いたような顔をした。
「厨房でございますか、奥様」
「はい。駄目でしょうか?」
「さて。当家の料理長がなんと申しますか……彼らには彼らの決まりがございまして」
それは、ドルモア夫人も言っていた。
「邪魔にならない時間帯に、ほんの半時ほどでいいのですが」
フィリスはがんばって食い下がる。なんとしても、この要望は通したい。アルカルドのために。
「問題ないのではないか?」
アルカルドがバルローに言った。
「できるだけ彼女の要望を叶えてやりたい。そのように料理長に伝えよ」
「……は。畏まりました」
「あ、ありがとうございます」
フィリスはほっとし、三つ目のペストリーに手を伸ばした。
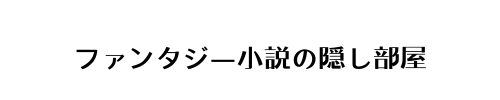


コメント