猫を愛し、その死を哀しみ、長く苦しむすべての人へ。
彼らは九生を生きる。毛皮を着替え、あなたのもとに帰ってくる……子がいるとしたら。
第二話 田中有紗の事情
頼子が現在住んでいるのは、千葉県佐倉市である。
佐倉の歴史は古い。鎌倉時代から戦国、安土桃山時代と、房総を代表する武家である千葉氏が支配し、江戸時代には土井利勝が佐倉城を築いた。以降は江戸の東の要衝として、有力な譜代大名が領主となり、城下町が整備された。江戸時代後半には、蘭学を奨励し順天堂を開いたことで有名な堀田正睦が城主となった。
頼子が暮らす古民家は、市内でも城下町の趣を色濃く残す海隣寺町にある。近隣には国や県の指定文化財となっている三棟の武家屋敷があり、広大な佐倉城址公園や国立歴史博物館も徒歩圏内だ。
込み入った路地の奥、うっそうとした竹林に隣接したこの家に越してきたのは、一年ほど前のことである。
縁もゆかりもない、とある老婆から、驚きの仕事を紹介され、その見返りとして、この家に住むことが許された。いわば、好条件の福利厚生のようなものだ。
月夜の晩に不思議な来客を出迎える古民家は、パンのもととなる酵母液のみならず、こねた生地の発酵も比較的早い。
早朝、材料をあわせてこね合わせた白い生地は、三時間後、すでに二倍以上に膨らんでいる。今は秋だから、普通なら半日はかかるものだ。
これをパンチングして、いったん、ガスを抜く。
生地はみるみるしぼんでしまう。しかし、内側に力を蓄えたままだ。
スケッパーを使い、生地を台の上に出す。半分に分割して、丸める。ベンチタイムも短い。ものの五分で、それぞれが十分な大きさを取り戻す。
打ち粉を振って、綿棒で伸ばす。
ここに、クリーム状に練ったバターと砂糖、シナモンを塗りつける。乾煎りして粗みじん切りにしたくるみをちらし、くるくると手前から巻く。再びスケッパーで切り分ける。渦巻き状の生地は、全部で九個。四角い型にバターを塗り、そこに丁寧に詰めてゆく。
二次発酵にかかる時間は、やはり短く、十分前後。生地が早く発酵するのは時短になっていいのだが、ぼんやりすることも多い頼子は、時々過発酵にさせすぎてしまい、失敗したこともある。
パン生地の方から、次の工程を急かされている感じだ。
それも仕方がない。
パン生地は生きている。酵母も生きている。力を蓄え、人や動物に作用する。
十分に発酵した生地が、互いにくっつき、型の中で窮屈そうにしている。それを、予熱を終えたオーブンに入れ、ほっと一息つく。
焼き上がる時間だけは、通常のパン作りと同じだ。
180°で三十分。
その間、頼子は自分のためにコーヒーを淹れる。
注ぎ口が細くて絶妙なカーブがいい、お気に入りの赤い電気ケトル。あっという間に湯が湧く。ガラス製のサーバーに紙フィルターをセットして、粉を計って入れ、湯を注ぐ。
無心になる。
普段遣いの粉引きのカップに、コーヒーを注ぎ、飲む。
ぼんやりする。
時刻は朝の八時。台所はほのかに暗いが、広縁と座敷には、朝の柔らかな光が満ちている。
差し込んでくる光の筋に、埃が舞っている。
掃除しなくちゃ。
でも今日は、出かけるから、明日でいいか。
焼き上がったのはシナモンロール。粗熱が取れたら純白の粉砂糖を水でといてアイシングし、箱に入れる。
藍染のエプロンを外し、座敷奥の、寝室にしている八畳間で、身支度を整える。前任者が使っていたらしい古い鏡台の前に座り、髪にさっと櫛を入れた。
頼子は、身長百七二センチと、大柄だ。一重で切れ長の目。太く、きっぱりとした印象を与える眉。真一文字に結んだ口。髪は短く、月に一度千円カットで整えている。首は長い。腕も長い。胸はぺたんこで、尻にも肉はついていない。つまり容姿はそっけない。時々、男に間違われる。
中学生の頃まで、とある理由で、ずっと髪を伸ばしていた。腰まで届く黒髪は、結んでいても、周囲に奇異な印象を与えたらしい。
「権藤はお化け」そう言われたこともある。
髪を切ったのは二十歳の時。それ以来ずっと、この髪型だ。シャンプーが楽だし、パン生地をこねるときも気を使わずにすむので合理的である。
杢グレーのパーカーに、意図せずダメージがすすんでいるデニムをはく。化粧はしない。装飾品は、小さなジルコニアのピアスだけ。
土間に戻ると年季の入ったコンバースを履いて、シナモンロールを詰めた箱を手に、外に出た。
良く晴れた日だ。クヌギの大木が葉を散らし、秋の深まりを感じさせる匂いがした。地面には落ち葉とドングリが降り積もっている。それらを踏み鳴らしながら、軽トラックに乗り込んだ。かなり年季が入っているこの車も、福利厚生のひとつなのである。
調査対象の人物の名は、田中有紗。小次郎は、有紗は十四歳だと言ったが、今は十六歳である。彼らが最後に別れてから、二年の歳月が経っていた。
佐倉市西ユーカリが丘へと向かう。比較的新しい住宅街だ。市をまたぐ案件は今のところ発生していない。この仕事は市内限定で、非常に地域色が濃いものだ。
軽トラックで国道296線を走り、ユーカリが丘駅から西へ、巨大ショッピングセンターを通り過ぎ、住宅街に入る。いったん路肩に寄せ、スマホアプリで地図を確認した。
深夜にやってくる客たちは、自分が住んでいた住所を言えるわけではない。したがって、この超個人情報を調べる必要が生じるが、それは別の人物が担当している。
頼子は調査に入る日にパンを焼き、あらかじめ送られてきた地図を頼りに現地に向かう。それを月に一度、行っている。
今回は、似たような住宅が多いので少し迷ったものの、アプリのおかげで無事にたどり着くことができた。車を塀に寄せて止め、箱を手に下りる。門扉の横の表札を再度確認し、インターホンを押す。手前の植栽スペースには、ピンクのコスモスが見事な株となって咲いている。
しばらくして、女性の声が聞こえた。
「はい」
「田中有紗さんいらっしゃいますか」
「……どちら様でしょう」
「権藤頼子と申します」
応対してくれているのは、母親か。普通なら、面識がまったくない頼子は不審者になるだろう。
しかし、次の言葉は圧倒的な力を持つ。
「事前調査にまいりました。田中小次郎さんの代理人です」
だいたい、五秒くらい。五、四、三……。
「お入りください」
許可を得て、門扉の取っ手を回して敷地内に入る。招き入れたのは彼らだ。もう、頼子を追い返すことはできない。
ここから粛々と業務を行う。
屋内から足音が響いて、玄関ドアが勢いよく開いた。そこに立っていたのは、可愛らしい顔立ちの若い女の子。
「……小次郎の?」
彼女が、田中有紗その人だ。
今日は日曜日だ。そのためか、家の中には彼女の母親のみならず、父親、そしておそらく弟だろう、十歳くらいの少年もいた。
全員が、少しぼんやりした顔で頼子を見て、曖昧な微笑みを浮かべ会釈した。
頼子も会釈し、有紗の案内で二階に上がる。
彼女の部屋に通され、ベッドの横にあわてて出された座布団に腰をおろした。
「あの……いったいどういうことなんですか」
ごく当たり前の疑問を口にする彼女は、いたって健康そうな女子に見える。引きこもりで歴史と漫画オタクだと聞いていたが、真逆の印象ではないか。髪は明るい栗色に染め、ベビーピンクのシャギーニットに短いデニムスカート。メイクも上手で、まつげがくるんとしている。
「お出かけになるところでしたか」
いったん、質問を流し、逆に訊いた。
「あ、はい。友達と約束していて……」
「十五分くらいなら大丈夫ですか」
「大丈夫です」
友達と約束。
小次郎。君は毛皮を着替えなくてもいいかもしれない。
「あの、それで……」
「まずはこちらをお召し上がりください」
頼子は箱を、目の前の小さなガラステーブルに置いた。ケーキ屋がよく使う箱と同じものだ。蓋を開くと、ふわんと甘い香りが広がった。
「シナモンロール?」
「甘いものがお好きだと聞きました」
「……小次郎が?」
「はい。召し上がってみてください。それから、お話を伺います」
そう。頼子は質問される側ではなく、する側なのだ。対象者が、今現在、どのように暮らしているか。
スマホを取り出す。メモ機能を利用する。スマホは心の友だ。心強い存在だ。マップやゲームのアプリは特に重宝している。
有紗はおずおずと手を伸ばし、シナモンロールをひとつ取った。頼子は彼女の前に、さっと持参した紙ナフキンを置く。
ひとくちパンを食べた有紗は、昨夜の小次郎と同じ表情をした。
「……わあ。美味しい」
それから続けてもぐもぐとひとつを食べ終え、軽く息を吐く。普通なら飲み物の心配をするところだが、頼子の目的は彼女と朝食やお茶をいただくことではない。
「では、小次郎さんのことを聞かせてください」
有紗は小さく頷いて、話し始めた。
―――田中有紗の話
ゴミ袋から救出したんです。まだ目も開かず、へその緒もついていました。
あたしが小学校四年の時だから、もう六年前の話ですね。
両親は、猫を飼うことに反対しました。動物が嫌いで、特に猫は、壁や家具で爪とぎをするから嫌だって。でも、あたしがしつこく頼んだので、しぶしぶ折れてくれたような感じです。
母は、それであたしの気が紛れるなら、ということで許可したんだと思います。
あたしはすでに、週の半分くらいしか、学校に通えていませんでした。
思えば幼稚園の頃から、なんとなく、人との距離の取り方が分からなかったんです。
ちょっと仲良くなると、もう親友みたいに勝手に思ってしまい、相手に期待しすぎてしまうところがありました。
でも向こうはそうじゃない。それが苦しくて、束縛したり、すねて嫌な態度を取ってしまい、嫌われて……気づいたらひとり。そういうことの繰り返しでした。
小学校の四年くらいで、教室で完全に孤立しました。陰口を言われ、ものを隠されたり、バイキン扱いされたりと、その内容はエスカレートしましたね。
誰にも相談できなかった。
あたし、プライドだけは馬鹿みたいに高かったんです。可哀想な子って、思われたくなかった。特に両親には。
それで、なかなか学校に行けなくなってしまって。でもあたしには、小次郎がいてくれました。
小次郎は、あたしに、学校に行かなくていい理由を与えてくれました。子猫の世話は大変です。あたしは夜中も二時間とか、三時間おきに起きて、ミルクをあげたんです。排泄のお手伝いも必要だし、すぐに便秘になったり、逆にお腹壊したり。
猫を飼うのは初めてでしたが、猫が、あんなにも愛情深い生き物だって、飼うまで知らなかった。
小次郎は、茶トラの鍵しっぽで、右前足だけが白い、とにかくかわいい子でした。あたしをお母さんだと思っていたのかもしれない。夜は当たり前の顔をして布団に入ってきて、腕枕で眠るんです。あたしが日中も自分の部屋にいるせいか、あの子もほとんどを、二階で過ごしていましたね。ほら、そこの窓から外を見るのが日課でした。たまに雀やカラスに向かって、えらそうに威嚇したりなんかして。
視界の中に、いつも小次郎がいる。手を伸ばせば、あの柔らかな体に触れられる。わけもなく苦しい時ってあるじゃないですか。そんな時は、向こうもなんとなく察してくれるんですよね。柔らかなお腹に顔を埋めてしつこく匂いを嗅いだり、肉球をぷにぷにしても、ちっとも怒らない。それどころか、あたしの、眉毛を熱心に舐めてくれたりして。あれ、けっこう痛いんだけど、今にして思えば、とっても幸せなことだった。
食べ物は猫用フードのカリカリが好きで、缶詰はあまり食べなかった。水を飲む時、耳の後ろのあたりを優しく撫でてもらうのが好きでした。変わってますよね。生まれてすぐに母猫とはぐれて、人間しか見たことがなかったから、自分のことも人間だと思っていたのかもしれない。
とにかく四年間、小次郎と、そんなふうに、べったりと過ごしました。
それがあの日、突然、終わったんです―――。
「交通事故でしたか?」
沈黙が長く続いたので、頼子の方から先を促した。有紗ははっとした様子で、頷く。
「あの日。あたし、フリースクールのある日で……行くの、嫌だったんです。でも、あのままでいるのもよくないって焦りもありました。だからあの日の少し前から、週に二日はフリースクールに通うようになっていました。それで、夕方、帰宅したら……小次郎が、死んだって。弟が、うっかり自分の部屋の窓を開けっ放しにして、そこから屋根伝いに外に出てしまって、家のすぐ前の道路で、車に轢かれたんだって、聞いて」
有紗の目の縁がみるみる赤くなり、涙が溢れ出す。振り絞るような声で彼女は言った。
「お姉ちゃんごめんねって、弟は泣いて謝ってくれた。でも、弟のせいじゃない。あたしのせいです。家にいればよかった。も、もしかしたら……追いかけようとしたのかもしれない。いつも家にいるあたしがいないから。ふ、不安に思って、それで。かわいそうに。かわいそうに。あんなに人懐こい子だったのに、あんなにいつも一緒にいたのに、ひとりぼっちで死んでしまった。せめてそばにいてあげたかった。耳の後ろを撫でて名前を呼んであげたかった」
有紗はとうとう顔を覆って泣いた。
しばらくの間、頼子も正座したまま、彼女の嗚咽を聞いていた。
かけてあげたい言葉はたくさんある。
誰のせいでもないし、彼もそんなことは思っていないよ。
でも、その言葉を彼女に伝えるのは頼子ではない。むしろ、言葉は必要ないのだ。
彼が、ここに戻ってくることさえできれば。
ベッドサイドのテーブルには、目覚まし時計と一緒に写真立てが飾ってある。今よりあどけない顔つきの有紗が、満面の笑みで、太った茶トラ猫を抱きかかえている。猫は少し迷惑そうに目を細めつつ、手足を弛緩させた状態で、有紗に体を預けている。
「なるほどお話よくわかりました。でも、有紗さんは、今現在はいい感じの日常を過ごされているのでは?」
有紗は顔をあげ、鼻を噛んだ。目元をごしごしと手でこする。せっかく上手に塗れていたマスカラが悲惨なことになってしまった。
「……小次郎のおかげだと思います。あたし、小次郎がいなくなって、たくさん泣いたんですけど、少しして、考えたんです。あの子は、すごかったなあって。ただ、当たり前にそこにいてくれた。時折要求がしつこい時もあったけど、そんなのは甘えの一種で、あの子はわかっていたんです。自分は存在するだけでいいんだって。だから。あたしもそうなりたいって思った。誰かを追いかけたり、強く期待したり、勝手にがっかりしないようにしよう。ただ、あたしとして存在して、いつも同じでいようって。ひとりぼっちでもいいから、せめて、しゃんと首を伸ばして、立ち続けていようって。それで、気づいたら、学校に行けるようになっていました」
「それで、友人もできたのですね」
「はい。あまり多くはないですけど」
「ではもう、寂しくはありませんね」
これは大事な質問だ。有紗は少し黙った後、顔をくしゃりと歪ませて、笑った。
「―――はい」
「承知しました。これで調査は終わりです。では、失礼いたします」
頼子は腰をあげる。
「あ、残りはご家族と召し上がってください」
「……ありがとうございます」
なにか腑に落ちない様子で、有紗がこちらを見上げてくる。まあ、当たり前の反応だ。
「では、お邪魔しました」
部屋を出ると、廊下に、有紗の弟がいた。壁によりかかり、難しい顔をしている。頼子を見ても、何も言わなかった。頼子は彼の前を通り抜け、階段を降り、玄関に向かう。
そのまま、外に出た。軽トラックに乗り込み、エンジンをかける。国道に出る頃には、明日はなんのパンを焼こうかと考え始めていた。
月がのぼった。見事な満月、中秋の名月だ。
しかし用意するのは月見団子ではない。オーブンが焼き上がりを知らせ、トレーを中から引き出す。しばらくして、湿った足音が聞こえてきたと思ったら。裏庭に通じる戸の向こうから声がした。
「ごめんください」
「どちら様ですか?」
「田中小次郎です」
「どうぞ」
からりと戸が開いて、影が忍び込み、目の前に人型の小次郎が現れた。三日前と同じ装いだ。金魚柄のシャツ。頼子は気づいていた。有紗の部屋に同じ柄のクッションがあった。
「おお。今日も、ぱんですか」
「毎日パンですよ」
漬物や、味噌ではない。もちろん冷蔵庫の中にはあるけれど。
それでも小次郎はパンが気に入ったのか、今日は躊躇なく手を伸ばし、食べ始める。
「はむはむ。むー、今日のも美味しいですね。なんですかこれは」
「リュスティックといいます。先日のものとは、材料が違います」
リュスティックに使うのは強力粉ではなく、準強力粉。こちらは国産ではなく、フランス産のものが使いやすい。ライ麦粉を一割ほど加えるのが、頼子のレシピだ。成形は丸ではなく、スケッパーで三角になるように切り分ける。クープと呼ばれる切れ目を入れ、そこに細長く切ったバターを載せて焼き上げる。
フランスパンとバターロールのいいとこどりをしたような、味わい深いパンなのだ。
ひとつを食べ終えた小太郎は、そわそわした様子で頼子を見た。
「それで、どうでしたか。有紗は」
「健やかにお過ごしでした」
頼子は見たままを伝える。ここで気を使うのは、違う。
「彼女、今はもう十六歳ですよ」
「えっ」
これには小太郎も驚いた様子だ。
「じゅ、十六? ええ、二十年も時が経って……」
どういう計算だ。
「二年ですね。あなたが家の前の道路で車に轢かれてお亡くなりになってから、二年」
「二年……そんなに」
「まあ二十年よりはいいですよ」
小次郎は呆然としたまま、二つ目のリュスティックに手をのばす。食べるのか。
「二年も、僕はいったいなにをしていたんでしょう。もっと早くここに来るべきだった」
「……早い方ですよ」
なにしろ、頼子が待っている子は、いっこうにやってこない。
もう五年も経つというのに。
いや……そもそも、毛皮を着替える機会が得られる子は、それほど多くはないのだ。いったいなにが判断基準なのか分からないが、神さまという存在がいるとして、彼がどういうふうに個体を選んでいるのかわからない。
「それでですね、有紗さんは元気です」
「本当ですか」
「綺麗でしたよ。美人さんです」
「そうでしょう、そうでしょう。いい匂いもしましたか」
「……匂いまではちょっと。まあ、でも、とにかく人生を謳歌しているようです。学校にも通っていて」
「学校に!」
「友達もできて。わたしが訪ねた日は、そのお友達と遊びに行く予定だったみたいです」
「そうなんだ。わあ、そうなんだあ、有紗。うふふ」
小次郎は嬉しそうだ。
彼らはいつもそうだ。もと飼い主の幸福を、我がことのように喜ぶ。
そして頼子は、そんな彼らに言わなければならない。
「幸福そうでした。あなたがいなくても」
小次郎は大きく目を見張った。ああ、なんて綺麗な金色だろう。人間の姿をして、髪はどこかのくたびれたサラリーマンのようにぺったりしていても、瞳だけは美しい金色のまま。
「寂しがっていませんでしたか」
「寂しくないですかって聞いたら、はいと答えました」
「そうですかあ……」
小次郎は三個目のパンは取らなかった。ただ、静かにうつむいている。
「それで。どうしますか。毛皮、着替えますか」
それとも。
「……あちらの戸から、お帰りになりますか」
裏庭に通じる戸から。
「僕が決めてもいいんですか? 確か、これは審査で、着替えを許可できない場合があるって」
「先方が、明らかに新たに猫を飼う状況にない時には、問答無用で。でも、今回は、小次郎さん次第でもあるかなと」
なにしろ彼らが着替えるのは、彼ら自身の恩返しのためだ。この恩返しの定義は、個体によって異なる。
「ゴクドウさん」
「権藤です」
「ゴンちゃん」
もうなんでもいいや。
「はい」
「有紗、こんな笑顔で、寂しくないって言いませんでしたか」
小次郎は、鼻の頭に皺を寄せて、顔をくしゃりとさせた。頼子は驚いた。
「ああ、たしかに。似てます、その顔」
「やっぱり」
「やっぱり?」
「有紗、我慢強い子なんです。でも我慢して笑う時、こんな顔をするんです。あなたが見た通り、有紗は今、幸せなんでしょう。僕がいなくたって、ちゃんと立派に、前に歩きだしているんでしょう。でももともと、頑張りすぎるし、寂しがり屋なんです。あなた言ったじゃないですか。パンは寂しがり屋だって」
話のつながりが謎だが、なんとなく言わんとすることはわかる。
「まあ、寂しがり屋なのはパンじゃなくて、酵母なんですけど。それで?」
「知ってますか? 一年って、三六五日もあるんですよ」
「……ええ、知っています」
「三六五日のうち、一日くらいは、ああ寂しいなあ、辛いなあって、思う日があるかもしれない。ないかもしれないけど、あるかもしれない。僕のお腹に顔をうずめたり、耳の後ろあたりのにおいをしつこく嗅ぎたくなるかもしれない。ねえ、ゴンちゃん。酵母が、たったいちにち、寂しさをどうしようもできなくなったら、どうなりますか」
頼子は考えた。
「その酵母、だめになるかもしれませんね。パンは焼けるかもしれないけど、膨らみが悪くなるかも」
「ほらね、だから、そういうことです」
「どういうことですって?」
小次郎はじっと頼子を見た。瞬きもせず。神々しささえ、感じさせる、宝石のような眼差しで。
「たとえ一日でも。有紗が寂しいと感じるかもしれない日のために。僕、毛皮を着替えますよ」
頼子はごくん、と唾を飲み込んだ。そういうことならば、頼子が言うべき言葉は決まっている。
「たとえ生まれ変わっても。先方は、あなたが小次郎さんだとわからないかもしれないです。むしろ、まったく別の猫として見る可能性が高い」
なにしろ、毛皮を着替えるのだから。同じ柄に生まれ変わることはできないと、決まっているのだから。
「大丈夫です。だって有紗は変わらないもの」
うふふ、と嬉しそうに笑う小次郎。頼子はその笑みにつられて、微かに口元を緩ませた。両手をぎゅっと胸の前で組み、息を吸って、吐いてから―――。
「分かりました。田中小次郎さん。あなたの着替えを、許可いたします」
その瞬間。部屋に淡い光が満ちた。
朝の光とも、昼の光とも違う。
満月の、清らかで静かな、それでいて強烈な光が。
眩しくて、とても目を開けてはいられない。頼子は目を閉じ、そして聞く。からりと、戸が開く音を。歩み去る足音を。少しして再び目を開けると、光は消え失せていた。
小次郎の姿も消えている。
戸は、開いたままだ。西側の裏庭ではなく、東に面した表玄関の方の戸だ。ふらりと立ち上がり、外に出てみる。
月の光が散らばって、静寂の中、さやさやと葉擦れの音だけが響いている。
着替えの結果を確認するのは、頼子の仕事の範疇ではない。それでも頼子は、毎度、確認せずにはいられなかった。
翌、早朝。軽トラックで国道を走り、ユーカリが丘駅から西に、住宅街の方角へ。今度は家の前に車をつけるわけにはいかない。用向きを訊ねられたら、先日と違って調査員の免罪符は効かない。そのため、近隣のコインパーキングに停めて、徒歩で移動する。服装は上下ジャージ姿。首にタオルを巻き、いかにもウォーキング中の女の演出をする。
住宅街は朝の気配に満ちている。食器が擦れ合う音や、元気に「行ってきます」と叫ぶ子どもの声。ゴミ出しついでに井戸端会議をする女性たち。犬の散歩をする老人や、登校する小学生たち。さてどうしたものか、と考えながら、田中家に向かって歩いていると。
「ぴぎぃー」
独特な、細く高い声がして、振り返った。
「あ」
そこにいたのは、田中有紗の弟だ。登校途中だったのか、ランドセルを背負っていて、両手のひらで何かを大事そうに持っている。
少年は、頼子と目が合うと、少し不可解そうに首をかしげた。もちろん、彼は頼子のことは憶えていないはず。
「どうしたの」
ごく自然に話しかけると、彼は両手を頼子の方に差し出した。
「……学校行こうとしたら。この先のゴミ捨て場で、こいつ見つけて」
手の中で小さな生き物がもにょもにょと動いている。ぴぎぃー、ぴぎぃー、と必死に鳴いている。
子猫だ。
生まれたて。目も開いていない。ぽこんと膨らんだ腹に、へその緒がついている。
「ゴミ袋に、詰められてて」
「よく気づいたね」
「声がでかいから。それに」
少年は、少し気まずそうな顔をした。
「……前にうちにいた猫も、ゴミ袋から救出したって、お姉ちゃんが言ってたから。だから俺も、ゴミ置き場の前通るときは、気にするようにしてて」
それは、かなり確率の低い話だ。それでも、彼はそうしたのだ。意識したのだ。おそらくは、その小さな胸に抱え続けていた大きな罪悪感のために。
「その猫、どうするの」
「わかんない」
と、彼は呟いた。
「連れて帰って、お姉ちゃんに見せる。そんで、できればうちで飼いたい」
「反対されない?」
「されないと思う。みんな……パパもママも、猫好きだし」
猫は飼いたくないと、反対した有紗の両親は、どうやら考えが変わったらしい。よく聞く話だ。猫は一度でも飼うと、その魅力の虜になってしまう。
彼らは人間の心の奥の奥まで侵食し、当たり前の顔をして居座り、眼差しひとつで言うことをきかせ、愛を欲しいままにする。
それでも少年が一抹の不安を口にするのは、肝心の姉が、有紗が、この子を受け入れるかどうか、ということだろう。
「大丈夫だよ、きっと」
「そうかな」
「うん」
頼子は、少年の手の中の子猫を見つめる。
茶トラではない。
黒と白の、ハチワレだ。
それでも頼子には、すぐに分かった。
おめでとう―――小次郎。
子猫特有の生命力と、破壊的な可愛らしさを有している。その愛おしさを知っている人間は、決して退けることはできない。
頼子は田中家に行くのをやめて、少年と別れた。
田中小次郎の着替えは、このようにして、無事に終了した。
※この物語はフィクションです。猫にパンその他人間の食べ物を不用意に与えてはなりません。塩分、糖分、アレルギー物質により健康被害、命の危険があります。そのため作中ではパンを食べるのは人間の姿の時のみとしています。
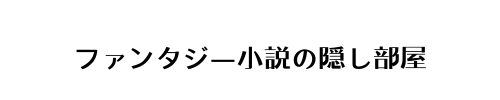


コメント