新しい毛皮を着て大事な人のところへ戻りたい。情念にも似た猫のひたむきな愛。でも、もとの世界は容赦なく時間が流れていて、飼い主は……。
第三話 小川のしま子
猫は九生を生きるという。つまり、八回、生まれ変わるということだ。
生まれ変わる度に、毛皮を着替えるという。
茶トラがハチワレになったり、サビ猫になったり、あるいは三毛猫になったり。
権堂頼子は千葉県佐倉市で、そんな猫たちの「着替えどころ」を営んでいる。
営んでいるとはいえ、雇われである。
実はこの「着替えどころ」となっている古民家は、佐倉市の所有だ。そして頼子は、半年前から、市の属託職員ということで、給料を得ている。
頼子自身は、佐倉市の出身ではない。
生まれは東京北区。2DKのアパートで両親と頼子の三人家族で暮らした。この頃は、それなりに幸せだったように思う。しかし八歳の時、父が事故で亡くなった。しばらくの間、母子で暮らしていたが、十歳の時、母が再婚した。さまざまな事情があり、頼子は父方の祖母と住むことになり、佐倉市に越してきたというわけだ。
不思議な土地だと、当初から思っていた。
成田よりは都心に近く、京成線や東葉高速鉄道を使って都内に通勤通学する者も多い。それでいて、少し主要な駅から外れるととたんに田園風景が広がり、印旛沼や、オランダ風車がそびえ立つふるさと広場もある。
この地に越してきてから、十七年。頼子はただの一度も、佐倉市から出ていない。
さて本日焼くのは、酒粕酵母を使った食パンだ。
頼子はこの家で、さまざまな種類の酵母を仕込んでいる。発酵の状態がよく、安定した出来栄えのパンになるのは、やはりレーズン酵母だろう。しかし葡萄やレーズンは、本来、猫にとっては毒になる。
この家に着替えに現れる彼らはすでに亡くなっていて、人型をとっていることから、基本的にはどんな食材を出してもいいとされている。それでも頼子は抵抗を感じ、レーズン酵母は使わない。
酒粕酵母は、パンとして焼成すればアルコール分はなくなる。この酵母を使用したパンは、風味がチーズに似ていて、食感はしっとり、とても美味しい。ただ、劣化が早く、取り扱いに気を使う。
パンに使う酵母種は、酵母液に強力粉やライ麦粉を混ぜて少しずつ発酵させたもの。しかし酒粕酵母だけは、その工程を短縮し、前種と呼ばれる状態で使う方が、風味が活きる。
前種の場合、一次発酵に時間がかかる。いくらこの家が発酵を促す環境であったとしても、最低六時間は見た方が良い。
九州産強力粉「南の香り」を使う。酒粕酵母、きび砂糖、赤穂の塩、豆乳、水を混ぜ込んで、こねる。こねる。こねる。
三十分放置。
ぼんやりする。
スケッパーで生地をいったん取り出し、こねる、こねる。バター三十グラム投入。こねる。こねる。
ラップをかけ、一次発酵開始。
テーブルの隅っこで、朝食をとる。今朝は、先週焼いて冷凍しておいたイングリッシュマフィン。解凍し、半分に切った片方に目玉焼き、ハム、チーズ、レタスを乗せる。もう片方には、糀と豆乳で手作りした発酵バターと蜂蜜をたっぷりと塗る。それから、カフェオレ。濃いめに淹れたコーヒーに、ミルクをしっかりクリーマーで泡立てて注ぐ。
我ながら、最高の朝食である。
その後は歯を磨き、髪を手櫛でさっと整え、身支度五分で終了。最後に作業台の上に置いたパン生地に挨拶をする。
「じゃ、仕事に行ってくるね」
おりこうにして、大きくなるんだよ。
着替えを請け負う猫は、月に一匹か、多くで二匹。市から払われる給料だけでは、生活はできない。家賃と光熱費がかからないのはいいが、暮らすにはお金がいる。食費にスマホ代。交際費や被服費はほぼ必要ないとして、それでも。だから頼子は、市民病院で清掃のアルバイトもしている。十九歳の頃から続けている仕事だ。以前は夜間のシフトだったのを、着替えどころとの兼業のため、昼間、週四、五日に変えてもらった。朝七時から午後三時まで。海隣寺町の古民家からは自転車で二十分ほどと、距離もちょうどいい。
軽トラックは市の所有物。だから、調査目的以外ではできるだけ使用しない。普段はここ十年愛用している自転車で移動している。どんなに大雨の日でもだ。
仕事から帰宅したのは午後三時半。空を見上げる。満月まであと三日。不完全な形の白い月が確認できる。
土間に入ると、いつものように古民家特有の清涼な香りに、パン生地のいいにおいがした。
いつも、帰宅するたびに、ほっとする。
東向きに建てられている家の中は、すでに薄暗い。しんと静まった空間は、頼子が留守のあいだも、ゆっくりと時が流れているのだ。
テーブルの上、ボウルの中の生地はみちっとラップを突き上げる勢いで発酵している。手を念入りに洗い、すぐに作業再開。
粉を振った台にスケッパーで生地を取り出し、三分割。いちいち計らないが、大体同じ大きさ。ベンチタイムのあいだ、スマホのゲームアプリにログインする。
生地が力を取り戻したのを確認後、成形、バターをたっぷり塗った型に入れる。二次発酵を待つ間、軽く掃除と、風呂の準備。それから、自分の夕飯作り。
今夜は、味噌漬けにしておいた豚ロース肉のソテー。自家製キャベツのザワークラウト。オクラと梅肉の和物。大根の味噌汁。
生地をオーブンに入れ、約三十分。
ゲームの続きをしながら、テーブルの端で食事。奇怪な猫の軍団が理不尽に人の城に攻め込むゲーム。食事中なのに、と眉をひそめる者は誰もない。ちなみに、テレビは置いていない。固定電話もない。ここに越してきた時からそれらはなかった。
祖母亡きあと、頼子はひとりの生活を謳歌している。安普請のアパートであろうと、おんぼろの借家であろうと、敷地面積が無駄に広い古民家であろうと、生活リズムはあまり変わらない。
パンも、以前から焼いていた。自家製酵母でパンを焼くようになったのは、祖母の影響だ。祖母はそれこそ、自慢のぬか床を持っていて、味噌も仕込むような発酵食の達人だった。基本的に食いしん坊だった祖母は、お気に入りのパン屋があったのだが、そこの食パンがよく売り切れていることを不満に思っていた。何度か買いに行くたびに振られ、それならいっそ、と図書館でパンのレシピ本を借りてきて、焼いてくれた。
祖母の手作りの食パンは、少し膨らみは悪かったが、もっちりとして、風味が豊かで、味わいがあり、とてつもなく美味だった。
祖母が台所に立てなくなってからは、食事作りは頼子の仕事となった。必然、自家製酵母のパン作りも引き継いで、今に至るほどの腕前を身に着けたというわけだ。
そして祖母亡き後、頼子はしばらく、自分ひとりだけのためにパンを焼き続けた。
「ごめんください」
深夜零時少しすぎ、玄関土間兼台所の、裏庭側の戸口向こうで、声がする。
「どちらさまですか」
「……小川、しま子」
まだ幼い少女の声だ。
「どうぞ、お入りください」
返事をすると、戸が、からりと開く。大きな影がにゅっと忍び込んできて、目の前に、五、六歳くらいの女の子が立った。
顎の線で切りそろえた黒髪。前髪もぱっつん。グレーのブラウスにウールっぽい厚地のプラム色のスカート。黒とグレーのボーダー柄のタイツに、もこもこの折返しがある黒いブーツをあわせている。
彼らにしては、なかなかおしゃれな方ではないだろうか。もっとも頼子自身、おしゃれという定義がよくわからないけれど。
大きなアーモンド型の瞳。すべてのパーツが顔の真ん中にぎゅっと寄っていて、好ましい顔立ちをしている。
招かれれば、堂々と入ることができる。
彼女はじっと頼子を見つめて、
「こんばんは」
と、可憐な声で挨拶をした。
「こんばんは。わたしは、権堂頼子といいます」
「ヨルに生まれたからそんな名前なの?」
くすくすくす、と少女は笑う。
先月やって来た茶トラの小次郎のように、名字を勘違いされたことはあるが、下の名前をいじられるのは初めてだ。
それも、ヨル―――その言葉は、頼子にとって特別なもの。胸に痛みが走って、少し無言になってしまったけれど、静かに否定した。
「いえ、生まれた時間は知りません」
「ふうん? あたしはシマシマだからよ。ほら、これと一緒」
彼女はスカートをほんの少し持ち上げて、縞模様のタイツをよく見せようとする。
サバトラか、アメショーの子かな。
そんなことを考えた。
頼子は、背が小さいしま子を、囲炉裏端に案内しようとした。しかし、彼女はダイニングテーブルのところに置いてある椅子のところまで行き、そこに腰掛けてしまう。その時、おや、と気づいた。左足を少し引きずっている。椅子の方が楽なのかもしれない。
案の定、大人用の椅子は彼女には大きすぎる。それでも、すました様子で
「お水ください」
と注文した。
「白湯じゃなくて、水でいいですか?」
「水が好きよ。冷たすぎなければ」
はいはい。言われた通り、水道の蛇口からグラスに水を注ぐ。佐倉市は水道水も普通に美味しい。なんでも五十%以上は地下水だという。頼子も都内から越してきて、まず水の美味しさに驚いた記憶がある。
グラスを手に、振り返った頼子は目を見張った。
しま子が、すでにパンを食べているではないか。テーブルの網の上、冷ましていた食パンを。まだカットもしていない。
「あの、しま子さん」
「美味しい! ヨルヨル、お店開けるよ、これ」
誰がヨルヨルだ。
「勝手に食べだすなんて、お行儀悪いですよ」
「味見だもん、あ、じ、み」
ぺろりと舌を出す。
しま子は食パンの端っこを強引にむしり取って食べてしまっていた。
頼子は嘆息し、パン切り包丁を出すと、味見の被害に遭った端っこを切り落とす。それから八枚切りくらいの薄さに切り分けたものを、改めて、皿に盛って出してやった。
しま子はそれも、躊躇なくぱくぱくと食べた。
「うん。深い味わい」
「パン食べたことありましたか」
「まあねー。あたしの飼い主、大らかな人だったから、人間の食べ物は時々味見をした」
「大丈夫だったんですか、それ」
「玉ねぎ入ったハンバーグ食べようとした時は怒られたけど、それ以外なら、しょうがないなあって笑ってた。優しい人だから、あの人」
猫に玉ねぎはいけない。チョコレートも、各種ハーブも。厳密に言えば、穀類の大量摂取も、バターも、卵も、生肉生魚も。だから猫である時にパンを食べたことがある子はほとんどいない。しま子はよほど食いしん坊だったようだ。
今も、むしゃむしゃと夢中で食べている。
「んまんま、ふー、ああ美味しい。んまんま」
いくら人型とはいえ、大丈夫なのだろうか。頼子の心配をよそに、彼女は結局、一斤の半分も食べてしまった。水もおかわりをして、ごくごくと飲み、ゲップをした。
「失礼」
えへへと笑って、椅子を降りると、囲炉裏のある居間に移動し、座布団の上にころんと横になる。
「しま子さん、眠いんですか」
「うん。ちょっと寝ていい?」
「だめです。お話聞かせてください」
「えー、めんどうくさい」
「だって、そのために来たんでしょう。そのために、パン食べたんでしょう」
「そうだった」
しま子は、ぴょん、と跳ねるように飛び起きる。髪の毛がちょっと乱れてしまっている。
「じゃあ、聞いて」
頼子は板の間の上り框に腰掛けた。しま子は座布団に左脚を投げ出すようにして座り、話し始める。

―――小川のしま子の話
あたしが毛皮を着替えたい理由は、おかーさんとの約束を守らなければならないからよ。
あたしはもともと、血統書付きの猫だったんだけど、二歳くらいの時、太りすぎて、目つきも可愛くないって言われて、最初の飼い主に捨てられたのね。
冬の、とても寒い夜のことだった。車に乗せられて、しばらく走って、突然、窓からぽーん、と外に放り投げられたの。
道路脇の草むらに体が打ち付けられて、たぶんあたし、気を失ったんだと思う。起きたら後ろ脚が変で、腰がまっすぐにならなくて、歩きづらかった。痛くて、寒くて、何度か吐いたの。
でもなにより、怖かった。
それまで、外の世界なんて知らなかったから。見るものすべてが怖かった。
風に揺れる草も怖いし、時々通る車の音も怖い。近くの森からフクロウの声がして、見つかったら食べられちゃうと思った。
でも、月は、不思議と怖くなかったな。
草むらの真ん中に、壊れたショベルカーが置かれてたんだけど、その下に潜り込んで何日か過ごしたの。
でも、お腹空いちゃって。上手に歩けないし、血は乾いてこびりついていたけど、頭もくらくらしちゃって。
頑張って食べ物を探し回ったの。水も飲めなかったけど、朝露を舐めてしのいだ。でもとにかく食べ物よね。なのに虫一匹、見つからなかった。いたとしても上手に取れたかわからないけど。鳥なんて、電線の上でこっちを見下ろして嘲笑ってるし。
それに、嵐まで襲ってきた。信じられないほどの風と雨。
ここにいちゃいけない。それで、思い切って道路を渡ることにしたの。怖かったし、早く走れないけど、一か八かで草むらから脱出した。
なんとか道路を渡って、そこはどうやら住宅街になっていて、明かりを目指して前に進んだ。誰かが出てきたから、必死に鳴いた。もう、残った力をすべて振り絞って、必死に鳴いたんだ。
そうしたら、温かくてやさしい手が、あたしを抱き上げてくれた。
それがおかーさんだった。小川佳代っていうの。道路沿いの、古い家に、たったひとりで住んでいた。旦那さんは随分前に亡くなって、娘がふたりいるけど、めったに帰ってこない。
おかーさんは、本当は猫が嫌いだったのよ。なんでかしらね? あたしたちほど、気高く愛情深い生き物はいないというのに。
とにかく猫は嫌いで、犬が好き。昔、犬は飼っていたことがあったけど、猫なんて考えられない。
でも、ひどい怪我をして死にかけていたあたしを、ほうっておくことはできなかったみたい。すぐに病院に連れていってくれて、治るまで面倒もみることにしたって。それで、治ったら里子に出すつもりでいたのよね。
でもほら、あたし、可愛いから。
肥って目つきが悪いとか言われて捨てられたけど、数日の野良生活のおかげですっかり痩せたし、目つきはまあ、人の感じ方はそれぞれだから。
で、おかーさん、すっかりあたしに情がうつっちゃって、一緒に住んでくれることになったのよ。
その時に、こう言われたの。
よしわかった、おまえのこと、三番目の娘だと思って育てる。
命を助けて、引き取るんだから、ご恩返しをしてくれなくちゃ駄目だよ。
おかーさんは、笑ってた。
でもね。目はぜんぜん笑っていなかった。
本気の本当に、ご恩返しを望んでいたのよ。
それであたし、そのご恩返しの約束を果たさないで死んじゃったもんだから。なんとしても、毛皮を着替えて、おかーさんのところに戻らなきゃならないの。
しま子は話し終えて、ふう疲れた、とつぶやき、再びごろりと座布団に横になった。
頼子はいくつか、訊きたいたいことがあった。
例によって黒いファイルの中を確認しつつ、訊ねる。
「しま子さんは、腎不全で亡くなったのですね」
「うんそうよ。でも、たぶん、寿命ってことでしょ」
「寿命?」
「お医者さんが言ってた。十八年も生きれば、当然あちこち悪くなるって。で、あたしの場合は、腎臓がもう使いものにならなくなって、最後は水も飲めなくなって、死んじゃった」
ファイルには、確かに、享年推定十八歳、と記されている。
その見た目からは子猫を彷彿とさせるが、彼らは実年齢に相応する姿に化けるわけではない。それでも、しま子の場合、本当に幼い少女の雰囲気がある。
「確かに十八歳なら、寿命ということなのでしょうね」
「でしょ。長生きした方でしょ」
「でも、今のしま子さんは、人間でいえばまだ五歳か、六歳くらいに見えますね」
「あー、これね。だってあたしは、おかーさんの永遠の娘だから。ある程度小さいままなのは当たり前」
「そういうものですか」
「そうだよ。あたしの見た目がおばあちゃんだったら、娘って感じじゃなくなるでしょ」
「まあ確かに」
「何度も考えたことあったから。もしもあたしがおかーさんの本当の、本物の娘なら、どんな見た目かなあって」
なるほど。それで、今の姿をしているのか。
「それで、ご恩返しっていうのは、具体的になにを?」
動物の恩返しは昔話によく出てくる。ツルは極上な布を、ネズミは金銀財宝を。では、猫は?
「ずっと一緒にいること」
よどみなく、しま子はそう答えた。
「おかーさん、寂しかったんだと思うのよ。本当の娘たちはちっとも帰ってこないし。だから、三番目の娘にするから、ずっと一緒にいてちょうだいって。それがご恩返しってものだよって。それなのに、あたし先に死んじゃって」
彼女は本当に申し訳無さそうな顔をする。
「ねえ、人間の世界じゃあ、子供が親より先に死ぬのは逆縁っていって、最大の親不孝なんでしょう?」
「確かに、そう言われてますね」
頼子の父は、祖母より先に死んだ。逆縁だ、親不孝だと、祖母が嘆いていたのを憶えている。
「あたし、恩返しどころか、親不孝しちゃったんだ。だからさ、一日でもはやく、毛皮を着替えたいの。血統書なんてついてなくていいよ。どんな柄でも贅沢言わないから。ね? お願い、ヨルヨル」
頼子は胸の中で、今聞いた話を整理する。
しま子は、十八年も長生きした。今度もそうなる可能性はある。一方で、小川佳代は七十四歳―――。
「では、今度はあなたが彼女を看取ると?」
「そのつもりよ」
「でもそうすると、あなたはまたひとりぼっちになるのでは……」
しま子は少し考えこむ様子を見せたが、すぐに、にこっと笑った。
「そんなの、全然構わない。今度こそ上手な野良生を送れるかもしれないし。とにかく一番の恩返しは、ずっと一緒にいることなんだもの」
ずっと一緒にいるのが、ご恩返し。
頼子は心の中で反芻する。
うん、わかるよ。
わたしもね。わたしも、ずっと一緒にいたかった子がいるんだ。それが叶うなら、ほかにはなにも望まない。
「わかりました。ではさっそく、明日、調査に行きまして、結果合格となりましたら、着替えを許可いたします」
「良かったあ。合格に決まってるもん。あ、それで、カタログかなんかはある?」
「カタログ?」
「次に着替える毛皮のカタログよ」
「さっき、どんな柄でもいいって……」
頼子が呆れて見つめると、金色の瞳がきろきろと輝く。
「あるの、ないの?」
「……ないです。毛皮は選べません」
「なんだ、つまんない」
しま子は、ぶつくさ言ったが、やがて大あくびをひとつすると、すうっと眠りに落ちてしまった。
どうしよう。本当は、いったん帰ってもらいたいのに。
でもこの子、実際はおばあちゃんだから。
仕方がない。頼子は押し入れから毛布を出して、囲炉裏端で眠ったしま子に、そっとかけてやった。そしてストーブは点けたまま、火を細く絞って、彼女が暖かく眠れるようにした。
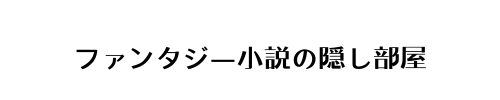


コメント