―――愛をくれる存在は、同じくらい大きな喪失をもたらす―――
第一話 田中の小次郎
満ちゆく月が、夜半過ぎ、西の空に傾き始める時刻。裏庭の草を踏みしめる、湿った足音が近づいてくる。
足音には個体差があって、今夜の音は大きく、それなりの重量を感じるものだ。
頼子はオーブンを確認する。残り五分で焼き上がる。ちょうどいい頃合いである。
背筋を伸ばし、裏庭に面した弁柄塗りの千本格子の引き戸を、じっと見つめていると。
「ごめんください」
ひそやかな声が、戸の向こう側からした。
「どちら様ですか」
本当は、相手が誰であるのか、もう分かっている。でも万が一にも間違いがあってはならない。
「田中小次郎と申します」
頼子は手元の黒いファイルに視線を落とし、その名前が確かにあることを確認した。
「田中さんですね。どうぞ」
ほどなくして、戸がからりと音を立てて開いた。そこには誰の姿もない。ただ、明らかに人ではない形の大きな黒い影が、淡い月光を受け、所在なさそうに揺らめいている。
「どうぞ、中にお入りください」
再度許可を与えると、影はゆらりと中に入ってきた。夜の湿った空気の匂いがして、影は、目の前で人間の姿になった。
頼子はいつも、この瞬間、妙に感心してしまう。
人間に化けることができるのは、たぬきや狐だけではないのだ。
今夜、やってきたのは、肥った中年男性である。主張の激しい金魚柄のシャツに、縞模様のズボンを、水玉模様のサスペンダーで吊っている。
彼らはたいてい、独特なファッションセンスをしている。
「どうも、初めまして」
彼は丁寧にお辞儀をした。すぐに顔をあげると、はらりと落ちた前髪を邪魔くさそうに手で払う。ずり落ちたメガネを直し、その奥の目をきろきろと光らせた。中年と思ったが、よく見ると、肌艶がやたらと良い。皺ひとつない。
頼子も軽くお辞儀をする。
「初めまして。権藤です」
「ゴクドウさん?」
「ごんどう、です。権藤頼子」
小次郎はひとつ、頷いた。
「ゴンちゃんって呼ばれるのと、ヨリちゃんって呼ばれるの、どっちがいい?」
「……できれば、ただ権藤、と」
「顔が怖いって言われない?」
「言われます」
「でも、気は優しくて力持ち。そうなんでしょ」
「特別優しくはないです。力は、まあ……そこそこ」
「わあ、いっしょだ」
「なにがです?」
「僕もなんです。顔は怖く、気は優しく、力持ち」
「はあ」
会話がちぐはぐだが、よくあることだ。小次郎は好奇心旺盛に質問を重ねる。
「歳は、何歳なの?」
「二十七歳です」
「ずいぶんと長生きだねえ」
「そうですか?」
「あ、間違えた。ええと……」
小次郎は太い指を折っては戻し、また折る。
「ああ。僕と同じくらいってことですね」
頼子は曖昧に頷き、彼を、ダイニングテーブルに着くように促した。小次郎はよいしょ、と木製の椅子に腰掛け、きょろきょろと家の中の観察を始める。
築百五十年の、古い日本家屋である。玄関兼台所の広い土間は吹き抜けで、太い四本の柱と、漆喰で固められた葦で葺かれた天井が見えている。土間には、骨董的価値のありそうな大きな竈もあるが、機能的なステンレスの作業台とIHコンロ、オーブンレンジ、冷蔵庫が設えられている。大きなダイニングテーブルは昔の蔵の戸を再利用したもの。土間から三和土を上がると囲炉裏を備えた居間があり、天井から下がる四本組の木枠には、魚を模した真鍮製の鈎がぶら下がっている。
奥には、続きの和室が三部屋ほど。どの部屋の畳も新しいし、障子や襖も張り替えてある。敷地は広く、前庭には池があり、立派なクヌギの木がある。通り土間と広縁で囲われた建物は大きく、焦げ茶色の梁は太い。
時刻は深夜。雨戸の一部はまだ閉めていない。月明かりが広縁の障子戸から差し込み、奥の部屋に漂う闇はいっそう濃く、不思議な陰影と広がりをもたらしている。
程よく調湿された空気が循環し、古い木材が醸し出す独特な香りが漂っている。それからーーー。
田中小次郎はうっとりとした顔をして、鼻をひくひくとさせた。
「なんだかいい匂いがするみたいだけど」
「パンを焼いています」
「ぱん?」
彼はかっと金色の瞳を見開いた。
「きみ、僕が……いや、僕たちが、パンを食べると思っているのかい」
「なんでも食べるって聞いてます。少なくとも、その姿でいるときは」
「僕が聞いたのは、ここに来ると、漬物を出されるって」
「漬物は、今は出していません」
実は、漬物を出してもらえると思ってやってくる客は割といる。どこでどんなふうに情報が回っているのだろうか。
「いやしかし、ぱん……パンかあ。ふむ。食べたことないけど、美味しいのかな」
「じゃあ漬物は食べたことあるんですか」
「いやないよ」
「お米とか」
「ううん。いつもは、カリカリとか、たまにぺちゃぺちゃとか、パタパタとか」
頼子と小次郎は、じっとお互いの顔を見つめる。どちらも真顔だ。
パタパタって、虫のことかな。いや、雀かもしれないな。
そんなことを考えていると、チン、と高い音がした。
「ああ、焼けました。しばらくお待ち下さい」
頼子はテーブルを離れ、オーブンがあるところまで行った。蓋をあけ、ミトンを両手にしっかりはめて、熱々のトレイをいったん、ステンレスの作業台に置く。
高い天井に向かって、パンの香りがさらに広がってゆく。
「……ほんとうにパンだ」
小次郎は用心深い目つきで、じっとこちらを見ている。
焼き上がったのは、普通のまるパンだ。手のひらにすっぽり収まるくらいのサイズで、表面は卵液を塗ったためにつやつやとしている。
材料は、北海道産強力粉「春よ来い」。沖縄産きび砂糖に赤穂の塩、バター。そしてこれが肝心、自家製天然酵母。
頼子は焼き立てのパンを網の上に出し、テーブルの真ん中に置いた。
小次郎は鼻をひくひくさせていたが、ペロリと舌なめずりをする。
「うん、思っていたよりも美味しそうだね」
「美味しいですよ。いい材料を使っています」
頼子はトングでパンをひとつ木製の皿に載せ、彼の前に置いた。
「これはまだ熱いんだよね」
「熱いの苦手ですよね」
「うん。だめだねえ、僕は、熱いのは」
「少しお待ちください。小さいから、割とすぐに冷めます。よかったら、その間、聞きますよ、あなたの話」
うん、と小次郎は頷いた。そしてぽつぽつと話しだしたのだ。
―――田中の小次郎の話
僕がもう一度会わねばと思っているのは、田中有紗、十四歳の女の子です。
とても可愛い子でねえ、漫画と歴史と甘いお菓子が好きで、ちょっと運動は苦手みたいだけど、手芸が得意で、とにかく誰に対しても優しい子なんです。
でも、ちょっと優しすぎたのかもしれないな。有紗はみんなに優しいのに、有紗に優しくしてくれる人があんまりいないのです。
そりゃあ、お父さんお母さんは優しいよ。ああでも、どっちも有紗に、少し要求が多すぎるかな。
何時までに寝ろとか、好き嫌いなく食べろとか、ちゃんと友達を作りなさい、とかね。
ちゃんと友達を作るって、どうすればいいのかなって、有紗は困っていた。
両親は、ちゃんと学校に行きなさい、とも言っていたっけな。
有紗は、僕と出会った頃には、すでに、学校にあまり通えなくなっていたんですよ。
学校って場所、僕は一度も行ったことはないけど、有紗と同じ歳くらいの子がたくさん集まって、怖くて意地悪な先生という大人の話を、延々と聞かなければならない場所なんですってね。それから、とっても苦手なトビバコとかドッジボールをやらされるとも言っていた。
そういうことが、ちゃんと要領よくできない有紗は、友達に馬鹿にされることが増えて、先生も一緒になって馬鹿にしてくるもんだから、ますます学校が嫌いになったんですって。それどころか、そのうち物を隠されたり、悪口を言われたり、バイキン扱いまでされるようになって。学校に行くこと自体が、怖くて、怖くて、がんばって行こうとすると、お腹が痛くなったりするって言っていた。
お腹が痛くなる。あれは辛いよねえ。僕も何度かお腹を壊して、トイレに間に合わず布団を汚してしまったりして、最悪だったな。でもそんな時も有紗は怒らなかった。僕は、トイレだけは綺麗に使いたいタイプなんだよね。だいたいさ……ああ、話がそれてしまった。
つまり、あれです。僕と有紗が出会ったのは、有紗が学校に行く途中でお腹が痛くなったからなんです。そう考えるとお腹イタも、まあ、時には奇跡を生んでくれるってことになりますかね。でもお腹イタだと、トイレが汚くなるし臭いし、トイレに間に合わないと迷惑をかけるし……ああ、またそれてしまいましたね。どうも、えへへ、トイレの話はがまんがまん、トレはがまんしない、えーっと。
……あの朝。四年ほど前ですかね。有紗は学校に行けず、道端でお腹イタになって、しゃがみこんでいたんです。そこは、町内のゴミ置き場のすぐ横のあたりでした。燃えるゴミの日だったらしいです。有紗はその時、聞いたのです。ピギー、ピギー、という、まるで豚のようなだみ声を。
豚ってねえ、テレビでしか見たことないですけど、あんまり上品な生き物じゃあないですよね。
なんといっても上品なのは、猫ですよねえ。
人間のきみに言うのもなんですが、猫ほど上品な生き物はいない。そう思いませんか。そもそも豚とか牛とかって……おっといけないいけない。
つまり、こういうことです。その豚のようなだみ声の主は、じゃーん、なにを隠そう、僕でした。生後二日で、市の燃えるゴミ袋に詰められて、殺されそうになっていたところを、有紗が気づいて、救出してくれたんです。
どうやら、僕の母親が人の家の庭先で仔を産み、それを不快に思ったその家の人が、庭木の伐採ついでに、僕のこともゴミ袋に詰め込んだらしいですねえ。覚えちゃいないけど。
有紗に聞いたところ、ゴミ袋には、僕しか入っていなかったんですって。濡れた枝木に必死につかまって、ピギー、ピギー、と鳴いていたっていうんですから。兄弟がいたはずですが、母親が一匹ずつ運んで脱出させたか、他の袋に詰められちゃったか。逃げていたならいいな。だって自分と血がつながった兄弟が、目も開かないうちに潰されて死んだなんて、なんともやりきれない話でしょう。
だから。ええ、だから。僕は、有紗に恩があるんですよ。それに、とても心配なんですよ。優しいのに、あんまり優しくされないあの娘が、ちゃんと生きているかなって。
ちゃんと友達がいなくてもいいし、ちゃんと学校に行けてなくてもぜんぜん構わない。
でも、ちゃんと、生きていて欲しいんですよ。
僕がそばにいれば、それを叶えてあげられる。
だから。僕は、毛皮を着替えて、田中有紗に会いにいかねばならないのです。

「なるほどお話はわかりました」
頼子は黒いファイルにざっと目を通し、咳払いをすると、やや事務的な口調で彼に告げた。
「それではこのあと、調査に入りまして、無事に合格となりましたら、毛皮を着替えていただくことになりますので」
「あのう、ひとついいですか」
「はい、なんでもどうぞ」
「不合格になるのは、どういう場合ですか」
この質問はよくされる。
「お相手が……つまり、小次郎さんの場合は、有紗さんですね。有紗さんが、現時点でとてもお幸せで、あなたの存在を受け入れる必要がないほど前向きな感じでいらっしゃった場合は、残念ながら着替えは諦めていただくことに」
田中小次郎は、すう、と目を細めた。
「有紗が、幸せに暮らしていたらってことですか」
「はい」
「それは、ちっとも残念じゃあありません。いやむしろ、そのほうが望ましい」
彼らはこんなふうに、とても健気だ。気まぐれで気位が高いけれど、愛というものを知っている。
「小次郎さん。パンがほどよく冷めました。どうぞ召し上がってください」
頼子がすすめると、小次郎は両手でそっとパンを取った。
まず、すんすんと鼻を近づけて匂いを嗅ぐ。
「ああ、いい匂い」
ぱくり。一口食んで、目を見開く。もう一口。ほわん、とした表情になる。あっという間にひとつを食べ終え、今度は自ら、手を伸ばして次を取る。
「これぜんぶ食べていいのですか」
「いいですよ。小次郎さんのために焼いたのです」
「なんと親切な。パンって、初めて食べましたが、きっと漬物よりもいいものですね」
「漬物も美味しかったと思いますよ。この状況なら」
頼子の前任者は、漬物を出していた。
その前の人は味噌。この土間で、何種類か、自家製味噌を作っていたらしい。
頼子はパン。
全部共通しているのは、発酵食品である、ということ。
頼子がパン作りに使うのは、イースト菌ではなく、自家製酵母だ。発芽玄米を元種にして、まず酵母液を作る。通常、酵母液がさかんに発酵しだすのは、気温二十度で四、五日。そのしゅわしゅわした酵母液を元に、パン作りに使う種を作るのに、さらに三日ほど。
しかしこの家では、すべての工程が二日ほどで終わる。今、頼子が小次郎に出したパンに使用した酵母液は、一昨日の早朝に仕込んだものである。
「パンをふくらませてくれる酵母は、寂しがり屋なんですよ」
あまり話すことは得意ではない。しかし、この家にやってくる客には、どうしてだか、この話をしたくなる。
「仲間に話しかけてもらえると、あっという間に増えるんです。この家にはもともと、酵母の仲間がたくさん住み着いていたんでしょうね。それとうまく呼応するから、美味しいパンができるし、漬物ができたんだと思います」
小次郎は五つ目のパンを食べ終えて深く頷いた。
「それだけじゃあないと思いますねえ」
「というと?」
「パンが美味しいのは、あなたが、優しい手をしているからでしょう」
『あなたはとても優しい手をしている。優しい手をした人には、逃れられない使命があるの』
頼子は、じっと自分の手を見下ろす。乾燥して荒れ気味な手だ。女にしては大きい。節は太く、爪はいつも短い。ネイルなど、生まれてこの方一度もしたことがない。
この手をそっと握ってくれた人のことを思い出し、束の間ぼんやりした。
「優しい手をした人が作るものを食べると、力を得られるんですってね」
小次郎が唇の端についたパンくずを、舌で舐め取って言った。
「ね、僕、最初に言ったでしょ。あなたは、顔は怖いけど、気は優しくて力持ちって」
「……ええ」
「だから僕は、今、もりもり力が湧いて、今すぐにでも、着替えられそうな感じがしています」
「小次郎さん」
「あ、先走っちゃって。すみません。もちろん審査に合格してから」
ほんのり赤くなる小次郎。中年男性の見た目なのに、金魚柄のシャツさえ可愛らしく見えてくる。
「それでは僕は、いったん失礼いたします」
頼子は頷いた。
「はい。では、満月の晩に」
「満月の晩に」
田中小次郎は重々しい声で応じると、入ってきた時と同じ引き戸を開けて、裏庭へと出てゆく。ひたひたと湿った音が遠ざかってから、頼子は自分も外に出てみた。
狭い。すぐそこに竹林と土手が迫っている。
まさに猫の額ほどの裏庭は、しんと静まり返っている。夜風に雑草が揺れ、奥の暗がりに鎮座する小さな祠に、月の光が届いている。
満月まであと三日。時刻は深夜零時を過ぎた頃。いつも、このタイミング。
明日、田中小次郎のもとの飼い主……もとい、家族である、田中有紗の身辺を調査する。
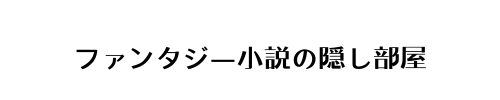


コメント