アルカルドの戸惑い
フィリスが嫁いできて二十日目にして、アルカルドは彼の妻を抱こうとした。
アルカルドは二年という限られた期間内に世継ぎをもうける必要がある。本来、一日の猶予もないはずが、嫁いできたフィリスという娘があまりにも風変わりだったため、アルカルド自身が彼女をどう扱っていいものか考えあぐね、結果、実際的な夫婦となる日を先送りにしてしまっていた。
貴族として生まれたからには、結婚に個人の感情など配慮されないことは覚悟していた。
前の婚約も家同士の取り決めだったし、アルカルドの両親も、祖父母もそうだ。家柄や互いの財産を守るため、時に王命により結婚した。
フィリスとの結婚も王命のためだ。しかし、そんな経緯で結婚した妻は、アルカルドに好きだと言った。
とても真っ直ぐな瞳だった。
アルカルドは、彼女の真摯な緑色の瞳から目が離せなかった。
彼女は変わっているが、アルカルドに向けられる想いは嘘偽りのないもののように感じられる。
しかし、アルカルドは違う。
この婚姻はあくまでも義務と契約の上に成り立っているという認識だ。彼女を抱くべきなのに、そうしなかったのは、自分の中に解決できない、不可解な感情が生じたためである。
彼女と同じ想いは返せないという罪悪感。それを無視し抱いてしまうのは、あまりにも不誠実なような気がした。
しかし、それだけでもない。
アルカルドは昔から、はっきりしないことが許せない性分だ。自分の中の感情にぴたりとはまる名前が見つけられない限り、名ばかりの妻を抱くことはできない。
しかし。
一夜明けて、自分の腕の中で眠る彼女を見た時―――アルカルドは、とても温かな気持ちになった。この無垢な寝顔をずっと見ていたいような、自分の腕の中で守り続けたいような、庇護欲にも似た気持ち。
アルカルドは、それから連日、フィリスと同時に就寝した。仕事を可能な限り早く切り上げ、彼女の体温を感じながら、時に腕の中に抱き寄せて眠った。そうすることで問題が解決するような気がしていたが、さらに分からなくなってゆく。
自分はこの娘をどうしたいのか。
「おはようございます。アルカルド様」
朝、彼女が起きて、花のように微笑むのを見ると、とても美しいと思う。
フィリスは日に日に美しくなっていく。若い従僕が思わず見惚れていることもある。新しく作らせたドレスや、立ち居振る舞いの勉強の成果だけではない。アルカルドに向けられる自然な微笑み、瞳が語る確かな愛と尊敬の気持ち……いまだ形だけの夫婦でありながら、自分の中で何かが折り合いがつかない。
アルカルドの困惑は深まるばかりだ。
フィリスは夕闇が迫る寝室を見渡した。午後のお茶と勉強が終わったので、クロエを下がらせ、ひとりでいる。
衣装室の奥から、嫁入りの日に持参した古びたトランクを引っ張り出し、中から目当てのものを取り出した。
乾燥させた桑の葉と、セージの葉である。それらを二枚の小皿に少量ずつ乗せ、魔法で火をつける。半分くらい燃えたところで火を消し、寝室の入り口の左右に置いた。
煙は薄く立ち上り、やがて空気の流れによって室内に行き渡る。
これで寝室は浄化できた。数日前、自分の体内で浄化するはずの魔を追い出してしまってから、毎日この魔法を行っている。抜け出した魔のかけらが、二度と戻ってこられないように。
同時にアルカルド自身の浄化も継続していた。
毎晩、彼と同時に就寝できるようになって、フィリスは確かな幸福を感じている。しかし一方で、浄化魔法を施す時間の確保には苦労するはめになった。
特に、彼のたくましい腕にすっぽりとくるまれるようにして横になった日には、フィリスも一緒に眠ってしまいそうになる。それを我慢し、彼が完全に根付いてから、浄化魔法にとりかかっている。
身体は辛かった。魔法に使う気力の回復が日を追うに連れ、困難になっている。彼と実際の夫婦になれないのは問題だが、正直なところ、フィリスにもその余裕はない。
フィリスは朝食を、以前よりさらに食べるようになった。
卵料理は二種類。自家製ベーコンやハムも必ず。新鮮なサラダを山盛りで。フルーツは林檎やオレンジを丸一つずつ。ペストリーもすべての種類、だいたい五つか六つ。スープも時にお代わりをする。作法にだけ気をつけて、たくさん食事をする。それだけでは足らず、午前中のお茶にはサンドウィッチも持ってきてもらう。昼も、午後のお茶の時間もそれぞれたっぷりと。そして晩餐には、必ず肉料理を出してもらうようにコルテスにお願いした。
晩餐の肉料理は、疲労回復には欠かせない。剣の鍛錬を再開させたアルカルドにとってもよいはずだ。
ただ、そのアルカルドより、フィリスはたくさん食べてしまうのだ。
「奥様はちっともお太りにならないのですね」
クロエが不思議そうに言う。フィリスは曖昧に笑うばかりだ。アルカルドの治癒魔法のためにたくさん食べなければならないのだとは、とても言えない。
魔法や魔術は、バランデュールの外では禁忌。魔女として火炙りにあった身内も過去にいる。
魔力を保つ一番の方法は、栄養と睡眠。この睡眠が足りていない。そして、侯爵家の舞踏会まであと一週間を切ったある日、とうとう限界が訪れた。
その日、フィリスは朝からドルモアと本家であるロシェル公爵家の歴史について学び、舞踏会で着るドレスの仮縫いをした。その後、アルカルドと例によってダンスの練習をしていた時だ。
急に、目の前が真っ暗になって、フィリスは床に倒れ込んだ。
アルカルドが自分を呼ぶ声が遠くに聞こえたものの、そのまま意識を失ってしまったのだった。
夢の中で、フィリスはまた、去ってゆく母の小舟を追いかけようとしていた。
『フィリス。ごめんなさい。でも分かって。この子は森にいると死んでしまうの。森は、この子の命をすべて吸い取ってしまうから……』

あなたは平気だと母は言った。フィリスは森と蟲に愛されている娘だからと。
でも、フィリスだって母が必要だった。美しくて儚くて、優しくて残酷で、脆かった母が。だから泣いて、必死に追いかけようとして、川に落ち、流されてしまったのだ。
母を乗せた小舟はもうすでに遠くなっていたが、それでもフィリスは気づいてしまった。
母が一瞬、たしかにこちらを見たこと。フィリスが溺れかけていることに、気づいたこと。
それなのに、彼女は戻ってこなかった。
弟を抱いたまま、どこかへ去ってしまったのだ。
「……お母様」
苦しい、苦しい。どうしてこれほど苦しいのだろう。フィリスは夢の中で慟哭している。自分が泣いている声なのか、あの日聞いた絶望的な川の流れの音なのか、定かではないまま。
行かないで、とフィリスはそれでも懇願した。行かないでお母様。わたしを置いていかないで。
「大丈夫だ。ここにいる」
温かで大きな手が、フィリスの手を包み込む。その心地よさに、フィリスは、胸につかえていた苦しみが引くのを感じた。
ああ、そうだ。わたしにはアルカルドがいる。あの日、溺れていたフィリスを助けてくれようとした貴公子が。
彼は今では、フィリスの夫なのだから。
フィリスは安心し、深い眠りに落ちた。
目覚めた時は寝台に寝かされていた。夜着を着て、髪はほどかれていた。頭がいくぶんすっきりとしている。部屋にいたクロエが安堵したような顔で側まで来た。
「奥様、良かった。お目覚めですね」
「わたし、どうしたの?」
「ダンスの練習中にお倒れになったのです。すぐにお医者様に来ていただいて、診ていただきました。疲れがたまっているのだろうと。眠っているだけだから、大丈夫だとおっしゃって」
「そうね。寝たらすっきりしたわ」
「旦那様を呼んでまいりますね」
クロエは出ていった。フィリスは額に手をあてる。なんということだ。自分ではぎりぎりうまくやっていると思っていたのに。どうしたものか、と思案しているところに、荒々しい足音が響いて、アルカルドが飛び込んできた。
「アルカ……」
アルカルドは大股で寝台に近づくと、
「起きて大丈夫なのか」
と聞いた。
「はい。ご迷惑をおかけしました。こんなことは初めてで……」
「やはり無理をさせてしまっていたのだな。倒れるほど疲れが溜まっていたとは」
それは違う。フィリスはむず痒かった。生家でのフィリスの暮らしに比べれば、今は毎日遊んで暮らしているようなものだ。
なにしろ食材の調達から下準備と料理、家事全般、畑の手入れ、蚕の飼育、繭の管理、古い城の壁の補修まで、フィリスは毎日朝から晩まで働いていた。
ただし、身体は疲れても、気力が途切れることはなかった。森が力をくれた。夜は鳥や虫の音を聞きながら、ぐっすりと深く眠り、朝は太陽と共に起き出した。
「丈夫なのが唯一の取り柄です。だから、少し休めば大丈夫です」
「君の取り柄はひとつだけではないがな」
苦笑してそう言われ、フィリスはまた照れてしまう。
「そ、そうでしょうか……」
「フィリス。前にも言ったが、具合が悪い時は正直に言ってくれ。そして十分に休んで欲しい」
「でも……」
反論しかけて口をつぐむ。でも旦那様。あなたの腕の怪我は、あと少しで完治できるのです。すると、
「……君には言っていなかったが、俺は先般の戦で負傷した」
アルカルドの方から、そのことを口にした。フィリスは非常に驚いた。怪我については、絶対に触れられたくない様子だったのに。
アルカルドはおもむろに、シャツを脱いだ。彼の裸を見るのは初めてだ。フィリスはどきどきしたが、努めて顔には出さないようにし、じっと彼の話を待った。
たくましい上半身と、右腕に、手の形の痣が残っているのが確認できる。だいぶ、薄くなっている。それに伴って、痛みや苦痛も減っているはず。
「先の戦で、魔物に噛まれたのだ」
「……魔物に」
「信じるか? 人間が、魔獣に変わった。人の腕が蛇に変じ、俺に噛み付いた。男は絶命の瞬間、呪いの言葉を口にした」
「信じます」
フィリスはそっと言った。アルカルドは、唇を歪める。
「俺はそれまで信じていなかった。この世に魔性が存在するなど。物語や歴史の中ならいざしらず」
「…………」
フィリスはなんと答えていいのか分からず黙り込む。
「俺が部隊を離れ、領地に戻ったのはこの傷のためだ。ほとんど剣も使えず、自尊心もぼろぼろだった。しかしもっとも良くなかったのは、この身に負った傷のことや、心に負った苦しみを、医者以外、誰にも言わなかったことだな。矜持が高すぎて、弱みを見せることができなかった」
「……なぜ、わたしに教えてくださるのですか」
震える声でフィリスはたずねる。するとアルカルドは、フィリスをじっと見つめ、こう答えた。
「俺には、やはり、君が何か無理をしているように見える。つい先日までの俺と同じように。無理をするから、身体が悲鳴をあげているのかもしれぬ。それは、俺の望むことではない。前にも言ったが、君には、健やかに過ごしてもらいたい」
「アルカルド様……」
「しかし、顧みて、自分は君にすべてをさらけだしていないことに気づいた」
「だから教えてくださったのですね」
「そうだ。俺は心身を負傷し、自暴自棄なまま、君と結婚した。君は俺を好きだと言ってくれたが、俺は君に誠実ではなかった。己のちっぽけな矜持にしがみつき、この不名誉な負傷のことさえ伝えてはいなかったから」
唐突に。フィリスは目の奥が熱くなり、思わず目を伏せた。
睫毛が震える。下唇を軽く噛み、込み上げてくるものを抑える。アルカルドは、フィリスの閨での告白を、それほど真剣に受け止めてくれたというのか。
アルカルドの言葉は嬉しい。しかし不誠実なのはフィリスの方かもしれない。できれば真実を告げてしまいたい。しかし言えない。
わたしは魔術が使えるのです。人はわたしのような女を、魔女と呼びます……。
露見してしまったら。森に帰らねばならなくなる。そしてフィリスは、帰りたくはない。まだ……できれば、生涯、彼と共にあり、添い遂げたい。
二年。はじめにこの取り決めを聞いた時は、自分は幸運だと思った。たとえ数日でも、彼の隣にいられるなら。しかし今は、あまりにも短いと感じる。
フィリスはいつの間にか、すっかり強欲になってしまったのだ。
そんな自分が恐ろしい。
自分の欲で、アルカルドを困らせてはならない。まして彼に心配をかけるのは申し訳ない。
「……アルカルド様。実はわたしは、幼い頃から、疲れすぎてしまうと突然眠ってしまうことがあるのです」
できれば嘘はつきたくない。だから、無難な真実だけを、言葉を選んで告げる。
「それを防ぐために、日々たくさん食事をいただきます。でも、食事でも疲れが取れない場合には、眠ってしまうのです」
アルカルドは真面目な顔でフィリスの話を聞いている。
「そんなことがあるのだな」
「一族に特有の体質かもしれません。伯母たちや、従姉妹もそうだと申しておりました」
「母君もか?」
突然、母のことを聞かれ、フィリスは驚いた。
「……え?」
「俺はあなたから親族の話は聞いたが、母君や弟君の、詳しい事情は聞いていない」
フィリスは少しの間黙り込んだ。確かにそうだ。
「差し障りのない範囲で構わない。母君について、よかったら聞かせてくれ」
フィリスは頷き、さらに言葉を選びながら話すことを決める。
「……母は、わたしが八歳の時に、領地を出て行ったのです。弟のシモンを連れて。すべては、弟が無事に成長するためだったと思います。バランデュールでは、男子は生まれても夭折すると言われていますから」
「だから代々女伯爵であるわけか」
「そのようです。領地の外側……森の外でなら、無事に育つと」
「王はそのことをご存知か」
「はい」
「……なるほど。そのため、男子ならエントワーズの後継ぎとして残し、女子なら領地に連れ帰るという契約になったのだな」
「そうだと思います」
子供を産んだことはないが、自分の子を手放すのは非常に苦しいだろう。だからフィリスは、母を恨もうとは思わない。八歳だったフィリスと、赤子だった弟。母は選択しなければならなかったのだ。
しかし。
「君は、辛かったのだな」
つぶやくようにアルカルドは言う。フィリスは驚き、目を見張った。
「……辛い?」
そんな感情を見せてしまっただろうか? 母の話もほとんどしていないのに? それともまさか、あの時のことを思い出してくれたのだろうか?
「アルカルド様。わたし……」
「君は、母を呼んでいた」
「え?」
「倒れ、眠りについている時。母を必死に呼んでいた。それで気になって訊いた」
フィリスは内心で焦った。まさか、醜態をさらしてしまったのでは。
「ほかに、何か言っていましたか?」
「ああ。確か、行かないでと」
フィリスは黙り込んだ。アルカルドは、その沈黙に長く付き合っていたが、やがて穏やかな声で言った。
「もうしばらく休め。これからは、どんな時であろうと、疲れを感じたら横になるがいい。ドルモアにも伝えておく」
「あ、ありがとうございます」
アルカルドは微笑み、立ち上がると、ふと思いついたように身を屈め、フィリスの額に口づけをした。
フィリスは笑おうとしたがうまくいかず、ぼんやりと、夫が部屋を出ていくのを見送った。
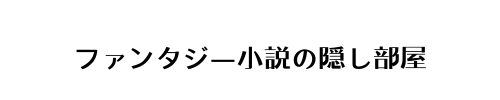



コメント